-ナレの村-1.カケルとイツキ [アスカケ第1部 高千穂峰]
「イツキ!もう戻ろう。」
高千穂の峰から流れ出る渓流に、膝まで浸かって、銛を片手にしたカケルが呼ぶ。腰につけた竹籠には、ヤマメや鮎が何尾も入っていた。
カケル8歳。まだ少年だが、自然の中でのびのびと育ち、溌剌とした眼差しには、生きる命の輝きを感じさせた。
「ええ?もう帰るの?」
山桃の木の枝の間から、鈴の音のような透き通った声が返ってきた。
声の主は、イツキだった。
カケルと同い年。イツキの母は、イツキが生まれた年に病気で亡くなり、父も3歳の時に亡くした為に、ナギとナミの夫婦に、カケルと兄妹同然に育てられたのだった。目覚める時から眠るまで、イツキはカケルの後を追うようにして、一日をともに過ごしていた。
「魚は、たくさん獲れたし、もう日が沈む。早く戻らないと道を失う。」
カケルの声に、イツキは山桃の木の枝をするすると降り、カケルのいる川岸にやってきた。腰の籠には、山桃の実が溢れるほど入っている。
カケルは、とても8歳の子どもとは思えない跳躍力で、水から飛び上がると、大岩の上を三つほど跳ねてから、川岸にたどり着いた。
二人は、蔓を手に、川岸から山道に上がり、深い森をぬうように駆けた。
「カケル!少しゆっくり駆けてよ。せっかくのヤマモモがこぼれちゃった。」
突然、カケルが止まった。
「どうしたの?」
「シッ!」
カケルは辺りの様子をじっと伺っていた。夕暮れになり、森の中にはじんわりと暗闇が広がり始めていた。ふいに、カケルは、上を見上げ、眼を凝らした。そして、少し先にある楠の大木に一気に登り始めた。下から3つほどの枝先に移ると、さらにその先に進んでいく。
「やっぱり、ここにいたのか。」
カケルはそういうと何かを抱えて、一気に枝先から下へ飛び降りた。
「カケル。何があったの?」
カケルの腕には、まだ幼鳥と思える「鷹」が抱えられていた。
「まだ、うまく飛べないのかな?」
腕に抱えられた鷹は、ピーピーと鳴きながら、時折、カケルの腕に鋭い嘴を突きたてようとしたり、鋭い爪で何かをつかもうとした。
「もう大丈夫だよ。」
カケルはそう言いながら、鷹の様子を見た。
「こいつ、怪我してるみたいだな。連れて帰ってやろう。」
そう言うと、また、先ほどのような速さで、山道を駆け出したのだった。
尾根を越えたところに、「ナレ」の村はあった。夕暮れには、獣除けの為に、檜で作った分厚い門を閉ざしていた。
「おお、カケルとイツキが戻ってきた。・・門を開けよ!」
高楼の上から、長老が声をかけた。門の傍に居た数人の男が、獣除けの分厚い門をわずかに開いた。カケルとイツキは、その隙間にすべり込むように村に入ってきた。そしてそのまま、カケルとイツキは、父母の待つ家へ駆け込んだ。

高千穂の峰から流れ出る渓流に、膝まで浸かって、銛を片手にしたカケルが呼ぶ。腰につけた竹籠には、ヤマメや鮎が何尾も入っていた。
カケル8歳。まだ少年だが、自然の中でのびのびと育ち、溌剌とした眼差しには、生きる命の輝きを感じさせた。
「ええ?もう帰るの?」
山桃の木の枝の間から、鈴の音のような透き通った声が返ってきた。
声の主は、イツキだった。
カケルと同い年。イツキの母は、イツキが生まれた年に病気で亡くなり、父も3歳の時に亡くした為に、ナギとナミの夫婦に、カケルと兄妹同然に育てられたのだった。目覚める時から眠るまで、イツキはカケルの後を追うようにして、一日をともに過ごしていた。
「魚は、たくさん獲れたし、もう日が沈む。早く戻らないと道を失う。」
カケルの声に、イツキは山桃の木の枝をするすると降り、カケルのいる川岸にやってきた。腰の籠には、山桃の実が溢れるほど入っている。
カケルは、とても8歳の子どもとは思えない跳躍力で、水から飛び上がると、大岩の上を三つほど跳ねてから、川岸にたどり着いた。
二人は、蔓を手に、川岸から山道に上がり、深い森をぬうように駆けた。
「カケル!少しゆっくり駆けてよ。せっかくのヤマモモがこぼれちゃった。」
突然、カケルが止まった。
「どうしたの?」
「シッ!」
カケルは辺りの様子をじっと伺っていた。夕暮れになり、森の中にはじんわりと暗闇が広がり始めていた。ふいに、カケルは、上を見上げ、眼を凝らした。そして、少し先にある楠の大木に一気に登り始めた。下から3つほどの枝先に移ると、さらにその先に進んでいく。
「やっぱり、ここにいたのか。」
カケルはそういうと何かを抱えて、一気に枝先から下へ飛び降りた。
「カケル。何があったの?」
カケルの腕には、まだ幼鳥と思える「鷹」が抱えられていた。
「まだ、うまく飛べないのかな?」
腕に抱えられた鷹は、ピーピーと鳴きながら、時折、カケルの腕に鋭い嘴を突きたてようとしたり、鋭い爪で何かをつかもうとした。
「もう大丈夫だよ。」
カケルはそう言いながら、鷹の様子を見た。
「こいつ、怪我してるみたいだな。連れて帰ってやろう。」
そう言うと、また、先ほどのような速さで、山道を駆け出したのだった。
尾根を越えたところに、「ナレ」の村はあった。夕暮れには、獣除けの為に、檜で作った分厚い門を閉ざしていた。
「おお、カケルとイツキが戻ってきた。・・門を開けよ!」
高楼の上から、長老が声をかけた。門の傍に居た数人の男が、獣除けの分厚い門をわずかに開いた。カケルとイツキは、その隙間にすべり込むように村に入ってきた。そしてそのまま、カケルとイツキは、父母の待つ家へ駆け込んだ。

-ナレの村-2.ヤマモモ [アスカケ第1部 高千穂峰]
2.ヤマモモ
「良かった。日暮れ前に戻ってきたな。」
父ナギが、縄を編みながら、家の中に飛び込んできた二人に、声を掛けた。
カケルの父、ナギは村で一番の縄作り名人であった。ナギの作る縄は、太く強く風雨に曝されても切れることがなかった。村を出てすぐのところにある谷を渡る縄橋や、裏山の崖に上る縄梯子もナギの手によるものだった。
「獲物はどうだ?見せてみろ。」
そういうとナギは、カケルの腰から籠を取り上げて、中を覗いた。
「ほう、たくさん獲ったな。」
「うん、西の谷にある二つ岩の向うまで行ってみたんだ!」
「そうか、あんなところまで行ってたのか。」
「そこにはね、深い淵があったんだ。そこに潜ったら、たくさん魚がいたよ。」
「ほう、良い場所を見つけたな。今度は、一緒に行こう。」
「うん。とと様なら、もっとたくさん獲れるよ。」
「ああ・・だがなあ、タケル。そんなにたくさん獲ってはいけないぞ。魚も命があるんだ。大事にせねばならない。自分たちが食べる分だけにしておかないといけない。・・それと、淵に入る前にはしっかりお祈りをするんだ。淵の神様に許しをもらってからにするんだぞ。」
「うん・・今日も、ちゃんとお祈りをしたよ。」
そう言って、地に両手をつき、深々と頭を下げ、いにしえの祈りの言葉を発した。
「ね・・これでいいんでしょ。」
「ああ、上出来だ。ちゃんとやるんだぞ。カケルは良い子だ。」
父の言葉に、カケルは得意な笑顔を見せて、家の中を跳ねてみせた。竃の火加減をみていた母ナミも微笑んでみていた。
「良かったね、カケル。・・イツキはどうしたの?」
「うん。イツキは山桃の実をたくさん採ったよ。」
その返事に、ナミとナギは顔を見合わせた。そして、ナミはナギに何かを確認するように頷いてから、静かに訊いた。
「そのヤマモモの木は大きかったの?」
「うん。とっても大きかった。川の傍に立ってて、両手をうんと伸ばしたような格好をしてたんだ。カケルが魚を獲る間に、私、そこに登って実を摘んだんだ。」
「そう、たくさん取れたのね。」
その会話を聞いていたナギが立ち上がり、イツキの傍に座り、イツキの背に手を当ててから優しい声で話し始めた。
「イツキ、よく聞きなさい。その山桃の木は、イツキの父様の樹なんだよ。」
ナギの言葉の意味がよくわからず、イツキはナギの顔を見た。
「イツキはきっと覚えていないだろうが、お前の母様が死んでから、父様はいつもお前をつれて、畑や猟にも行っていた。ある日、西の谷の向うにある畑に行く途中、大きな熊が出たんだ。」
「熊?でも、熊は人を襲わないでしょ?優しいもの。」
イツキが訊いた。
「ああ、熊は人は襲わない。だが、その熊は手傷を追っていたんだ。どこかで喧嘩をしたのか、あるいは、ほかの村人が傷を負わせたか・・とても興奮していた。そして、畑に向かっていた娘たちを襲いそうだったんだ。お前の父様は、何とか止めようとして、熊に矢を放ち、見事に当たった。だが、すぐに父様のほうに向かって走ってきた。・・お前をおぶっていた父様は、西の谷へ降りた。熊はどんどん近づいてくる。父様はとっさにお前を大きな山桃の樹の高い枝に乗せてから、熊から守ろうとした。」
「父様はどうなったの?」
「山桃の樹から離すために、川へ入った。熊は追いかけて行って、父様に手をかけたんだ。娘たちが村に知らせに来てから、俺もすぐに行ったんだが・・もう駄目だった。」
イツキは、父の最期の様子を初めて聞かされ、驚いた様子で言葉が出なかった。その様子を見ていたナミが、
「イツキ、今日、実を摘んだ山桃の樹は、イツキの命を守ってくれた樹なのよ。そう、イツキの父様の代わりにね。だから、イツキの父様の樹なの。」
その言葉に、イツキが不意に涙が零れはじめ、止まらなくなった。昼間、実を摘みながら、どこか懐かしく、温かな気持ちになれたのを思い出して、さらに泣いた。ナミはイツキを抱きしめながら、
「今日、そこに行ったのは、きっと父様がお前に会いたいと思っていたからじゃないかしらね。時々、会いに行くといいわ。」
その様子を眺めていたカケルが、
「そうだ。今度、母様も一緒に行こう。父様と僕は魚を獲る。母様とイツキは山桃の実を摘んで来よう。」
「そうね。そうしましょう。・・ほら、カケル!串を打ったから、やぐらのところへ持っていきなさい。もう、宴の仕度もほとんど済んでいるだろうから。・・それとこれも一緒に・・」
母ナミは、黍で作った団子を盛った皿をカケルに渡した。

「良かった。日暮れ前に戻ってきたな。」
父ナギが、縄を編みながら、家の中に飛び込んできた二人に、声を掛けた。
カケルの父、ナギは村で一番の縄作り名人であった。ナギの作る縄は、太く強く風雨に曝されても切れることがなかった。村を出てすぐのところにある谷を渡る縄橋や、裏山の崖に上る縄梯子もナギの手によるものだった。
「獲物はどうだ?見せてみろ。」
そういうとナギは、カケルの腰から籠を取り上げて、中を覗いた。
「ほう、たくさん獲ったな。」
「うん、西の谷にある二つ岩の向うまで行ってみたんだ!」
「そうか、あんなところまで行ってたのか。」
「そこにはね、深い淵があったんだ。そこに潜ったら、たくさん魚がいたよ。」
「ほう、良い場所を見つけたな。今度は、一緒に行こう。」
「うん。とと様なら、もっとたくさん獲れるよ。」
「ああ・・だがなあ、タケル。そんなにたくさん獲ってはいけないぞ。魚も命があるんだ。大事にせねばならない。自分たちが食べる分だけにしておかないといけない。・・それと、淵に入る前にはしっかりお祈りをするんだ。淵の神様に許しをもらってからにするんだぞ。」
「うん・・今日も、ちゃんとお祈りをしたよ。」
そう言って、地に両手をつき、深々と頭を下げ、いにしえの祈りの言葉を発した。
「ね・・これでいいんでしょ。」
「ああ、上出来だ。ちゃんとやるんだぞ。カケルは良い子だ。」
父の言葉に、カケルは得意な笑顔を見せて、家の中を跳ねてみせた。竃の火加減をみていた母ナミも微笑んでみていた。
「良かったね、カケル。・・イツキはどうしたの?」
「うん。イツキは山桃の実をたくさん採ったよ。」
その返事に、ナミとナギは顔を見合わせた。そして、ナミはナギに何かを確認するように頷いてから、静かに訊いた。
「そのヤマモモの木は大きかったの?」
「うん。とっても大きかった。川の傍に立ってて、両手をうんと伸ばしたような格好をしてたんだ。カケルが魚を獲る間に、私、そこに登って実を摘んだんだ。」
「そう、たくさん取れたのね。」
その会話を聞いていたナギが立ち上がり、イツキの傍に座り、イツキの背に手を当ててから優しい声で話し始めた。
「イツキ、よく聞きなさい。その山桃の木は、イツキの父様の樹なんだよ。」
ナギの言葉の意味がよくわからず、イツキはナギの顔を見た。
「イツキはきっと覚えていないだろうが、お前の母様が死んでから、父様はいつもお前をつれて、畑や猟にも行っていた。ある日、西の谷の向うにある畑に行く途中、大きな熊が出たんだ。」
「熊?でも、熊は人を襲わないでしょ?優しいもの。」
イツキが訊いた。
「ああ、熊は人は襲わない。だが、その熊は手傷を追っていたんだ。どこかで喧嘩をしたのか、あるいは、ほかの村人が傷を負わせたか・・とても興奮していた。そして、畑に向かっていた娘たちを襲いそうだったんだ。お前の父様は、何とか止めようとして、熊に矢を放ち、見事に当たった。だが、すぐに父様のほうに向かって走ってきた。・・お前をおぶっていた父様は、西の谷へ降りた。熊はどんどん近づいてくる。父様はとっさにお前を大きな山桃の樹の高い枝に乗せてから、熊から守ろうとした。」
「父様はどうなったの?」
「山桃の樹から離すために、川へ入った。熊は追いかけて行って、父様に手をかけたんだ。娘たちが村に知らせに来てから、俺もすぐに行ったんだが・・もう駄目だった。」
イツキは、父の最期の様子を初めて聞かされ、驚いた様子で言葉が出なかった。その様子を見ていたナミが、
「イツキ、今日、実を摘んだ山桃の樹は、イツキの命を守ってくれた樹なのよ。そう、イツキの父様の代わりにね。だから、イツキの父様の樹なの。」
その言葉に、イツキが不意に涙が零れはじめ、止まらなくなった。昼間、実を摘みながら、どこか懐かしく、温かな気持ちになれたのを思い出して、さらに泣いた。ナミはイツキを抱きしめながら、
「今日、そこに行ったのは、きっと父様がお前に会いたいと思っていたからじゃないかしらね。時々、会いに行くといいわ。」
その様子を眺めていたカケルが、
「そうだ。今度、母様も一緒に行こう。父様と僕は魚を獲る。母様とイツキは山桃の実を摘んで来よう。」
「そうね。そうしましょう。・・ほら、カケル!串を打ったから、やぐらのところへ持っていきなさい。もう、宴の仕度もほとんど済んでいるだろうから。・・それとこれも一緒に・・」
母ナミは、黍で作った団子を盛った皿をカケルに渡した。

タグ:霧島 ヤマモモ
-ナレの村-3.篝火 [アスカケ第1部 高千穂峰]
村の真ん中の広場には、大きな篝火が焚かれていた。夕日が沈み、辺り一面、夜の闇が広がり始めていて、篝火の明かりが村中を照らしていた。
それぞれの家々から、男も女も手に手に食べ物を抱えて、篝火の周りに集まり始めていた。
儀式の合図の銅鐸が打ち鳴らされた。
今宵は、アスカケの道へ旅立つ若者の、旅の無事を祈る儀式が開かれるのだった。
巫女の「セイ」が、紅花で染めた衣を纏い、勾玉の首輪を幾重にも飾りつけ、頭には鷹の羽で飾った冠のいでたちで、ゆっくりと高楼に姿を現わした。
すぐ、後ろに、村の長老「テイシ」が続く。テイシも同じようないでたちだった。そして、少し離れて、アスカケに出る若者「ケスキ」が続いた。
ケスキは今年で15になる。この村で生まれ、この村で育った。ケスキは父に似て筋骨隆々の大男だった。村の命たちにも、力自慢では負けないほどだった。
村の者たちは、篝火の周りに座り、高楼を見上げ、静まった。
セイは、いにしえより伝わる、祈りの言葉を唸りながら、高楼に設えられた神台に高く積まれた「ゆずり葉」を手に取ると四方に撒き始めた。そして、ケスキの前に行くと、勾玉の首飾りをひとつ外すと、ケスキの首にかけてから、ケスキの額に紅を使って、一族の証の印を付けた。
一通りの祈りの儀式が終わると、長老のテイシが高楼から下に向かって声を出した。
「明日朝、ケスキはアスカケへ出る。今宵は、皆で命の息を分けてやってくれ。」
その声を合図に、篝火の脇に置かれた打木を男たちが叩き始める。笛の音が響き、その音色に乗せて、女たちが舞う。そして、それぞれに持ち寄ったご馳走に手をつける。長老から順番に濁酒が酌み交わされる。男も女も、皆、次々にケスキの隣に座り、声を掛け背を叩く。これが、長老の言った「命の息を吹き込む」風習であった。
若い娘たちは、透き通るほど薄く織られた絹の衣を首から肩へ掛け、優雅に舞う。次第に、笛の音が大きく響き、男たちも混ざって、にぎやかな踊りへと変わっていく。そのうち、踊りつかれた娘が、カケルたちの座っているところにやってきた。そして、イツキに手を伸ばし、踊りに誘った。イツキは、戸惑っていた養子だったが、ナミが、こう言った。
「行っておいで。イツキの母様も、踊りが上手だったから。きっとイツキもうまく踊れるはずよ。さあ。」
イツキは、その言葉ににこりと頷き、娘から羽衣を掛けられ、踊りの輪の中へ入っていった。
篝火に照らされたイツキは、ナミが言ったとおりに、娘たちの中でも負けないほどに、美しく踊った。カケルもつられて踊りの輪の中へ入っていった。
にぎやかな宴は続いていた。皆、濁酒を酌み交わし、踊り、歌い、それぞれに入れ替わり、ケスキの傍に来て声を掛けていた。
その宴の脇で、じっとケスキの様子を見つめ、涙を零す娘がいた。ナミが静かに近寄り、隣に座った。
「大丈夫よ、きっと戻ってくるわ。」
娘はこくりと頷き、ナミにもたれかかるようにして声を殺して泣いた。
「ケスキは、この村でやりたいことがあるんでしょ?だからきっと戻ってくる。」
娘は、ナミの胸に顔を埋めたまま、小さく言った。
「・・海に出るって・・・ケスキの父様も命を落としかけたって・・」
「でも、ちゃんと村に戻ってきたでしょう。貴方もケスキを信じて待っていましょう。」
アスカケに出る青年に恋心を抱く娘。村に戻る青年にその事を伝えてはならないのが、村の女たちの掟になっていた。アスカケへ出かける青年が、自分の生きる道を定めるための過酷な旅を途中で挫折しないための女たちの精一杯の思いなのであった。

それぞれの家々から、男も女も手に手に食べ物を抱えて、篝火の周りに集まり始めていた。
儀式の合図の銅鐸が打ち鳴らされた。
今宵は、アスカケの道へ旅立つ若者の、旅の無事を祈る儀式が開かれるのだった。
巫女の「セイ」が、紅花で染めた衣を纏い、勾玉の首輪を幾重にも飾りつけ、頭には鷹の羽で飾った冠のいでたちで、ゆっくりと高楼に姿を現わした。
すぐ、後ろに、村の長老「テイシ」が続く。テイシも同じようないでたちだった。そして、少し離れて、アスカケに出る若者「ケスキ」が続いた。
ケスキは今年で15になる。この村で生まれ、この村で育った。ケスキは父に似て筋骨隆々の大男だった。村の命たちにも、力自慢では負けないほどだった。
村の者たちは、篝火の周りに座り、高楼を見上げ、静まった。
セイは、いにしえより伝わる、祈りの言葉を唸りながら、高楼に設えられた神台に高く積まれた「ゆずり葉」を手に取ると四方に撒き始めた。そして、ケスキの前に行くと、勾玉の首飾りをひとつ外すと、ケスキの首にかけてから、ケスキの額に紅を使って、一族の証の印を付けた。
一通りの祈りの儀式が終わると、長老のテイシが高楼から下に向かって声を出した。
「明日朝、ケスキはアスカケへ出る。今宵は、皆で命の息を分けてやってくれ。」
その声を合図に、篝火の脇に置かれた打木を男たちが叩き始める。笛の音が響き、その音色に乗せて、女たちが舞う。そして、それぞれに持ち寄ったご馳走に手をつける。長老から順番に濁酒が酌み交わされる。男も女も、皆、次々にケスキの隣に座り、声を掛け背を叩く。これが、長老の言った「命の息を吹き込む」風習であった。
若い娘たちは、透き通るほど薄く織られた絹の衣を首から肩へ掛け、優雅に舞う。次第に、笛の音が大きく響き、男たちも混ざって、にぎやかな踊りへと変わっていく。そのうち、踊りつかれた娘が、カケルたちの座っているところにやってきた。そして、イツキに手を伸ばし、踊りに誘った。イツキは、戸惑っていた養子だったが、ナミが、こう言った。
「行っておいで。イツキの母様も、踊りが上手だったから。きっとイツキもうまく踊れるはずよ。さあ。」
イツキは、その言葉ににこりと頷き、娘から羽衣を掛けられ、踊りの輪の中へ入っていった。
篝火に照らされたイツキは、ナミが言ったとおりに、娘たちの中でも負けないほどに、美しく踊った。カケルもつられて踊りの輪の中へ入っていった。
にぎやかな宴は続いていた。皆、濁酒を酌み交わし、踊り、歌い、それぞれに入れ替わり、ケスキの傍に来て声を掛けていた。
その宴の脇で、じっとケスキの様子を見つめ、涙を零す娘がいた。ナミが静かに近寄り、隣に座った。
「大丈夫よ、きっと戻ってくるわ。」
娘はこくりと頷き、ナミにもたれかかるようにして声を殺して泣いた。
「ケスキは、この村でやりたいことがあるんでしょ?だからきっと戻ってくる。」
娘は、ナミの胸に顔を埋めたまま、小さく言った。
「・・海に出るって・・・ケスキの父様も命を落としかけたって・・」
「でも、ちゃんと村に戻ってきたでしょう。貴方もケスキを信じて待っていましょう。」
アスカケに出る青年に恋心を抱く娘。村に戻る青年にその事を伝えてはならないのが、村の女たちの掟になっていた。アスカケへ出かける青年が、自分の生きる道を定めるための過酷な旅を途中で挫折しないための女たちの精一杯の思いなのであった。

-ナレの村-4.ナギのアスカケ [アスカケ第1部 高千穂峰]
4.ナギのアスカケ
「ねえ、アスカケって何?」
踊り疲れ、父母の元へ戻ったイツキは、昼間に摘んできた山桃の実を摘まみながら言った。カケルは、黍団子を何個か口に入れて、自分も確かな事を知らないのを誤魔化すようにもごもごと答えた。
脇で、濁酒の入った竹筒を口に運びながら、ほろ酔い気味の父ナギが答えた。
「アスカケは、自分を見つけるための旅だよ。」
父の言葉の意味は6歳の子どもには充分に理解できず、カケルもイツキも顔を見合わせた。
アスカケの道とは、村を出て、九重の山々を超え、まだ見ぬ世界で自らの生きる意味を問う旅であり、その終着点は自ら決める。村を出て、短い期間で村に戻ってもよし、一生放浪を続けてもよし、ただ、ひとつ、自らの生きる意味を見つける事とされている。
これまで、アスカケの道に旅立った男の半数は村に戻り、村のために自らの生きる意味を心に留め、ひたすらに生きている。半数は行方知れずだが、アスカケから戻った男からの話で、消息のわかるものも居た。村に戻った男はほとんどが村の外から嫁を連れて帰ってくる。
そう、アスカケの道は、外の世界との交流の乏しい高千穂の山間の村にとって、血が濃くならないための自衛の手段でもあった。また、外界の情報を得て、時代を進める力にもなっているのであった。そして、この時代、九重の国の村々にはみな同じような掟があった。
「父(とと)様の、アスカケはどんなだったの?」
カケルは、自分で獲ってきたヤマメの串焼きを手にしながら訊いた。隣にいたイツキも興味深げな顔でナギを見た。ナギは、もう一口、濁酒を飲むと、篝火をぼんやり見つめながら話し始めた。
「俺のアスカケは、御山を越え、九重の山を目指した道だった。御山を越えると、もっと大きな山が連なっていた。見えるものはすべて深い森。そこを何日も何日も歩いた。いよいよ疲れ果て、もう歩けないと思った先に、ウスキという村があった。」
「そこはどんなところだったの?」
カケルは、食べるのを止め、じっと父ナギの顔を見ている。イツキもカケルの横で同じようにナギの顔を見ていた。
「そこは・・・ナレとよく似た村だが・・ここよりも小さく、暮らしは厳しい。俺が辿り付いた時は冬。ここより寒さが厳しくて、凍えるようだった。だが、皆、優しかった。・・おお、そうだ、そうだ。その村には、深い深い底なしの淵があった。その淵には、大きな主がいた。村のものは、毎朝、淵でお祈りをし、主を宥めてから、魚を獲らせてもらっていたんだ。」
「とと様も獲った?」
「いや、淵に入れるのは選ばれたものだけだった。俺は、その村の長老に世話になった。村の中でいろんな仕事をした。そして、縄を編む事を教えてもらった。・・それが俺のアスカケだと決めたんだ。」
「縄を編む事がとと様のアスカケ?」
「ああ・・ナレの村も谷が深い。お前たちが獲物を取りにいくとしても、深い谷を降り、また登り、時には谷底に落ちる事もある。・・ウスキの村も同じだった。だから、強い強い縄を作り、谷に縄橋を掛ければ皆安心して獲物を獲りにいけるだろう。」
「じゃあ、西の谷の橋もとと様が掛けたの?」
「ああ、そうだ。あそこだけじゃない。御山へ向かう道にもいくつか作った。もっともっと作って村の人が楽に行けるようにしたいんだ。」
「ふーん。」
カケルとイツキは、感心したようにナギの顔を見ていた。
「それとなあ・・かか様に出会ったのも、そのウスキの村だったんだ。」
「え?かか様は、ウスキの村にいたの?」
カケルは初めて聞いた話に驚き、脇に座っていた、母ナミの顔を見た。ナミはにっこりと微笑んでからゆっくりと口を開いた。
「ええ、そうよ。ナギ様は、とても疲れていてね、しばらく動けなくなっていて、私が介抱したのよ。・・元気になるまでの間、毎日のように、ナレの村の話を聞いていたわ。」
「それで?」
「ナギ様は元気になって、ウスキの村で一生懸命仕事をしたわ。壊れた家を直したり、堀を大きくしたり、田んぼも作ってくれた。村の人は皆、ナギ様を信頼した。私のとと様もすっかり気に入って、二人が一緒になる事を許してくださったのよ。ナギ様が縄編みを覚えた頃、二人で一緒にナレの村に戻ってきたのよ。」
「へえ・・そうだったの。ウスキの村かあ・・僕もいつか行ってみたいなあ。」
「そうね、じじ様やばば様に会えると良いわね。」
夜の闇空に、篝火が赤々と燃え、夜は更けていった。
旅立ちの儀式と祝いの宴も終わり、それぞれ皆家に戻って行った。
カケルは、寝床に入ってからも、父や母に聞いた話を思い出し、胸の中が妙に高鳴るのを抑え切れなくてなかなか寝付けなかった。頭の中に、まだ見ぬ高千穂の峰からの風景や、その先に続く九重の山々、そして、その中にひっそりと存在するウスキの村。紺碧に輝く底なしの淵とそこに住む大きな主。いつしか、カケルは夢の中で、その主にまたがり、淵の中を泳ぎまわっていたのだった。

「ねえ、アスカケって何?」
踊り疲れ、父母の元へ戻ったイツキは、昼間に摘んできた山桃の実を摘まみながら言った。カケルは、黍団子を何個か口に入れて、自分も確かな事を知らないのを誤魔化すようにもごもごと答えた。
脇で、濁酒の入った竹筒を口に運びながら、ほろ酔い気味の父ナギが答えた。
「アスカケは、自分を見つけるための旅だよ。」
父の言葉の意味は6歳の子どもには充分に理解できず、カケルもイツキも顔を見合わせた。
アスカケの道とは、村を出て、九重の山々を超え、まだ見ぬ世界で自らの生きる意味を問う旅であり、その終着点は自ら決める。村を出て、短い期間で村に戻ってもよし、一生放浪を続けてもよし、ただ、ひとつ、自らの生きる意味を見つける事とされている。
これまで、アスカケの道に旅立った男の半数は村に戻り、村のために自らの生きる意味を心に留め、ひたすらに生きている。半数は行方知れずだが、アスカケから戻った男からの話で、消息のわかるものも居た。村に戻った男はほとんどが村の外から嫁を連れて帰ってくる。
そう、アスカケの道は、外の世界との交流の乏しい高千穂の山間の村にとって、血が濃くならないための自衛の手段でもあった。また、外界の情報を得て、時代を進める力にもなっているのであった。そして、この時代、九重の国の村々にはみな同じような掟があった。
「父(とと)様の、アスカケはどんなだったの?」
カケルは、自分で獲ってきたヤマメの串焼きを手にしながら訊いた。隣にいたイツキも興味深げな顔でナギを見た。ナギは、もう一口、濁酒を飲むと、篝火をぼんやり見つめながら話し始めた。
「俺のアスカケは、御山を越え、九重の山を目指した道だった。御山を越えると、もっと大きな山が連なっていた。見えるものはすべて深い森。そこを何日も何日も歩いた。いよいよ疲れ果て、もう歩けないと思った先に、ウスキという村があった。」
「そこはどんなところだったの?」
カケルは、食べるのを止め、じっと父ナギの顔を見ている。イツキもカケルの横で同じようにナギの顔を見ていた。
「そこは・・・ナレとよく似た村だが・・ここよりも小さく、暮らしは厳しい。俺が辿り付いた時は冬。ここより寒さが厳しくて、凍えるようだった。だが、皆、優しかった。・・おお、そうだ、そうだ。その村には、深い深い底なしの淵があった。その淵には、大きな主がいた。村のものは、毎朝、淵でお祈りをし、主を宥めてから、魚を獲らせてもらっていたんだ。」
「とと様も獲った?」
「いや、淵に入れるのは選ばれたものだけだった。俺は、その村の長老に世話になった。村の中でいろんな仕事をした。そして、縄を編む事を教えてもらった。・・それが俺のアスカケだと決めたんだ。」
「縄を編む事がとと様のアスカケ?」
「ああ・・ナレの村も谷が深い。お前たちが獲物を取りにいくとしても、深い谷を降り、また登り、時には谷底に落ちる事もある。・・ウスキの村も同じだった。だから、強い強い縄を作り、谷に縄橋を掛ければ皆安心して獲物を獲りにいけるだろう。」
「じゃあ、西の谷の橋もとと様が掛けたの?」
「ああ、そうだ。あそこだけじゃない。御山へ向かう道にもいくつか作った。もっともっと作って村の人が楽に行けるようにしたいんだ。」
「ふーん。」
カケルとイツキは、感心したようにナギの顔を見ていた。
「それとなあ・・かか様に出会ったのも、そのウスキの村だったんだ。」
「え?かか様は、ウスキの村にいたの?」
カケルは初めて聞いた話に驚き、脇に座っていた、母ナミの顔を見た。ナミはにっこりと微笑んでからゆっくりと口を開いた。
「ええ、そうよ。ナギ様は、とても疲れていてね、しばらく動けなくなっていて、私が介抱したのよ。・・元気になるまでの間、毎日のように、ナレの村の話を聞いていたわ。」
「それで?」
「ナギ様は元気になって、ウスキの村で一生懸命仕事をしたわ。壊れた家を直したり、堀を大きくしたり、田んぼも作ってくれた。村の人は皆、ナギ様を信頼した。私のとと様もすっかり気に入って、二人が一緒になる事を許してくださったのよ。ナギ様が縄編みを覚えた頃、二人で一緒にナレの村に戻ってきたのよ。」
「へえ・・そうだったの。ウスキの村かあ・・僕もいつか行ってみたいなあ。」
「そうね、じじ様やばば様に会えると良いわね。」
夜の闇空に、篝火が赤々と燃え、夜は更けていった。
旅立ちの儀式と祝いの宴も終わり、それぞれ皆家に戻って行った。
カケルは、寝床に入ってからも、父や母に聞いた話を思い出し、胸の中が妙に高鳴るのを抑え切れなくてなかなか寝付けなかった。頭の中に、まだ見ぬ高千穂の峰からの風景や、その先に続く九重の山々、そして、その中にひっそりと存在するウスキの村。紺碧に輝く底なしの淵とそこに住む大きな主。いつしか、カケルは夢の中で、その主にまたがり、淵の中を泳ぎまわっていたのだった。

タグ:ナギ アスカケ 高千穂峡
-ナレの村-5.ケスキの旅立ち [アスカケ第1部 高千穂峰]
5. ケスキの旅立ち
翌朝、日の出とともに、皆起きだしてきて、ケスキの旅立ちを見送った。ケスキは、真新しい服と毛皮を身にまとい、片手には、銛を持ち、腰には剣を挿し、背中には、わずかな食糧を布に包んで背負っていた。ケスキの父「シシト」と母「モヨ」がじっと見守っていた。ケスキは、村の出口の門の前に立ち、村の皆のほうを見渡してから、大きな声でこう言った。
「俺は、必ず帰ってくる。自分のアスカケを見つけ、必ず戻る。皆、元気でなあ。」
そして、くるっと向きを変え、走り去るように門を出た。カケルとイツキは、門にすがりついて、その様子を見ていた。
門の前から、南へ谷を降りていく細い道が一本続いている。ケスキは、下り道を飛び跳ねるように降りていく。徐々に、足音も遠ざかり、静かになっていった。
「ねえ、ケスキはどこに行ったの?」
イツキが、傍にいたカケルに訊いた。
「・・うん・・南に行くって言ってたよ。南には煙を吐く御山があるんだって。その先には、淵より大きな <うみ> というのがあって、そこからまだ先に行けるんだって。」
「その先には何があるの?」
「そこから舟に乗って、どんどん行くと、海の中に <しま> というのがあるんだって・・」
「そこに何があるの?」
「さあ・・でも、ケスキは、そこに岩を割る人たちがいるって言ってた。自分も大きな岩を割れるようになるんだって・・そしたら、戻ってくるんだって。」
「どうして?」
「・・・ほら、東の尾根に大きな岩があるだろう。あれを割るんだって。そしたら、東の尾根にある畑にも行き易くなるだろ。あそこは、大きな畑が作れるから、もっとみんなの食べ物を作れるようになる。そのために岩を割る力を身に付けたいんだって。」
「ふーん。」
ナレの村は、東西に伸びる高千穂の峰の尾根に囲まれた小高い丘の中にある。30ほどの家族が暮らすには充分なのだが、畑地をもっと増やしたいと長年村の人は努力してきた。西の尾根はなだらかだがその先には深い谷がある。
東の尾根の先には、慣れの村よりも広い平地があるのだが、そこへの道は、尾根にのぞく大岩を登って越えるか、その下に作った狭い山道を通るほかなく、よほど足腰の丈夫な人間しか行く事ができなかったのだ。これまでにもそこを越えようとして何人かの村人が命を落としていた。その岩を割る事ができ、畑を広げる事ができるなら、村にとって大きな財産になる。
カケルとイツキの会話を聞いていたケスキの父「シシト」が呟くように言った。
「無事に戻って来れればいいが・・・」
ケスキの父シシトも、アスカケの道でケスキと同じように石を割る力を得ようとした。ケスキはその話を幼い頃から聞いていて、自分のアスカケでも、父と同じように石を割る力を得ようと考えたのだった。シシトも同じように南を目指して旅立った。しかし、煙を吹く御山にたどり着いた後、舟で更にその先へ進もうとしたが、海が荒れてその先へ進めなかったのだった。結局、シシトは、煙を吹く御山の近くの村で、畑を作る技を身につけ、ケスキの母となるモヨとともに村に戻ったのだった。
「ねえ、シシト様。海とはどんなものなんですか?」
カケルが訊いた。シシトは腰を落として、カケルと視線を合わせてから、
「カケルは海が見たいか?」
「うん、みてみたい。」
「そこはな・・淵よりも川よりもずっとずっと広い。舟で海に出ると、見えるものはもう海だけだ。青い空と青い海。風が吹くと、海は暴れる。舟が上に下に右に左に揺れて、自分を見失う。夜になると何も見えなくなって、自分さえ闇に飲み込まれてしまうのではないかと怖くなる。・・・とにかく大きくて深くて、飲み込まれれば命はない。怖い怖いものだよ。」
カケルは、シシトの話にぶるっと身を震わせた。この村には怖いものなどないが、シシトの話に聞いた海はとてつもなく恐ろしいものに思えたのだった。その様子に、シシトは少しにやりと笑ってから、
「そんなに恐れる事はない。丈夫な体があれば、海に飲み込まれても大丈夫さ。俺だって一度海に飲み込まれたが、こうやって生きている。・・カケル、海が見たいならもっともっと体を鍛えるんだ。そうすれば大丈夫さ。」
そう言って、カケルを抱えあげると、隣にいたイツキも片方の肩に乗せて、村の中に戻って行った。

翌朝、日の出とともに、皆起きだしてきて、ケスキの旅立ちを見送った。ケスキは、真新しい服と毛皮を身にまとい、片手には、銛を持ち、腰には剣を挿し、背中には、わずかな食糧を布に包んで背負っていた。ケスキの父「シシト」と母「モヨ」がじっと見守っていた。ケスキは、村の出口の門の前に立ち、村の皆のほうを見渡してから、大きな声でこう言った。
「俺は、必ず帰ってくる。自分のアスカケを見つけ、必ず戻る。皆、元気でなあ。」
そして、くるっと向きを変え、走り去るように門を出た。カケルとイツキは、門にすがりついて、その様子を見ていた。
門の前から、南へ谷を降りていく細い道が一本続いている。ケスキは、下り道を飛び跳ねるように降りていく。徐々に、足音も遠ざかり、静かになっていった。
「ねえ、ケスキはどこに行ったの?」
イツキが、傍にいたカケルに訊いた。
「・・うん・・南に行くって言ってたよ。南には煙を吐く御山があるんだって。その先には、淵より大きな <うみ> というのがあって、そこからまだ先に行けるんだって。」
「その先には何があるの?」
「そこから舟に乗って、どんどん行くと、海の中に <しま> というのがあるんだって・・」
「そこに何があるの?」
「さあ・・でも、ケスキは、そこに岩を割る人たちがいるって言ってた。自分も大きな岩を割れるようになるんだって・・そしたら、戻ってくるんだって。」
「どうして?」
「・・・ほら、東の尾根に大きな岩があるだろう。あれを割るんだって。そしたら、東の尾根にある畑にも行き易くなるだろ。あそこは、大きな畑が作れるから、もっとみんなの食べ物を作れるようになる。そのために岩を割る力を身に付けたいんだって。」
「ふーん。」
ナレの村は、東西に伸びる高千穂の峰の尾根に囲まれた小高い丘の中にある。30ほどの家族が暮らすには充分なのだが、畑地をもっと増やしたいと長年村の人は努力してきた。西の尾根はなだらかだがその先には深い谷がある。
東の尾根の先には、慣れの村よりも広い平地があるのだが、そこへの道は、尾根にのぞく大岩を登って越えるか、その下に作った狭い山道を通るほかなく、よほど足腰の丈夫な人間しか行く事ができなかったのだ。これまでにもそこを越えようとして何人かの村人が命を落としていた。その岩を割る事ができ、畑を広げる事ができるなら、村にとって大きな財産になる。
カケルとイツキの会話を聞いていたケスキの父「シシト」が呟くように言った。
「無事に戻って来れればいいが・・・」
ケスキの父シシトも、アスカケの道でケスキと同じように石を割る力を得ようとした。ケスキはその話を幼い頃から聞いていて、自分のアスカケでも、父と同じように石を割る力を得ようと考えたのだった。シシトも同じように南を目指して旅立った。しかし、煙を吹く御山にたどり着いた後、舟で更にその先へ進もうとしたが、海が荒れてその先へ進めなかったのだった。結局、シシトは、煙を吹く御山の近くの村で、畑を作る技を身につけ、ケスキの母となるモヨとともに村に戻ったのだった。
「ねえ、シシト様。海とはどんなものなんですか?」
カケルが訊いた。シシトは腰を落として、カケルと視線を合わせてから、
「カケルは海が見たいか?」
「うん、みてみたい。」
「そこはな・・淵よりも川よりもずっとずっと広い。舟で海に出ると、見えるものはもう海だけだ。青い空と青い海。風が吹くと、海は暴れる。舟が上に下に右に左に揺れて、自分を見失う。夜になると何も見えなくなって、自分さえ闇に飲み込まれてしまうのではないかと怖くなる。・・・とにかく大きくて深くて、飲み込まれれば命はない。怖い怖いものだよ。」
カケルは、シシトの話にぶるっと身を震わせた。この村には怖いものなどないが、シシトの話に聞いた海はとてつもなく恐ろしいものに思えたのだった。その様子に、シシトは少しにやりと笑ってから、
「そんなに恐れる事はない。丈夫な体があれば、海に飲み込まれても大丈夫さ。俺だって一度海に飲み込まれたが、こうやって生きている。・・カケル、海が見たいならもっともっと体を鍛えるんだ。そうすれば大丈夫さ。」
そう言って、カケルを抱えあげると、隣にいたイツキも片方の肩に乗せて、村の中に戻って行った。

-ナレの村-6.鷹 ハヤテ [アスカケ第1部 高千穂峰]
6.鷹 ハヤテ
森で見つけた怪我をした鷹は、父ナギが、折れた翼に添え木をして手当てをした。鷹は、父ナギの手にいるときは、まったく暴れることなく、おとなしかった。
カケルは、母ナミから竹を使って鳥篭をこしらえる事を教わり、一日かけて、丁寧に作った。
「鷹は肉と魚が餌になる。しばらく、カケルは鷹の餌集めをしなさい。」
父ナギに言われ、カケルはしばらくの間、餌取りに励んだ。
魚は、西の谷の淵に行けば、いくらでも獲れた。鷹に魚をやると、器用に足で掴み、啄ばんだ。
だが、肉となる動物には困った。村でも、男たち総がかりで、イノシシやウサギ等の猟に行くのだが、獲れないことも多く、鷹の餌の為に肉を分けてもらうなどできなかった。
しばらくの間は、そのまま、魚の餌を与えていたが、次第に食べなくなり、元気がなくなってきたのがわかった。
「父様、ハヤテに肉の餌をやらないとだめかな。」
竹籠の中の止まり木にとまっている鷹を見つめながら、カケルがぼんやりとした表情で呟く。
「ハヤテ?・・こいつの名か。・・・なんだ、獲物が取れないのか?」
「・・・う・・ん。・・・」
「お前、サチ(弓矢)は使ったことはあるか?」
「・・ううん、ない。・・・。」
「鷹の餌になるものは、畑を荒らす野ねずみやウサギだ。サチ(弓矢)があれば、捕まえる事もできよう。」
「・・でも・・サチ(弓矢)は持ってない。父様のは使えないんでしょ。」
「ああ、あれは、命(みこと)の分身だからな。そうか、それなら、サチ(弓矢)をこしらえるか。そろそろ、自分のものを持つころだろう。さあ。」
ナギはそういうと、カケルと一緒に、家の前に出た。二人は、弓を作るために、タカヒコの家に行った。タカヒコは、3人息子の父で、村一番の弓の名手だった。
「タカヒコ、サチを作ってもらえまいか・・」
家の前で、矢の手入れをしていたタカヒコは快く引き受けてくれた。タカヒコは、カケルの肩を掴んでから、
「うむ。・・お前、いくつになった?」
「八つになりました。」
「そうか・・その割りに力があるようだ。お前には強い弓を作ってやる。強く、遠く、大きな獲物も貫ける強い弓だ。最初は、引けないかも知れぬが、そのうちに引けるようになる。まあ、任せとけ。・・・そこにある櫨の木を取ってくれ。」
タカヒコはそういうと、家の前に立てかけてある弓にする木の束を示した。
「いいか・・できるだけ太くてまっすぐしたものを選べ。」
カケルはその中から白くまっすぐ伸びているものを選んで渡した。
「おお、良いのを選んだな。そうだ、これなら丈夫だ。いいか、お前が使いたいものを見極めるんだぞ。」
そう言って、タカヒコは、カケルに削り方を教え始めた。その様子を見ながら、ナギが、
「よし。俺が弦を用意しよう。タカヒコ、命(みこと)が使う太い弦で良いな。」
「ああ。カケルなら必ず使いこなせるだろう。」
何とか形になったところで、弦を張った。
「よし、次は矢だ。三本作るんだ。鏃(やじり)は、黒石で良いだろう。ひとつ削ってあるから、よくよく見て、あと二つ自分で作るんだ。・・それと、矢羽には鷹の羽が良い。お前が飼っている鷹からもらおう。尾羽を1本抜いて来い。」
そう言われて、カケルは竹籠に走った。竹籠の中に手を入れ、カケルは尾羽を抜こうとした。鷹はじっとカケルを見ていた。
「ハヤテ、すまない。羽を分けてくれ。」
カケルがそう言うと、承知したかのようにハヤテは尾をカケルに向けた。
尾羽を持っていくと、タカヒコは見事に半分に割り、矢の尻に埋め込んでいった。
「よし、いいサチができた。これなら永く使える。お前が大人になっても充分だ。」
タカヒコはそういうと、カケルに手渡してくれた。初めての自分のサチ(弓矢)を手にして、カケルは手が震えた。そして、体の中に何か熱くなるものを感じ、鼓動が高鳴った。
「どうした?さあ、引いてみろ。」
タカヒコとナギが微笑んでみている。カケルは大人たちが弓を引く姿を思い出しながら、左手に弓を持ち、矢を指に挟んで弦に合わせた。そして、力いっぱい引いた。ぐいっと弓は撓る。そして、矢の先を、柵の方へ向けて放った。びゅうと音を立てて、勢いよく矢が飛んでいく。すると、柵に吊るしてあった干し肉を矢は貫通した。

森で見つけた怪我をした鷹は、父ナギが、折れた翼に添え木をして手当てをした。鷹は、父ナギの手にいるときは、まったく暴れることなく、おとなしかった。
カケルは、母ナミから竹を使って鳥篭をこしらえる事を教わり、一日かけて、丁寧に作った。
「鷹は肉と魚が餌になる。しばらく、カケルは鷹の餌集めをしなさい。」
父ナギに言われ、カケルはしばらくの間、餌取りに励んだ。
魚は、西の谷の淵に行けば、いくらでも獲れた。鷹に魚をやると、器用に足で掴み、啄ばんだ。
だが、肉となる動物には困った。村でも、男たち総がかりで、イノシシやウサギ等の猟に行くのだが、獲れないことも多く、鷹の餌の為に肉を分けてもらうなどできなかった。
しばらくの間は、そのまま、魚の餌を与えていたが、次第に食べなくなり、元気がなくなってきたのがわかった。
「父様、ハヤテに肉の餌をやらないとだめかな。」
竹籠の中の止まり木にとまっている鷹を見つめながら、カケルがぼんやりとした表情で呟く。
「ハヤテ?・・こいつの名か。・・・なんだ、獲物が取れないのか?」
「・・・う・・ん。・・・」
「お前、サチ(弓矢)は使ったことはあるか?」
「・・ううん、ない。・・・。」
「鷹の餌になるものは、畑を荒らす野ねずみやウサギだ。サチ(弓矢)があれば、捕まえる事もできよう。」
「・・でも・・サチ(弓矢)は持ってない。父様のは使えないんでしょ。」
「ああ、あれは、命(みこと)の分身だからな。そうか、それなら、サチ(弓矢)をこしらえるか。そろそろ、自分のものを持つころだろう。さあ。」
ナギはそういうと、カケルと一緒に、家の前に出た。二人は、弓を作るために、タカヒコの家に行った。タカヒコは、3人息子の父で、村一番の弓の名手だった。
「タカヒコ、サチを作ってもらえまいか・・」
家の前で、矢の手入れをしていたタカヒコは快く引き受けてくれた。タカヒコは、カケルの肩を掴んでから、
「うむ。・・お前、いくつになった?」
「八つになりました。」
「そうか・・その割りに力があるようだ。お前には強い弓を作ってやる。強く、遠く、大きな獲物も貫ける強い弓だ。最初は、引けないかも知れぬが、そのうちに引けるようになる。まあ、任せとけ。・・・そこにある櫨の木を取ってくれ。」
タカヒコはそういうと、家の前に立てかけてある弓にする木の束を示した。
「いいか・・できるだけ太くてまっすぐしたものを選べ。」
カケルはその中から白くまっすぐ伸びているものを選んで渡した。
「おお、良いのを選んだな。そうだ、これなら丈夫だ。いいか、お前が使いたいものを見極めるんだぞ。」
そう言って、タカヒコは、カケルに削り方を教え始めた。その様子を見ながら、ナギが、
「よし。俺が弦を用意しよう。タカヒコ、命(みこと)が使う太い弦で良いな。」
「ああ。カケルなら必ず使いこなせるだろう。」
何とか形になったところで、弦を張った。
「よし、次は矢だ。三本作るんだ。鏃(やじり)は、黒石で良いだろう。ひとつ削ってあるから、よくよく見て、あと二つ自分で作るんだ。・・それと、矢羽には鷹の羽が良い。お前が飼っている鷹からもらおう。尾羽を1本抜いて来い。」
そう言われて、カケルは竹籠に走った。竹籠の中に手を入れ、カケルは尾羽を抜こうとした。鷹はじっとカケルを見ていた。
「ハヤテ、すまない。羽を分けてくれ。」
カケルがそう言うと、承知したかのようにハヤテは尾をカケルに向けた。
尾羽を持っていくと、タカヒコは見事に半分に割り、矢の尻に埋め込んでいった。
「よし、いいサチができた。これなら永く使える。お前が大人になっても充分だ。」
タカヒコはそういうと、カケルに手渡してくれた。初めての自分のサチ(弓矢)を手にして、カケルは手が震えた。そして、体の中に何か熱くなるものを感じ、鼓動が高鳴った。
「どうした?さあ、引いてみろ。」
タカヒコとナギが微笑んでみている。カケルは大人たちが弓を引く姿を思い出しながら、左手に弓を持ち、矢を指に挟んで弦に合わせた。そして、力いっぱい引いた。ぐいっと弓は撓る。そして、矢の先を、柵の方へ向けて放った。びゅうと音を立てて、勢いよく矢が飛んでいく。すると、柵に吊るしてあった干し肉を矢は貫通した。

タグ:鷹 ハヤテ 弓 サチ
-ナレの村-7.サチ(箭霊)封印 [アスカケ第1部 高千穂峰]
7.サチ(箭霊)封印
タカヒコもナギも驚いた。初めて弓を引いたはずなのに、カケルの放った矢は、驚くほどの威力で大人でもなかなか射抜く事が難しい干し肉を見事に貫通した。
「もう一度引いてみろ。」
タカヒコは驚きを隠せずに言った。カケルは同じように構え、引いた。また同じように、干し肉に刺さった。
「よし、もう一度、干し肉を狙って見ろ。」
今度はナギが言った。同じように構え、更に力をこめて弓を引き放った。三本目の矢は、大人でもなかなか出せない笛のような高い音を立てて飛んで、干し肉の、それもさっきの矢を貫くように刺さった。
タカヒコとナギは顔を見合わせた。信じられない気持ちだった。まだ八つの子どもの放つ矢ではなかったのだ。そこに、高楼の上から様子を見ていた巫女セイが現れた。
「セイ様・・カケルのサチ(箭霊・弓矢)の腕前が・・」
ナギがそう言い掛けたのをセイは制止するように手をかざした。そして、
「この子のサチ(弓矢)は、封印すべし。」
厳しい声でそう告げた。
「ですが・・・セイ様、これだけの腕前なら、すぐにでも猟に連れて行けます。村の者も、ひもじい思いもせずに済むやも知れませぬ。」
ナギは、そう言ったが、巫女セイは首を横に振った。
「どうやら、カケルは幼いながら、恐ろしい力を持っておるようじゃ。使い道を誤るといのちを落とす事になる。いや、この村に災いとなるであろう。・・良いか、この子がアスカケに出る日まで、サチ(弓矢)は封印じゃ。・・カケル、良いな。このサチ(弓矢)は私が預かる。十五になる年にお前がアスカケに出るのなら、その時に返そう。」
そう言うと、カケルの手からサチ(弓矢)を取り上げた。
「セイ様!・・ハヤテの餌を獲るために、サチ(弓矢)が欲しいんです。」
カケルはそう言って、巫女セイに取り縋った。
「あの鷹は、すでに飛べるようになっておる。竹籠から出してやれば、自分で餌を獲る。さあ、竹籠から出したおやり。」
カケルは、巫女セイに言われるまま、竹籠を開けた。
羽の添え木をそっと取ってやると、ハヤテは、しばらくは、止まり木にじっとしていたが、辺りをじっと見渡し、一度身震いをしたと思うと、羽を広げ一瞬のうちに飛び上がっていった。村の上を3回ほど回った後、高千穂の峰のほうへ飛び去っていった。
カケルのサチ(箭霊)の腕前は、すぐに村人の知るところとなった。初めて引いた矢が肉を貫通するなど、並みの男でもできる事ではない。巫女セイが封印した事で、それは、さらに、村の伝説というべきものに変わってしまった。
次の日、カケルは、いつものように西の谷に行き、銛を使って魚取りをしていた。
上空にハヤテが旋回している。カケルが水から顔を出すと、ハヤテは上空から急速度で降下し、水面すれすれに飛んできた。カケルに挨拶でもするかのような飛び方だった。二度ほど繰り返したあと、今度は水面を泳いでいた魚を足で掴んで飛び上がり、岸に魚を落としたのだった。
岸にいたイツキが言った。
「ハヤテがお礼に魚をくれたのかなあ。」
「そんなことはないだろ。上手く掴めなくて落としちゃったんだろ?」
しかし、同じようにもう一度ハヤテは魚を掴むと二人のいる岸辺に落としたのだった。
「ほら、やっぱり、そうよ。・・・カケルが手当てをしてくれた御礼をしてるのよ。」
「そうかあ・・ありがとう、ハヤテ。」
カケルは、上空を旋回しているハヤテに手を振った。ハヤテは甲高い鳴き声で答え、飛び去っていった。
「でも、せっかく、サチが上手いのに使えないなんてね・・」
イツキがつい口走ってしまった。カケルは、
「いいんだ。僕もちょっと怖かったんだ。サチを持った時、ここがドキドキして苦しかったんだ。なんだか変な気持ちだった。それに、やっぱり、こうやって魚を獲るほうが楽しいし・・」
「そうなの?ならいいわ。でも、私も見たかったなあ、カケルのサチを射るところ。」
イツキはそう言うと、山桃の木にするすると登っていった。

タカヒコもナギも驚いた。初めて弓を引いたはずなのに、カケルの放った矢は、驚くほどの威力で大人でもなかなか射抜く事が難しい干し肉を見事に貫通した。
「もう一度引いてみろ。」
タカヒコは驚きを隠せずに言った。カケルは同じように構え、引いた。また同じように、干し肉に刺さった。
「よし、もう一度、干し肉を狙って見ろ。」
今度はナギが言った。同じように構え、更に力をこめて弓を引き放った。三本目の矢は、大人でもなかなか出せない笛のような高い音を立てて飛んで、干し肉の、それもさっきの矢を貫くように刺さった。
タカヒコとナギは顔を見合わせた。信じられない気持ちだった。まだ八つの子どもの放つ矢ではなかったのだ。そこに、高楼の上から様子を見ていた巫女セイが現れた。
「セイ様・・カケルのサチ(箭霊・弓矢)の腕前が・・」
ナギがそう言い掛けたのをセイは制止するように手をかざした。そして、
「この子のサチ(弓矢)は、封印すべし。」
厳しい声でそう告げた。
「ですが・・・セイ様、これだけの腕前なら、すぐにでも猟に連れて行けます。村の者も、ひもじい思いもせずに済むやも知れませぬ。」
ナギは、そう言ったが、巫女セイは首を横に振った。
「どうやら、カケルは幼いながら、恐ろしい力を持っておるようじゃ。使い道を誤るといのちを落とす事になる。いや、この村に災いとなるであろう。・・良いか、この子がアスカケに出る日まで、サチ(弓矢)は封印じゃ。・・カケル、良いな。このサチ(弓矢)は私が預かる。十五になる年にお前がアスカケに出るのなら、その時に返そう。」
そう言うと、カケルの手からサチ(弓矢)を取り上げた。
「セイ様!・・ハヤテの餌を獲るために、サチ(弓矢)が欲しいんです。」
カケルはそう言って、巫女セイに取り縋った。
「あの鷹は、すでに飛べるようになっておる。竹籠から出してやれば、自分で餌を獲る。さあ、竹籠から出したおやり。」
カケルは、巫女セイに言われるまま、竹籠を開けた。
羽の添え木をそっと取ってやると、ハヤテは、しばらくは、止まり木にじっとしていたが、辺りをじっと見渡し、一度身震いをしたと思うと、羽を広げ一瞬のうちに飛び上がっていった。村の上を3回ほど回った後、高千穂の峰のほうへ飛び去っていった。
カケルのサチ(箭霊)の腕前は、すぐに村人の知るところとなった。初めて引いた矢が肉を貫通するなど、並みの男でもできる事ではない。巫女セイが封印した事で、それは、さらに、村の伝説というべきものに変わってしまった。
次の日、カケルは、いつものように西の谷に行き、銛を使って魚取りをしていた。
上空にハヤテが旋回している。カケルが水から顔を出すと、ハヤテは上空から急速度で降下し、水面すれすれに飛んできた。カケルに挨拶でもするかのような飛び方だった。二度ほど繰り返したあと、今度は水面を泳いでいた魚を足で掴んで飛び上がり、岸に魚を落としたのだった。
岸にいたイツキが言った。
「ハヤテがお礼に魚をくれたのかなあ。」
「そんなことはないだろ。上手く掴めなくて落としちゃったんだろ?」
しかし、同じようにもう一度ハヤテは魚を掴むと二人のいる岸辺に落としたのだった。
「ほら、やっぱり、そうよ。・・・カケルが手当てをしてくれた御礼をしてるのよ。」
「そうかあ・・ありがとう、ハヤテ。」
カケルは、上空を旋回しているハヤテに手を振った。ハヤテは甲高い鳴き声で答え、飛び去っていった。
「でも、せっかく、サチが上手いのに使えないなんてね・・」
イツキがつい口走ってしまった。カケルは、
「いいんだ。僕もちょっと怖かったんだ。サチを持った時、ここがドキドキして苦しかったんだ。なんだか変な気持ちだった。それに、やっぱり、こうやって魚を獲るほうが楽しいし・・」
「そうなの?ならいいわ。でも、私も見たかったなあ、カケルのサチを射るところ。」
イツキはそう言うと、山桃の木にするすると登っていった。

タグ:箭霊 サチ 弓 封印
-ナレの村-8.水足(みたり)の御川 [アスカケ第1部 高千穂峰]
8.水足(みたり)の御川
ケスキがアスカケに旅立ってから、夏が過ぎ、秋、冬、そしてまた春になっていた。
カケルもイツキも、少し大きくなった。以前のように、畑の手伝いや川で魚とり、木の実集め等をしながら過ごしていたが、徐々に大人の仕事の手伝いが増えるようになっていた。
カケルは、時々、男たちに混じって、山の猟にも付いていくようになった。
イツキは、冬の間に、機織りを覚え、天気の悪い時などはずっと篭って過ごすようにもなっていた。
ナレの村の西側には、谷に向かって流れ落ちるように、幅2間ほどの水路がある。もともと、小さな川だったところを、先人たちが川幅を広げ、田畑のあるところまで水を引くために水路にしたのだった。
この川は不思議な事に、1年のうち、半年近くは枯れている。春、辺りの草が花を咲かせ、緑が濃くなる頃に突然水を噴出し、秋、収穫を終え冬支度に入る頃にはまた枯れてしまうのだった。だから、村の者は、「水足り(みたり)の御川(おんかわ)」と呼んだ。この川に水が噴き出す頃、農作物の植え付けを始め、枯れる頃には、厳しい冬に向け蓄えをしていく。暦のような川であった。
今日は、朝から村を上げて水路の掃除をすることになった。昨夜、巫女セイが、水神様のお告げを聞いたと言い、村の命(みこと)達が集まって相談し、水路の掃除と祈りをする事に決まったのだった。
子どもたちも、大人に混じって水路に入り、川底のごろ石をどけたり、伸びた草を刈ったり、土手を修復したりしながら、汗を流した。水路の両脇には、ノカイドウや山つつじの花が咲き始めていた。
しばらくは、大人に混じって手伝いをしていた子どもたちも、エン・セン・ケンの3兄弟が、木登りを始めたのをきっかけに、水路の掃除をやめてしまい、土手に上がって遊んでいた。
エン・セン・ケンの3兄弟はみな年子で、一番上のエンはカケルと同い年だった。長男のエンが、野いちごを見つけた。兄弟は競うように野いちごを摘み食べた。知らぬうちに、森の中にはいっていた。
ナレの村の周りの森は、子どもたちが遊ぶのを禁じていた。太古、高千穂峰が噴火した後、溶岩の流れた跡が大きな空洞となっていて、森の中にはそこかしこに深い穴が口を開けていたからだった。そこに落ちれば、子どもでは、這い上がる事は不可能だった。3人はその掟をすっかり忘れ、ずんずんと森の中に入っている。次男のセンが、ふと気づいて兄に、
「ねえ、兄ちゃん、もう戻ろう。森は入っちゃならないって父様も言ってたし・・。」
その言葉に、エンは、
「大丈夫さ。まだ、みたりの御川が見える。すぐそこにあるじゃないか。」
そう言って、振り返って指差した。確かに、木々の間から、みたりの御川がわずかに見えていた。しかし、
「おい!ケンはどこだ?」
辺りを見回したが、末っ子のケンの姿が見えない。
「え?さっきまでそこでイチゴを食べてたけど・・・」
二人は、ケンの名を呼んだ。どこか遠くからかすかに返事の声が聞こえる。二人は、その声のするほうへ急いだ。しかし、辺りには姿が見えない。じっと耳を澄ますと、その声は地中から聞こえていた。草の茂る中を手探りで声を頼りに探した。すると、体がすっぽりと入るほどの大穴の底の方から声がする。ケンは、穴の中へ落ちてしまったのだった。エンとセンは、穴の中に顔を突っ込んで様子を見ようとした。だが、穴の中は真っ暗で、ひんやりとした風が抜けてくるだけだった。
「ケン、すぐ、父様を呼びに行け。判るだろ、ほら、そこに御川がある。あそこに出て、下っていけば父様がいるはずだ。」
そう言われて、ケンはすぐに走り出した。
土手にはイツキとカケルがいた。川の土手に生えていた野いちごを摘んでいた。血相を変えて飛び出してきたケンを見て、イツキが訊いた。
「どうしたの?」
「センが・・森の中で・・穴に落ちた・・父様を呼びにいく。父様は?」
「皆、祠に向かったわ。もうじきお祈りを始めるからって・・。」
祠は、みたりの御川の水が噴出す水穴にあった。掃除を終えて、村人たちは、奉げ物を持って祠に向かったのだった。
「私が行ってくる。場所を知ってるのはケンだけだから、ここで待ってて。」
イツキは、水の流れていない御川を上流に走っていった。
カケルは、じっと森の中を見ていた。カケルは、人並みはずれた聴力と視力を持っていた。岸に生えている欅の幹に登り、辺りを見回し、すぐに、穴の場所を見つけると、枝から大きく飛び上がり、木々を縫うようにして、森の中へ入っていった。

ケスキがアスカケに旅立ってから、夏が過ぎ、秋、冬、そしてまた春になっていた。
カケルもイツキも、少し大きくなった。以前のように、畑の手伝いや川で魚とり、木の実集め等をしながら過ごしていたが、徐々に大人の仕事の手伝いが増えるようになっていた。
カケルは、時々、男たちに混じって、山の猟にも付いていくようになった。
イツキは、冬の間に、機織りを覚え、天気の悪い時などはずっと篭って過ごすようにもなっていた。
ナレの村の西側には、谷に向かって流れ落ちるように、幅2間ほどの水路がある。もともと、小さな川だったところを、先人たちが川幅を広げ、田畑のあるところまで水を引くために水路にしたのだった。
この川は不思議な事に、1年のうち、半年近くは枯れている。春、辺りの草が花を咲かせ、緑が濃くなる頃に突然水を噴出し、秋、収穫を終え冬支度に入る頃にはまた枯れてしまうのだった。だから、村の者は、「水足り(みたり)の御川(おんかわ)」と呼んだ。この川に水が噴き出す頃、農作物の植え付けを始め、枯れる頃には、厳しい冬に向け蓄えをしていく。暦のような川であった。
今日は、朝から村を上げて水路の掃除をすることになった。昨夜、巫女セイが、水神様のお告げを聞いたと言い、村の命(みこと)達が集まって相談し、水路の掃除と祈りをする事に決まったのだった。
子どもたちも、大人に混じって水路に入り、川底のごろ石をどけたり、伸びた草を刈ったり、土手を修復したりしながら、汗を流した。水路の両脇には、ノカイドウや山つつじの花が咲き始めていた。
しばらくは、大人に混じって手伝いをしていた子どもたちも、エン・セン・ケンの3兄弟が、木登りを始めたのをきっかけに、水路の掃除をやめてしまい、土手に上がって遊んでいた。
エン・セン・ケンの3兄弟はみな年子で、一番上のエンはカケルと同い年だった。長男のエンが、野いちごを見つけた。兄弟は競うように野いちごを摘み食べた。知らぬうちに、森の中にはいっていた。
ナレの村の周りの森は、子どもたちが遊ぶのを禁じていた。太古、高千穂峰が噴火した後、溶岩の流れた跡が大きな空洞となっていて、森の中にはそこかしこに深い穴が口を開けていたからだった。そこに落ちれば、子どもでは、這い上がる事は不可能だった。3人はその掟をすっかり忘れ、ずんずんと森の中に入っている。次男のセンが、ふと気づいて兄に、
「ねえ、兄ちゃん、もう戻ろう。森は入っちゃならないって父様も言ってたし・・。」
その言葉に、エンは、
「大丈夫さ。まだ、みたりの御川が見える。すぐそこにあるじゃないか。」
そう言って、振り返って指差した。確かに、木々の間から、みたりの御川がわずかに見えていた。しかし、
「おい!ケンはどこだ?」
辺りを見回したが、末っ子のケンの姿が見えない。
「え?さっきまでそこでイチゴを食べてたけど・・・」
二人は、ケンの名を呼んだ。どこか遠くからかすかに返事の声が聞こえる。二人は、その声のするほうへ急いだ。しかし、辺りには姿が見えない。じっと耳を澄ますと、その声は地中から聞こえていた。草の茂る中を手探りで声を頼りに探した。すると、体がすっぽりと入るほどの大穴の底の方から声がする。ケンは、穴の中へ落ちてしまったのだった。エンとセンは、穴の中に顔を突っ込んで様子を見ようとした。だが、穴の中は真っ暗で、ひんやりとした風が抜けてくるだけだった。
「ケン、すぐ、父様を呼びに行け。判るだろ、ほら、そこに御川がある。あそこに出て、下っていけば父様がいるはずだ。」
そう言われて、ケンはすぐに走り出した。
土手にはイツキとカケルがいた。川の土手に生えていた野いちごを摘んでいた。血相を変えて飛び出してきたケンを見て、イツキが訊いた。
「どうしたの?」
「センが・・森の中で・・穴に落ちた・・父様を呼びにいく。父様は?」
「皆、祠に向かったわ。もうじきお祈りを始めるからって・・。」
祠は、みたりの御川の水が噴出す水穴にあった。掃除を終えて、村人たちは、奉げ物を持って祠に向かったのだった。
「私が行ってくる。場所を知ってるのはケンだけだから、ここで待ってて。」
イツキは、水の流れていない御川を上流に走っていった。
カケルは、じっと森の中を見ていた。カケルは、人並みはずれた聴力と視力を持っていた。岸に生えている欅の幹に登り、辺りを見回し、すぐに、穴の場所を見つけると、枝から大きく飛び上がり、木々を縫うようにして、森の中へ入っていった。

-ナレの村-9.地下の洞 [アスカケ第1部 高千穂峰]
9. 地下の洞
穴の脇では、エンが必死に声を掛けていた。
「今、父様を呼びに行ったから・・待ってるんだぞ!」
暗闇の中で、センは半べそをかいていた。その内、何か穴の中で音がし始めた。その音はゴーゴーと響いて聞こえる。
「兄ちゃん、なんか聞こえる。怖いよう・・・。」
そこにカケルがやってきた。
「エン!ケンは?」
「この中だよ。何か音がするって・・・どうしよう、何か魔物でもいるのかな?」
カケルは地面に耳をつけて音の正体を考えていた。まだ9歳の子どもにその正体がわかるはずもなかったが、じっと耳とつけて音の様子を探った。
「何か、近づいてきてるみたいだ。・・・」
「掟を破って・・森に入ったから・・森の神様が怒ってるのかなあ・・・」
穴の中から、ケンが、弱弱しい声で言った。
「兄ちゃん・・・冷たいよう・・・水が・・・冷たいよう・・・」
地中の空洞に、水が入って来たようだった。
「エン!僕の足を持ってて。頭を入れてみる。」
そう言われ、エンはカケルの足を持った。カケルは穴の中に体を入れて中を覗いてみた。最初は、真っ暗で何も見えなかったが、徐々に目が慣れると様子がわかってきた。ケンは、穴の底に立っていた。膝辺りまで水に浸かっている。手を伸ばしてみると、あとわずかで届きそうだった。その時だった。
「うわっ!」
エンが耐えかねてカケルの足を離してしまったのだった。カケルは頭から真っ逆さまに穴の中に落ちたのだった。カケルは起き上がり、ケンの手を取った。
「ここにいちゃ駄目だ。もうじき、水がたくさん来る。逃げよう。」
カケルはそういうと、耳を澄まして音のする方向を定めた。そして、それとは反対の方向にケンの手を取って、駆け出した。ケンは真っ暗闇で何も見えなかったが、カケルには穴の様子がちゃんと見えていた。
二人は必死で走った。途中、ケンは何度も転びそうになりながら、その度に、カケルに起こされた。しかし、足元の水嵩は増えるばかりだった。腰辺りから肩口くらいまで水はどんどん嵩を増した。もうほとんど泳ぐような格好になっていた。
イツキは祠に着き、ケンたちの父タカヒコに事情を説明した。それを聞いたカケルの父ナギも心配して、タカヒコとともに穴に向かった。穴に着くと、エンとセンが穴の脇にいた。父タカヒコの顔を見るなり、二人は大声で泣いた。
「カケルも・・・落ちた。・・水がたくさん来て流された・・・ごめんなさい・・ごめんなさい。」
泣きじゃくりながら、説明した。タカヒコは、二人を抱きしめた。そして穴を覗きこんだ。
「随分、水が入ってきているな。二人とも流されたか。」
カケルの父ナギは、じっと考えた。そして、皆にこう言った。
「よし、祠に戻るぞ。・・大丈夫だ。カケルが一緒なら、きっと大丈夫だ。」
地下の洞の中で、カケルとケンはもうほとんど肩口まで水に浸かり息をするのもやっとの状態だった。ケンは暗闇の中で何も見えず、カケルの腰紐を強く握っていた。二人の足元を何かがすりぬけて行った。カケルは水面に顔をつけてみた。少し前方に、金色に輝くような大きな鯉が泳いでいる。暗闇の中でもそれは輝いていた。そして、着いて来いというようにゆったりと泳いでいる。
「ケン、もう少しだ。すぐに出口だ。」
「そうかい?・・まさか、黄泉の入り口じゃないだろうねえ。」
「黄泉?」
「ああ、お婆様(おばば様)から聞いたんだ。土の底に、黄泉の入り口がある。そこに子どもが入っちゃならないって・・。」
「大丈夫だ。きっと水神様が守ってくれる。さあ行こう。」
そう言うやいなや、背中を押されるように流れが強くなった。いや、流れが強いのではなく、小魚の群れが背中を押しているのだ。
「あっ!」
「わあっ!」
二人は急に深みに落ちた。洞が急に狭まり。地中深くに落ち込んでいたのだった。もう、どちらが上か下かわからない状態で、水流に流された。だが、二人の周りには小魚たちがまとわりついて岩にぶつかるのを防いでくれていた。カケルは、水流の中で確かに魚たちが自分たちを取り囲み、守ってくれているのを見たのだった。一旦、落ち込んだあと、急に上昇し始めた。そして、明かりが近づいてきたような気がした。

穴の脇では、エンが必死に声を掛けていた。
「今、父様を呼びに行ったから・・待ってるんだぞ!」
暗闇の中で、センは半べそをかいていた。その内、何か穴の中で音がし始めた。その音はゴーゴーと響いて聞こえる。
「兄ちゃん、なんか聞こえる。怖いよう・・・。」
そこにカケルがやってきた。
「エン!ケンは?」
「この中だよ。何か音がするって・・・どうしよう、何か魔物でもいるのかな?」
カケルは地面に耳をつけて音の正体を考えていた。まだ9歳の子どもにその正体がわかるはずもなかったが、じっと耳とつけて音の様子を探った。
「何か、近づいてきてるみたいだ。・・・」
「掟を破って・・森に入ったから・・森の神様が怒ってるのかなあ・・・」
穴の中から、ケンが、弱弱しい声で言った。
「兄ちゃん・・・冷たいよう・・・水が・・・冷たいよう・・・」
地中の空洞に、水が入って来たようだった。
「エン!僕の足を持ってて。頭を入れてみる。」
そう言われ、エンはカケルの足を持った。カケルは穴の中に体を入れて中を覗いてみた。最初は、真っ暗で何も見えなかったが、徐々に目が慣れると様子がわかってきた。ケンは、穴の底に立っていた。膝辺りまで水に浸かっている。手を伸ばしてみると、あとわずかで届きそうだった。その時だった。
「うわっ!」
エンが耐えかねてカケルの足を離してしまったのだった。カケルは頭から真っ逆さまに穴の中に落ちたのだった。カケルは起き上がり、ケンの手を取った。
「ここにいちゃ駄目だ。もうじき、水がたくさん来る。逃げよう。」
カケルはそういうと、耳を澄まして音のする方向を定めた。そして、それとは反対の方向にケンの手を取って、駆け出した。ケンは真っ暗闇で何も見えなかったが、カケルには穴の様子がちゃんと見えていた。
二人は必死で走った。途中、ケンは何度も転びそうになりながら、その度に、カケルに起こされた。しかし、足元の水嵩は増えるばかりだった。腰辺りから肩口くらいまで水はどんどん嵩を増した。もうほとんど泳ぐような格好になっていた。
イツキは祠に着き、ケンたちの父タカヒコに事情を説明した。それを聞いたカケルの父ナギも心配して、タカヒコとともに穴に向かった。穴に着くと、エンとセンが穴の脇にいた。父タカヒコの顔を見るなり、二人は大声で泣いた。
「カケルも・・・落ちた。・・水がたくさん来て流された・・・ごめんなさい・・ごめんなさい。」
泣きじゃくりながら、説明した。タカヒコは、二人を抱きしめた。そして穴を覗きこんだ。
「随分、水が入ってきているな。二人とも流されたか。」
カケルの父ナギは、じっと考えた。そして、皆にこう言った。
「よし、祠に戻るぞ。・・大丈夫だ。カケルが一緒なら、きっと大丈夫だ。」
地下の洞の中で、カケルとケンはもうほとんど肩口まで水に浸かり息をするのもやっとの状態だった。ケンは暗闇の中で何も見えず、カケルの腰紐を強く握っていた。二人の足元を何かがすりぬけて行った。カケルは水面に顔をつけてみた。少し前方に、金色に輝くような大きな鯉が泳いでいる。暗闇の中でもそれは輝いていた。そして、着いて来いというようにゆったりと泳いでいる。
「ケン、もう少しだ。すぐに出口だ。」
「そうかい?・・まさか、黄泉の入り口じゃないだろうねえ。」
「黄泉?」
「ああ、お婆様(おばば様)から聞いたんだ。土の底に、黄泉の入り口がある。そこに子どもが入っちゃならないって・・。」
「大丈夫だ。きっと水神様が守ってくれる。さあ行こう。」
そう言うやいなや、背中を押されるように流れが強くなった。いや、流れが強いのではなく、小魚の群れが背中を押しているのだ。
「あっ!」
「わあっ!」
二人は急に深みに落ちた。洞が急に狭まり。地中深くに落ち込んでいたのだった。もう、どちらが上か下かわからない状態で、水流に流された。だが、二人の周りには小魚たちがまとわりついて岩にぶつかるのを防いでくれていた。カケルは、水流の中で確かに魚たちが自分たちを取り囲み、守ってくれているのを見たのだった。一旦、落ち込んだあと、急に上昇し始めた。そして、明かりが近づいてきたような気がした。

タグ:洞窟 風穴 溶岩 穴
-ナレの村-10.水柱 [アスカケ第1部 高千穂峰]
10.水柱
ナギとタカヒコ、そして子どもたちが祠に戻ってくると、村人は皆心配顔をして待っていた。
祠の脇には、深くて大きな水穴があった。水神様を祭るため、ナギの作った注連縄(しめなわ)が穴の周りに取り付けられていた。
穴の脇には巫女セイが座り、詔を奉げていた。ひときわ大きな声になった時だった。
水穴の奥からごぼごぼという音が響いてきた。そして、すさまじい轟音とともに、冷たい水柱が立ち上がった。徐々に水柱が小さくなり、水穴はすぐに満水になり、みたりの御川に清らかな水が満たされ始めた。
じっとその様子を見ていた村人たちも、水柱が作った滴に一気に包まれてしまった。辺り一面、水浸しになっていた。
「あ・・あそこに、カケルとケンが!」
辺りが静かになった時、イツキが気づいて指差した。村人みな、指差す方を見ると、注連縄(しめなわ)に二人がぶら下がっていたのだった。
急いで駆け寄り、二人を助け、岸辺に寝かせた。噴き出す水の流れに巻き込まれたにも関わらず、二人ともすぐに気がついた。そして、ケンが何事もなかったかのように、みたりの御川を見て、こう言った。
「カケル!カケル!・・魚がいっぱいだよ。やったよ!」
余りにも無邪気に魚が跳ねる姿を喜ぶケンに、みな安堵したと同時に、おかしくて笑い出してしまった。
「洞の中で、金色に輝く大きな魚を見たんだ!」
カケルは興奮気味にそう言った。巫女セイが、答える様に言った。
「それは、この川のぬしであろう。先代の巫女も、この祠で祝詞を上げていた時、水穴が輝くのを見ておる。」
「僕は、その魚についていったんだ。そしたら、小魚たちが周りにたくさん集まってきて、そのまま一緒に流されちゃったんだよ。きっと、魚たちが僕たちを運んでくれたんだね。」
清らかな流れは徐々に川下に流れていった。そして、畑に引いた水路にも流れ込んできた。村人たちは、畑に水を引くために戻って行った。
巫女セイと子どもたちは、川の畔に立ち、清流を眺めていた。
「よいか、子どもらよ。・・ここの魚は、お前たちの命を救ってくれた、水神様の使いじゃ。・・くれぐれも、この川を汚したり、この川に入って魚を取ったりするでないぞ。もし、お前たちがこの川の魚を取ろうものなら、川の水が枯れ、田畑も枯れてしまうじゃろう。良いな。」
子どもらは皆こくりとうなづいた。
そして、イツキが訊ねた。
「ねえ、セイ様。この魚たちはどこにいたの?」
「きっと、カケルたちが落ちた穴の奥の奥・・・きっと、あの御山の中に大きな大きなお池があるのじゃ。寒い冬にはそこにじっとしておって、温かくなるとこうして外に出てくるんじゃな。」
「ねえ、そこにセイ様は行ったことがあるの?」
「いや、ない。そこは・・・」
巫女セイは少し答えに困っていた。すると、ケンが横から口を挟んだ。
「おら、知ってるぞ。・・おらの・・おばば様が言ってた。・・この地面の深い深いところに、黄泉というところがあって、いつかはそこに行かなくちゃいけないんだって・・・きっとそこにお池もあるんだよ。」
「何よ、黄泉って?・・ねえ、セイ様、皆、そこに行くの?私、ずっとここに居たいよ。」
イツキは知らない事を自分より小さいケンの口から聞いて少し怒って言った。
「・・ほう、そうか・・黄泉の国のことを知っておったか。・・そうじゃ、いつかは皆そこへ行く。だが、それは、この身が滅びる時じゃ。こうして息をし、食べ、歩き、話をし、毎日毎日祈りを奉げているうちには行けない。そして、一度行ったらもう戻れないんじゃな。」
「死んじゃうと行くところ?私の父様も母様もそこにいるの?」
イツキが訊く。
「ああ、そうじゃな。だが、イツキの父様も母様も、掟を守り毎日毎日しっかり生きた。そうやってちゃんと生きていた者は、またどこかで生まれ変わる事ができるそうじゃ。」
「そうか・・」
「だがな・・・掟を破り、森へ勝手に入ると、黄泉の国への入口がぽかんと口を開けて待っておる。このたびは、なんとか水神様がお救い下されたが・・次は、黄泉の国へまっすぐ連れて行かれるぞ。良いな。」
「はい。」
子どもたちは神妙な顔で返事をし、川の対岸に広がる深い高千穂の森をじっと見ていた。

ナギとタカヒコ、そして子どもたちが祠に戻ってくると、村人は皆心配顔をして待っていた。
祠の脇には、深くて大きな水穴があった。水神様を祭るため、ナギの作った注連縄(しめなわ)が穴の周りに取り付けられていた。
穴の脇には巫女セイが座り、詔を奉げていた。ひときわ大きな声になった時だった。
水穴の奥からごぼごぼという音が響いてきた。そして、すさまじい轟音とともに、冷たい水柱が立ち上がった。徐々に水柱が小さくなり、水穴はすぐに満水になり、みたりの御川に清らかな水が満たされ始めた。
じっとその様子を見ていた村人たちも、水柱が作った滴に一気に包まれてしまった。辺り一面、水浸しになっていた。
「あ・・あそこに、カケルとケンが!」
辺りが静かになった時、イツキが気づいて指差した。村人みな、指差す方を見ると、注連縄(しめなわ)に二人がぶら下がっていたのだった。
急いで駆け寄り、二人を助け、岸辺に寝かせた。噴き出す水の流れに巻き込まれたにも関わらず、二人ともすぐに気がついた。そして、ケンが何事もなかったかのように、みたりの御川を見て、こう言った。
「カケル!カケル!・・魚がいっぱいだよ。やったよ!」
余りにも無邪気に魚が跳ねる姿を喜ぶケンに、みな安堵したと同時に、おかしくて笑い出してしまった。
「洞の中で、金色に輝く大きな魚を見たんだ!」
カケルは興奮気味にそう言った。巫女セイが、答える様に言った。
「それは、この川のぬしであろう。先代の巫女も、この祠で祝詞を上げていた時、水穴が輝くのを見ておる。」
「僕は、その魚についていったんだ。そしたら、小魚たちが周りにたくさん集まってきて、そのまま一緒に流されちゃったんだよ。きっと、魚たちが僕たちを運んでくれたんだね。」
清らかな流れは徐々に川下に流れていった。そして、畑に引いた水路にも流れ込んできた。村人たちは、畑に水を引くために戻って行った。
巫女セイと子どもたちは、川の畔に立ち、清流を眺めていた。
「よいか、子どもらよ。・・ここの魚は、お前たちの命を救ってくれた、水神様の使いじゃ。・・くれぐれも、この川を汚したり、この川に入って魚を取ったりするでないぞ。もし、お前たちがこの川の魚を取ろうものなら、川の水が枯れ、田畑も枯れてしまうじゃろう。良いな。」
子どもらは皆こくりとうなづいた。
そして、イツキが訊ねた。
「ねえ、セイ様。この魚たちはどこにいたの?」
「きっと、カケルたちが落ちた穴の奥の奥・・・きっと、あの御山の中に大きな大きなお池があるのじゃ。寒い冬にはそこにじっとしておって、温かくなるとこうして外に出てくるんじゃな。」
「ねえ、そこにセイ様は行ったことがあるの?」
「いや、ない。そこは・・・」
巫女セイは少し答えに困っていた。すると、ケンが横から口を挟んだ。
「おら、知ってるぞ。・・おらの・・おばば様が言ってた。・・この地面の深い深いところに、黄泉というところがあって、いつかはそこに行かなくちゃいけないんだって・・・きっとそこにお池もあるんだよ。」
「何よ、黄泉って?・・ねえ、セイ様、皆、そこに行くの?私、ずっとここに居たいよ。」
イツキは知らない事を自分より小さいケンの口から聞いて少し怒って言った。
「・・ほう、そうか・・黄泉の国のことを知っておったか。・・そうじゃ、いつかは皆そこへ行く。だが、それは、この身が滅びる時じゃ。こうして息をし、食べ、歩き、話をし、毎日毎日祈りを奉げているうちには行けない。そして、一度行ったらもう戻れないんじゃな。」
「死んじゃうと行くところ?私の父様も母様もそこにいるの?」
イツキが訊く。
「ああ、そうじゃな。だが、イツキの父様も母様も、掟を守り毎日毎日しっかり生きた。そうやってちゃんと生きていた者は、またどこかで生まれ変わる事ができるそうじゃ。」
「そうか・・」
「だがな・・・掟を破り、森へ勝手に入ると、黄泉の国への入口がぽかんと口を開けて待っておる。このたびは、なんとか水神様がお救い下されたが・・次は、黄泉の国へまっすぐ連れて行かれるぞ。良いな。」
「はい。」
子どもたちは神妙な顔で返事をし、川の対岸に広がる深い高千穂の森をじっと見ていた。

タグ:水柱 湧水 霧島
-母と子‐1.薬草探し [アスカケ第1部 高千穂峰]
1.薬草探し
ケスキの旅立ちから2年、カケルは10歳になった。変わらず、イツキと一緒に、川で魚を獲ったり果物をとったり、畑の仕事をしたりしながら過ごしていた。
カケルは、ずっと心配事を抱えていた。母ナミが、昨年の冬に一度倒れてから、度々寝込むようになってしまったからだ。父ナギは、「春になれば元気になる」と言ったが、もう夏も間近になのにまったく良くならなかった。カケルは何としてでも母を元気にしたいと考えていた。
村中の一番北のはずれに、村の事を相談する館がある。そこには、巫女セイの祈りの場も設えられていた。
昨夜の事。巫女セイが、村の女たちを集めた。女たちは車座に座り、セイの話を聞いた。
「ナミはもう長くはないじゃろう。病の気が知らず知らずのうちに身に広がっておる。・・痛みもかなりだろう。ナミは辛抱強いおなごじゃから、泣き言など言わぬじゃろうが・・相当な苦痛のはずじゃ。」
「何とかならないのですか!」
車座の真ん中に座っていたハルが、嘆くように言った。ハルは、エン・セン・ケンの兄弟の母だった。ナミとは同い年で、三人目のケンを産んだ時、ナミに二人の子どもの世話を頼んで以来、姉妹のように過ごしていたのだ。
「うむ・・ナミの病をみて、何とかならぬものかと考えたんじゃが・・・。」
「何か手はないのですか?」
「・・ひとつだけ・・試すべき事がある。」
そう言って、巫女セイは、懐から書物を取り出した。
この頃の倭国には、まだ、文字などなかった。しかし、ナレの村の一族は、昔、大陸の戦乱を逃れ、倭国に渡った渡来人であり、先人たちは、いくつかの書物を持ち込んでいた。ナレの村の人々は、幼い頃から、この書物を頼りに、大陸の文字を学んでいたのだ。しかし、迫害を恐れ、渡来人であることをひたすら隠し、この地に根付いてからも、普段の暮らしの中では文字を使うことを厳しく禁じていた。
「それは・・」
「そうじゃ・・いにしえより伝わる書のひとつじゃ。・・これは、野山の草木で病を治す術が記してある。ワシは、この中を丹念に読んだ。そして、ナミの病を治すための薬を見つけた。」
「じゃあ・・それを摘んで飲ませれば・・ナミは元気になるのでしょうか。」
「・・そうじゃ・・だが・・これは、古人(いにしえびと)が遥か大陸で得た知恵じゃ。この地にその草木があるかどうかもわからぬ。また、あるとしても、どれくらい飲ませればよいかもわからぬのじゃ。・・間違えれば毒になるやもしれぬ。」
車座に座った女たちは、じっと考え込んだ。巫女の言うとおり、もし違えば、弱っているナミをさらに苦しめるかもしれない。いや、それがきっかけに命を落とすかもしれなかった。
「でも、セイ様。このままではいずれナミは命を落とすのでしょう。」
「ああ・・日に日に体は弱り、いずれは、苦痛に耐え切れずに果てる事になるじゃろう。」
それを聞いて、ケスキの母モヨが言った。
「それなら・・・私たちがまず、その書物にある草木を集めましょう。そして、ほんの少し、自分たちが試してみましょう。私たちは元気です。多少の毒なら耐えられるはずです。大丈夫なら、ナミに飲ませてみる。ねえ、どう?」
女たちは皆、頷いた。
「そうか・・皆がそういうなら、まずは草木を集めよう。・・だが・・良いか、まだどうなるかは判らぬものじゃ。日々の仕事の合間に、命達(みこと)には気づかれぬように探すのじゃ。この事を知れば、命達はきっと反対するじゃろう。わが身をかけて・・草木の毒を調べるのじゃからな。良いな。」
女たちは互いに見つめあい、覚悟を確認するように頷いた。
巫女セイは、書物を大事そうにゆっくりと開いた。皆、黙って一つ一つ確認するように見入った。痛みに効く草、力をつける草・・ナミの体の具合を思い浮かべながら、どの草が良いのかじっくりと選んでいった。
次の日から、薬草探しが始まった。初夏は、田畑の仕事が多い。男たちは山へ猟に出かける事も多く、女たちはほとんど田畑の仕事に追われていた。みな、交代に仕事をしながら、田畑の周りや、みたりの御川の土手、子どもは入れない森、とにかく村の周りを隅々まで回って、薬草を探した。そして、夜毎、館に集まると、取ってきた草を広げて、書物の絵と見比べながら吟味していった。1週間ほどが過ぎたが、なかなか薬草と思えるものが見つからない。似た草はあるのだが、葉の形や根の形、花の色、それぞれ少しずつ違うものばかりだった。
次の日も次の日も、薬草探しは続いた。しかし、なかなか見つからなかった。
「セイ様・・ナミの病に利く薬草は本当にあるのでしょうか?やはり、大陸にしかないのでは?」
半ばあきらめに似た空気が漂っていた。

ケスキの旅立ちから2年、カケルは10歳になった。変わらず、イツキと一緒に、川で魚を獲ったり果物をとったり、畑の仕事をしたりしながら過ごしていた。
カケルは、ずっと心配事を抱えていた。母ナミが、昨年の冬に一度倒れてから、度々寝込むようになってしまったからだ。父ナギは、「春になれば元気になる」と言ったが、もう夏も間近になのにまったく良くならなかった。カケルは何としてでも母を元気にしたいと考えていた。
村中の一番北のはずれに、村の事を相談する館がある。そこには、巫女セイの祈りの場も設えられていた。
昨夜の事。巫女セイが、村の女たちを集めた。女たちは車座に座り、セイの話を聞いた。
「ナミはもう長くはないじゃろう。病の気が知らず知らずのうちに身に広がっておる。・・痛みもかなりだろう。ナミは辛抱強いおなごじゃから、泣き言など言わぬじゃろうが・・相当な苦痛のはずじゃ。」
「何とかならないのですか!」
車座の真ん中に座っていたハルが、嘆くように言った。ハルは、エン・セン・ケンの兄弟の母だった。ナミとは同い年で、三人目のケンを産んだ時、ナミに二人の子どもの世話を頼んで以来、姉妹のように過ごしていたのだ。
「うむ・・ナミの病をみて、何とかならぬものかと考えたんじゃが・・・。」
「何か手はないのですか?」
「・・ひとつだけ・・試すべき事がある。」
そう言って、巫女セイは、懐から書物を取り出した。
この頃の倭国には、まだ、文字などなかった。しかし、ナレの村の一族は、昔、大陸の戦乱を逃れ、倭国に渡った渡来人であり、先人たちは、いくつかの書物を持ち込んでいた。ナレの村の人々は、幼い頃から、この書物を頼りに、大陸の文字を学んでいたのだ。しかし、迫害を恐れ、渡来人であることをひたすら隠し、この地に根付いてからも、普段の暮らしの中では文字を使うことを厳しく禁じていた。
「それは・・」
「そうじゃ・・いにしえより伝わる書のひとつじゃ。・・これは、野山の草木で病を治す術が記してある。ワシは、この中を丹念に読んだ。そして、ナミの病を治すための薬を見つけた。」
「じゃあ・・それを摘んで飲ませれば・・ナミは元気になるのでしょうか。」
「・・そうじゃ・・だが・・これは、古人(いにしえびと)が遥か大陸で得た知恵じゃ。この地にその草木があるかどうかもわからぬ。また、あるとしても、どれくらい飲ませればよいかもわからぬのじゃ。・・間違えれば毒になるやもしれぬ。」
車座に座った女たちは、じっと考え込んだ。巫女の言うとおり、もし違えば、弱っているナミをさらに苦しめるかもしれない。いや、それがきっかけに命を落とすかもしれなかった。
「でも、セイ様。このままではいずれナミは命を落とすのでしょう。」
「ああ・・日に日に体は弱り、いずれは、苦痛に耐え切れずに果てる事になるじゃろう。」
それを聞いて、ケスキの母モヨが言った。
「それなら・・・私たちがまず、その書物にある草木を集めましょう。そして、ほんの少し、自分たちが試してみましょう。私たちは元気です。多少の毒なら耐えられるはずです。大丈夫なら、ナミに飲ませてみる。ねえ、どう?」
女たちは皆、頷いた。
「そうか・・皆がそういうなら、まずは草木を集めよう。・・だが・・良いか、まだどうなるかは判らぬものじゃ。日々の仕事の合間に、命達(みこと)には気づかれぬように探すのじゃ。この事を知れば、命達はきっと反対するじゃろう。わが身をかけて・・草木の毒を調べるのじゃからな。良いな。」
女たちは互いに見つめあい、覚悟を確認するように頷いた。
巫女セイは、書物を大事そうにゆっくりと開いた。皆、黙って一つ一つ確認するように見入った。痛みに効く草、力をつける草・・ナミの体の具合を思い浮かべながら、どの草が良いのかじっくりと選んでいった。
次の日から、薬草探しが始まった。初夏は、田畑の仕事が多い。男たちは山へ猟に出かける事も多く、女たちはほとんど田畑の仕事に追われていた。みな、交代に仕事をしながら、田畑の周りや、みたりの御川の土手、子どもは入れない森、とにかく村の周りを隅々まで回って、薬草を探した。そして、夜毎、館に集まると、取ってきた草を広げて、書物の絵と見比べながら吟味していった。1週間ほどが過ぎたが、なかなか薬草と思えるものが見つからない。似た草はあるのだが、葉の形や根の形、花の色、それぞれ少しずつ違うものばかりだった。
次の日も次の日も、薬草探しは続いた。しかし、なかなか見つからなかった。
「セイ様・・ナミの病に利く薬草は本当にあるのでしょうか?やはり、大陸にしかないのでは?」
半ばあきらめに似た空気が漂っていた。

タグ:薬草 病 母 ナミ
-母と子‐2.諦め [アスカケ第1部 高千穂峰]
2.諦め
毎夜、女たちがこっそり館に集まっているのを命(ミコト)たちも気付いていた。
ある晩、女たちがいつものように薬草とおぼしきものを抱え、館に集まり、ひとつひとつ吟味しているところに、ナギをはじめ数人の命(ミコト)がやってきた。
「お前たち、何をしているのだ。」
その声に皆持ってきた草を懐にしまったが、遅れてやってきたハルが様子を知らずに草をもって入ってきた。そして、
「セイ様、この草はきっと薬草です。さあ。」
と言った。皆、入口に立っていたハルを見た。セイが観念したように、事情を説明した。
「そんな無茶な事。仮に薬草が見つかったとしても、お前たちが試してもし命を落とす事になったらどうするのだ。・・・そんな事、ナミは望んではいない。・・・ナミの命が尽きるのは天の定め。受け入れる覚悟は出来ている。だが、お前たちの命を絶つような事は許さない。」
ナギは、強く咎めるようにそう言い放った。そして、
「セイ様。もう充分です。皆にやめる様に言って下さい。」
ナギの目からは涙が零れていた。皆の心遣い、努力を決して否定するのではなく、ナギとしても直せるものならばと考え、日々、ナミの体に少しでも滋養になるものをと必死で探し食べさせてきた。だが、ナミの辛さは想像以上であったのだ。毎夜、苦痛に喘ぎながらも、ナギや子どもたちに心配をかけまいと必死に堪えるナミの辛さもそばに居て一番わかっている。
女たちも、ナギの思いを強く感じ、ともに泣いた。自分たちの無力さを痛いほどに感じながら、ともに泣いた。
イツキは、女たちが毎夜集まる事をミコトたちよりも先に知っていた。そして、その晩もこっそり館の物入れの中に身を潜めていた。ナギと女たちの泣く様を目の当たりし、イツキも一緒に泣いた。
次の日、イツキはカケルとともに、西の谷の川に行った。イツキは、ヤマモモの木に登り、実を集めながら、昨夜の出来事をカケルに話すべきか考えていた。
イツキは母を病気で亡くし、ナミに育てられた。今では、実の母以上に大切な存在である。病を治したい想いは、きっとナギやカケルに負けるものではなかった。しかし、自分の力で出来る事等なく、悔しくて悔しくて仕方なかった。薬草探しが中断され、もはや、村の人もナミを病から救う事を諦めている。しかし、イツキにはどうしても諦め切れなかった。
「ねえ、カケル。」
イツキは思い切ってカケルに昨夜の出来事を話した。カケルはじっとイツキの話を聞くと、こう言った。
「とと様も、ずっと薬草を探していたんだよ。今朝、とと様が言ったんだ。村の人たちにはこれ以上迷惑を掛けられない、かか様も体が痛くて、長くないだろう、覚悟しておくんだって。」
「そうだったの・・・。」
「だけど、俺は諦め切れない。きっとかか様の病を治してやるんだ。・・・だけど、薬草がどんなものかも判らないんだ。」
そう言うと、カケルは今まで秘めてきた悔しい想いが胸にこみ上げてきて、大粒の涙を流し、泣き始めた。イツキもカケルの涙につられ、ともに泣いた。しばらく泣いた後、ようやく正気に戻った二人は、何か出来る事は無いかを考えた。
「イツキ、皆はどんな草を探していたんだ?」
「判らない。でも、館に赤い色をした大事な書物があって、それを開いてみていたみたいだった。」
「そうか・・・その書物を見れば何かわかるんだな・・・。よし、その書物を見に行こう。・・昼間、誰も居ない時こっそり入ればいいだろう。」
二人は、翌日、巫女セイが館を出るのを確認して、こっそり、館に忍び込んだ。そして、祭壇の周りを探した。書物は祭壇の下の棚に仕舞われていた。
「ねえ、カケル。書物の中身がわかるの?」
「大丈夫さ。かか様から文字は教わってる。きっといつか役に立つからと、かか様が教えてくれたんだ。イツキにも教えてくれるって言ってたが、病になってそうもいかなくなったんだ。」
二人は書物を開いた。上・中・下の文字、草・木等に分かれて書物は書かれていた。文字を一つずつ辿りながら、病の事・草や木の特徴などを読んで行った。もちろん、まだ判らない文字もたくさんあった。挿絵も描かれていたが、どれも目にしたことは無いようなものばかりだった。
館の外で、巫女セイの声がした。二人は急いで書物を棚に戻すと、見つからぬように館の窓から外に出た。
「だめだ・・すぐには判らない。明日もう一度書物を見に行こう。」
二人は、次の日も次の日も書物を見るために館に忍び込んだ。
四日目の事だった。イツキが書物を開いていた時、
「これ、見たことある。西の谷で・・・」
カケルは、イツキが示す挿絵をじっと見つめた。
「うん、これ。確か・・・見たことある。・・・これ、病に効くのか・・・良し、これを取ってこよう。そして、巫女様に見てもらうんだ。」
挿絵にあったのは、奇妙な形をしたキノコだった。
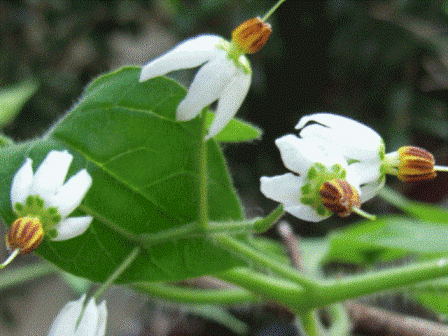
毎夜、女たちがこっそり館に集まっているのを命(ミコト)たちも気付いていた。
ある晩、女たちがいつものように薬草とおぼしきものを抱え、館に集まり、ひとつひとつ吟味しているところに、ナギをはじめ数人の命(ミコト)がやってきた。
「お前たち、何をしているのだ。」
その声に皆持ってきた草を懐にしまったが、遅れてやってきたハルが様子を知らずに草をもって入ってきた。そして、
「セイ様、この草はきっと薬草です。さあ。」
と言った。皆、入口に立っていたハルを見た。セイが観念したように、事情を説明した。
「そんな無茶な事。仮に薬草が見つかったとしても、お前たちが試してもし命を落とす事になったらどうするのだ。・・・そんな事、ナミは望んではいない。・・・ナミの命が尽きるのは天の定め。受け入れる覚悟は出来ている。だが、お前たちの命を絶つような事は許さない。」
ナギは、強く咎めるようにそう言い放った。そして、
「セイ様。もう充分です。皆にやめる様に言って下さい。」
ナギの目からは涙が零れていた。皆の心遣い、努力を決して否定するのではなく、ナギとしても直せるものならばと考え、日々、ナミの体に少しでも滋養になるものをと必死で探し食べさせてきた。だが、ナミの辛さは想像以上であったのだ。毎夜、苦痛に喘ぎながらも、ナギや子どもたちに心配をかけまいと必死に堪えるナミの辛さもそばに居て一番わかっている。
女たちも、ナギの思いを強く感じ、ともに泣いた。自分たちの無力さを痛いほどに感じながら、ともに泣いた。
イツキは、女たちが毎夜集まる事をミコトたちよりも先に知っていた。そして、その晩もこっそり館の物入れの中に身を潜めていた。ナギと女たちの泣く様を目の当たりし、イツキも一緒に泣いた。
次の日、イツキはカケルとともに、西の谷の川に行った。イツキは、ヤマモモの木に登り、実を集めながら、昨夜の出来事をカケルに話すべきか考えていた。
イツキは母を病気で亡くし、ナミに育てられた。今では、実の母以上に大切な存在である。病を治したい想いは、きっとナギやカケルに負けるものではなかった。しかし、自分の力で出来る事等なく、悔しくて悔しくて仕方なかった。薬草探しが中断され、もはや、村の人もナミを病から救う事を諦めている。しかし、イツキにはどうしても諦め切れなかった。
「ねえ、カケル。」
イツキは思い切ってカケルに昨夜の出来事を話した。カケルはじっとイツキの話を聞くと、こう言った。
「とと様も、ずっと薬草を探していたんだよ。今朝、とと様が言ったんだ。村の人たちにはこれ以上迷惑を掛けられない、かか様も体が痛くて、長くないだろう、覚悟しておくんだって。」
「そうだったの・・・。」
「だけど、俺は諦め切れない。きっとかか様の病を治してやるんだ。・・・だけど、薬草がどんなものかも判らないんだ。」
そう言うと、カケルは今まで秘めてきた悔しい想いが胸にこみ上げてきて、大粒の涙を流し、泣き始めた。イツキもカケルの涙につられ、ともに泣いた。しばらく泣いた後、ようやく正気に戻った二人は、何か出来る事は無いかを考えた。
「イツキ、皆はどんな草を探していたんだ?」
「判らない。でも、館に赤い色をした大事な書物があって、それを開いてみていたみたいだった。」
「そうか・・・その書物を見れば何かわかるんだな・・・。よし、その書物を見に行こう。・・昼間、誰も居ない時こっそり入ればいいだろう。」
二人は、翌日、巫女セイが館を出るのを確認して、こっそり、館に忍び込んだ。そして、祭壇の周りを探した。書物は祭壇の下の棚に仕舞われていた。
「ねえ、カケル。書物の中身がわかるの?」
「大丈夫さ。かか様から文字は教わってる。きっといつか役に立つからと、かか様が教えてくれたんだ。イツキにも教えてくれるって言ってたが、病になってそうもいかなくなったんだ。」
二人は書物を開いた。上・中・下の文字、草・木等に分かれて書物は書かれていた。文字を一つずつ辿りながら、病の事・草や木の特徴などを読んで行った。もちろん、まだ判らない文字もたくさんあった。挿絵も描かれていたが、どれも目にしたことは無いようなものばかりだった。
館の外で、巫女セイの声がした。二人は急いで書物を棚に戻すと、見つからぬように館の窓から外に出た。
「だめだ・・すぐには判らない。明日もう一度書物を見に行こう。」
二人は、次の日も次の日も書物を見るために館に忍び込んだ。
四日目の事だった。イツキが書物を開いていた時、
「これ、見たことある。西の谷で・・・」
カケルは、イツキが示す挿絵をじっと見つめた。
「うん、これ。確か・・・見たことある。・・・これ、病に効くのか・・・良し、これを取ってこよう。そして、巫女様に見てもらうんだ。」
挿絵にあったのは、奇妙な形をしたキノコだった。
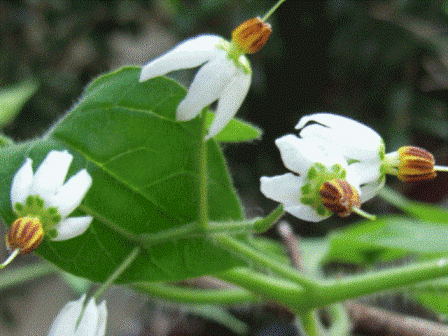
タグ:薬草 母 病 きのこ
-母と子‐3.濁流 [アスカケ第1部 高千穂峰]
3.濁流
カケルとイツキは、昨日、書物で見つけた「奇妙な形をしたキノコ」を探すため、日の出とともにこっそりと家を出た。この頃は、長雨の季節に入っていて、田畑の仕事も、猟も出来ない日が多く、村人たちはほんと家の中の仕事をしていた。薄暗い中では仕事もおぼつかないため、皆、いつもより遅くまで眠っていた。
二人は、ひっそりとした村を抜け出すために、閉じられた大門は使えず、裏山に続く北の塀によじ登るほかなかった。カケルは、ナギの拵えた長縄を一巻き、借り出して、塀の上に掛け、よじ登り、イツキを引き上げて、どうにか抜け出すことが出来た。
長雨で、山肌のあちこちで、しぶきを上げて流れる水が道を塞ぐほどであった。だから、この時期に、西の谷に行くというのは決して許される事ではなく、だからこそ二人はこっそりと抜け出したのだった。
西の谷につく途中、何度か足元をすくわれるほどの泥濘を越え、時には下り坂で滑りながら西の谷を目指した。いつもなら容易に行ける道のりが、今日はとても険しいものであった。
二人が西の谷に着くころに、ナギもようやく二人の姿が見えないことに不審を感じていた。そして、村の家々を訪ね二人の所在を確認したが、わからない。
村のミコトたちが館に集まり、二人の行方を相談した。そこに巫女セイも顔を出した。
「先日来、書物を誰かが触った形跡がある。もしや、あの二人、書物を読んでおったのではないかな。」
「まさか、まだ子どもだぞよ。文字など読めるはずも無い。それに、ここに書物がある事など知る由も無い。」
「いや、カケルはもう文字は覚えておる。幼き時より、ナミが文字を教えた。」
ナギがそう答える。
「だが、書物がここにあるのを知っているはずは・・・・」
「いや、先日の女たちの次第を俺がカケルに話した。ひょっとしたら、その後、ここに忍び込んで見つけたのやも知れぬ。」
「セイ様、誰かが開いたようですか?」
「ああ・・草の巻だけでではない、木や茸の巻も開いておる様じゃ。」
「じゃあ、子ども二人で薬草探しに行ったのか。」
「この大雨じゃ、山道は危ないぞ。無事に戻れば良いが・・。」
ミコトたちは皆心配した。
「探し手をだすか?」
それにはナギが答えた。
「いや、探し手とてこの雨では危なかろう。日暮れまでにはきっと戻るだろう。ここで待つ。」
「なら、せめて、大門を開け、村の周囲だけでも見て回ろう。」
そう決まり、ミコトたちは手分けして、村の周囲の田畑や尾根筋辺りに出て行った。
その頃、二人は西の谷を流れる神川のほとりに居た。いつもは静かな清流が、茶色の濁流に変わり、水かさもいつもより随分増えていた。

「ここは通れない。・・・他の道を行こう。」
カケルはそう言うと、川上に向って畔を歩き始めた。足元はかなり泥濘んでいる。足をとられ転びそうになったイツキの手を取り、ゆっくりと進んで行った。
しばらく行くと、大岩が数個並んでいる場所があり、その上を通れば対岸にいけそうであった。ゆっくりと岩の上に上がる。滑りそうで足元がおぼつかない。
イツキは岩の上に立って周囲を見回す。曇り空と茂る木々で、薄暗い森の風景を眺めているのではない。いつものように通う淵の畔にある山桃の木を探しているのだ。
「カケル!淵はどこ?」
カケルも辺りをじっと見渡し、指で淵のある方向を指した。
「あっちだ。少し、山に入ってしまった。」
「まよったの?」
「いや、大丈夫だ。川を下っていけばつける。もう少しだよ。」
「ぶなの木・・ぶなの木が目印よ。」
「ああ・・多分、あそこにあるはずだ。」
二人はやっとの思いで大岩を越え、対岸に渡った。
水かさが増えたせいか、いつもなら川岸に歩きやすい場所があるのだが、ほとんど見えず、やむなく、森の中に入りながら川を左手に見ながら進んだ。ようやく、いつもの淵に辿り着いた。いつも透き通る程の清流で底まで見える淵も、茶色の濁流で一変している。水は山桃の木の根元近くまで迫っていた。
「あんなところまで水が来てる。大丈夫かなあ。」
「大丈夫だよ。山桃の木はイツキのとと様の木だろ。さあ、キノコを探そう。」
二人は求めているキノコを探し始めた。以前、淵を泳ぎ渡り辿り着いた対岸で、蕨取りをしていた時に、大きなぶなの木の根元辺りで、おかしな形のキノコを見たのだ。村では、「キノコには霊が宿る。人に良い霊と悪い霊が居る。むやみに触れてはならない。」と言われていて、おかしなキノコを見つけた時も、触れずそっとしておいたのだった。

カケルとイツキは、昨日、書物で見つけた「奇妙な形をしたキノコ」を探すため、日の出とともにこっそりと家を出た。この頃は、長雨の季節に入っていて、田畑の仕事も、猟も出来ない日が多く、村人たちはほんと家の中の仕事をしていた。薄暗い中では仕事もおぼつかないため、皆、いつもより遅くまで眠っていた。
二人は、ひっそりとした村を抜け出すために、閉じられた大門は使えず、裏山に続く北の塀によじ登るほかなかった。カケルは、ナギの拵えた長縄を一巻き、借り出して、塀の上に掛け、よじ登り、イツキを引き上げて、どうにか抜け出すことが出来た。
長雨で、山肌のあちこちで、しぶきを上げて流れる水が道を塞ぐほどであった。だから、この時期に、西の谷に行くというのは決して許される事ではなく、だからこそ二人はこっそりと抜け出したのだった。
西の谷につく途中、何度か足元をすくわれるほどの泥濘を越え、時には下り坂で滑りながら西の谷を目指した。いつもなら容易に行ける道のりが、今日はとても険しいものであった。
二人が西の谷に着くころに、ナギもようやく二人の姿が見えないことに不審を感じていた。そして、村の家々を訪ね二人の所在を確認したが、わからない。
村のミコトたちが館に集まり、二人の行方を相談した。そこに巫女セイも顔を出した。
「先日来、書物を誰かが触った形跡がある。もしや、あの二人、書物を読んでおったのではないかな。」
「まさか、まだ子どもだぞよ。文字など読めるはずも無い。それに、ここに書物がある事など知る由も無い。」
「いや、カケルはもう文字は覚えておる。幼き時より、ナミが文字を教えた。」
ナギがそう答える。
「だが、書物がここにあるのを知っているはずは・・・・」
「いや、先日の女たちの次第を俺がカケルに話した。ひょっとしたら、その後、ここに忍び込んで見つけたのやも知れぬ。」
「セイ様、誰かが開いたようですか?」
「ああ・・草の巻だけでではない、木や茸の巻も開いておる様じゃ。」
「じゃあ、子ども二人で薬草探しに行ったのか。」
「この大雨じゃ、山道は危ないぞ。無事に戻れば良いが・・。」
ミコトたちは皆心配した。
「探し手をだすか?」
それにはナギが答えた。
「いや、探し手とてこの雨では危なかろう。日暮れまでにはきっと戻るだろう。ここで待つ。」
「なら、せめて、大門を開け、村の周囲だけでも見て回ろう。」
そう決まり、ミコトたちは手分けして、村の周囲の田畑や尾根筋辺りに出て行った。
その頃、二人は西の谷を流れる神川のほとりに居た。いつもは静かな清流が、茶色の濁流に変わり、水かさもいつもより随分増えていた。

「ここは通れない。・・・他の道を行こう。」
カケルはそう言うと、川上に向って畔を歩き始めた。足元はかなり泥濘んでいる。足をとられ転びそうになったイツキの手を取り、ゆっくりと進んで行った。
しばらく行くと、大岩が数個並んでいる場所があり、その上を通れば対岸にいけそうであった。ゆっくりと岩の上に上がる。滑りそうで足元がおぼつかない。
イツキは岩の上に立って周囲を見回す。曇り空と茂る木々で、薄暗い森の風景を眺めているのではない。いつものように通う淵の畔にある山桃の木を探しているのだ。
「カケル!淵はどこ?」
カケルも辺りをじっと見渡し、指で淵のある方向を指した。
「あっちだ。少し、山に入ってしまった。」
「まよったの?」
「いや、大丈夫だ。川を下っていけばつける。もう少しだよ。」
「ぶなの木・・ぶなの木が目印よ。」
「ああ・・多分、あそこにあるはずだ。」
二人はやっとの思いで大岩を越え、対岸に渡った。
水かさが増えたせいか、いつもなら川岸に歩きやすい場所があるのだが、ほとんど見えず、やむなく、森の中に入りながら川を左手に見ながら進んだ。ようやく、いつもの淵に辿り着いた。いつも透き通る程の清流で底まで見える淵も、茶色の濁流で一変している。水は山桃の木の根元近くまで迫っていた。
「あんなところまで水が来てる。大丈夫かなあ。」
「大丈夫だよ。山桃の木はイツキのとと様の木だろ。さあ、キノコを探そう。」
二人は求めているキノコを探し始めた。以前、淵を泳ぎ渡り辿り着いた対岸で、蕨取りをしていた時に、大きなぶなの木の根元辺りで、おかしな形のキノコを見たのだ。村では、「キノコには霊が宿る。人に良い霊と悪い霊が居る。むやみに触れてはならない。」と言われていて、おかしなキノコを見つけた時も、触れずそっとしておいたのだった。

-母と子-4.ぶなの森 [アスカケ第1部 高千穂峰]
4.ぶなの森
「変だなあ、確かこの辺りだったはずなんだけど・・・。」
夏草を分けながら、カケルが言う。
「大きなぶなの木の近くにあったはずなのに・・・無くなったのかな。」
「もっと奥の方だったかな?」
見上げてみると、大きなぶなの木は、岸辺には1本だったが、よく見ると森の奥はすべてぶなやこならの木が続いていた。
「きっと生えてはすぐに消えてしまうのよ。もっと探してみようか。」
二人は、木々の根元に視線をやりながら森の中に入って行った。
谷に着いた時には暗かった空も、雲が切れ、日が差し始めていた。木々の間から差し込む光が安心させたのか、二人とも知らぬうちに随分森深くまで入ってしまっていた。
「カケル!これ、違うかな?」

イツキがミズナラの木の根元に、黄色い色をしたキノコを見つけた。霊が宿るといわれていたため、すぐには触ることが出来なかった。カケルはすぐにイツキのもとにやってきた。そして、膝を付いてそのキノコをじっくり見つめた。書物に書かれていた薬になるキノコの絵を頭に思い出しながら、じっくり見た。そして、
「きっとそうだ。色も黄色くて・・きっとそうだよ。」
カケルは、躊躇いなくキノコを手に取った。そして、懐から麻袋を取り出してしまった。
「でもこれだけじゃきっと足りない。もっと見つけなくちゃ。」
そう言って、木の周りを探した。よく見ると、周りの木々の根元にも同じようなキノコが生えている。茶色いものも赤みがかったものもあった。二人は、次々に見つけて袋に中にしまっていった。
「これくらいあればきっと大丈夫だろ。・・・ここを覚えておいてまた来ればいい。」
カケルは、キノコを見つけたミズナラの木に、服の袖を裂いて、結びつけた。
「これが目印だ。・・よし、帰ろう。早く戻らないと、とと様が心配する。」
そう言って、来た道を戻ろうとした。イツキもカケルについて歩いた。しばらく歩いてから、カケルが立ち止まった。
「おかしいな。さっき、ここに岩があったはず・・・それに大きなぶなの木も・・・。」
「ねえ、帰り道が判らなくなったの?」
カケルは返事をしなかった。そして、辺りの様子をじっと伺っていた。
「ねえ、カケル?大丈夫?」
「大丈夫、きっとこのまままっすぐ行けば川に出るはずだから。」
そう言ってまた歩き始めた。だが、なかなか川に辿り着かなかった。
「おかしいなあ・・・そろそろ川に出るはずなんだけどなあ・・・。」
カケルの一言で、イツキは胸の中にじわりと言葉に出来ない不安がこみ上げてきた。カケルと森に入るのはいつもの事だった。カケルが森で迷うなんて思いもしなかった。イツキは、カケルの後ろを歩きながら、怖くて怖くて今にも泣き出しそうになっていた。ひょっとしたら、キノコを採ったことでキノコに宿る悪い霊に迷わせられているのではないか・・そんな不安を抱えていた。
「あ!見えた。川が見えた。」
カケルがそう言って急に駆け出した。イツキも遅れないようにカケルの後を追う。
二人は森をようやく抜け、川辺に辿り着けた。不安と怖さを堪えていたイツキが、川辺にしゃがみこんで、安心したのか、堪えていた気持ちが急に緩んで、大声をだして泣き始めた。
「どうしたんだよ、イツキ。川に着いたんだよ?」
「うん・・うん・・」
そう頷きながらも、イツキはしばらく泣き止まなかった。
「イツキ、ちょっとここにいろ。すぐに戻るから。」
カケルはそう言うと、また森に戻っていった。そしてすぐに戻ってきて、
「ほら、腹が減ったろ。」
そう言って、腰につけた袋から、黄色い実を何個も取り出してイツキに渡した。それは、ビワの実だった。
「さっきの森で、見つけたんだ。でも、美味しそうだったから採って来た。甘くて美味いぞ。」
カケルはそう言うと、むしゃむしゃと食べ始めた。イツキは、そんなカケルを見て、何だかとても腹立たしく感じていた。さっきまで道に迷ってしまって不安で不安で仕方なかったのに、カケルはちっとも不安を感じていなかった。それが妙に腹立たしかった。
しかし、安心したのもつかの間だった。さっきまで晴れていた空が、再び曇り空に変わり、山の高いところではもう雨が降り始めているようだった。目の前の川も、見る見るうちにまた水かさをましているのだった。

「変だなあ、確かこの辺りだったはずなんだけど・・・。」
夏草を分けながら、カケルが言う。
「大きなぶなの木の近くにあったはずなのに・・・無くなったのかな。」
「もっと奥の方だったかな?」
見上げてみると、大きなぶなの木は、岸辺には1本だったが、よく見ると森の奥はすべてぶなやこならの木が続いていた。
「きっと生えてはすぐに消えてしまうのよ。もっと探してみようか。」
二人は、木々の根元に視線をやりながら森の中に入って行った。
谷に着いた時には暗かった空も、雲が切れ、日が差し始めていた。木々の間から差し込む光が安心させたのか、二人とも知らぬうちに随分森深くまで入ってしまっていた。
「カケル!これ、違うかな?」

イツキがミズナラの木の根元に、黄色い色をしたキノコを見つけた。霊が宿るといわれていたため、すぐには触ることが出来なかった。カケルはすぐにイツキのもとにやってきた。そして、膝を付いてそのキノコをじっくり見つめた。書物に書かれていた薬になるキノコの絵を頭に思い出しながら、じっくり見た。そして、
「きっとそうだ。色も黄色くて・・きっとそうだよ。」
カケルは、躊躇いなくキノコを手に取った。そして、懐から麻袋を取り出してしまった。
「でもこれだけじゃきっと足りない。もっと見つけなくちゃ。」
そう言って、木の周りを探した。よく見ると、周りの木々の根元にも同じようなキノコが生えている。茶色いものも赤みがかったものもあった。二人は、次々に見つけて袋に中にしまっていった。
「これくらいあればきっと大丈夫だろ。・・・ここを覚えておいてまた来ればいい。」
カケルは、キノコを見つけたミズナラの木に、服の袖を裂いて、結びつけた。
「これが目印だ。・・よし、帰ろう。早く戻らないと、とと様が心配する。」
そう言って、来た道を戻ろうとした。イツキもカケルについて歩いた。しばらく歩いてから、カケルが立ち止まった。
「おかしいな。さっき、ここに岩があったはず・・・それに大きなぶなの木も・・・。」
「ねえ、帰り道が判らなくなったの?」
カケルは返事をしなかった。そして、辺りの様子をじっと伺っていた。
「ねえ、カケル?大丈夫?」
「大丈夫、きっとこのまままっすぐ行けば川に出るはずだから。」
そう言ってまた歩き始めた。だが、なかなか川に辿り着かなかった。
「おかしいなあ・・・そろそろ川に出るはずなんだけどなあ・・・。」
カケルの一言で、イツキは胸の中にじわりと言葉に出来ない不安がこみ上げてきた。カケルと森に入るのはいつもの事だった。カケルが森で迷うなんて思いもしなかった。イツキは、カケルの後ろを歩きながら、怖くて怖くて今にも泣き出しそうになっていた。ひょっとしたら、キノコを採ったことでキノコに宿る悪い霊に迷わせられているのではないか・・そんな不安を抱えていた。
「あ!見えた。川が見えた。」
カケルがそう言って急に駆け出した。イツキも遅れないようにカケルの後を追う。
二人は森をようやく抜け、川辺に辿り着けた。不安と怖さを堪えていたイツキが、川辺にしゃがみこんで、安心したのか、堪えていた気持ちが急に緩んで、大声をだして泣き始めた。
「どうしたんだよ、イツキ。川に着いたんだよ?」
「うん・・うん・・」
そう頷きながらも、イツキはしばらく泣き止まなかった。
「イツキ、ちょっとここにいろ。すぐに戻るから。」
カケルはそう言うと、また森に戻っていった。そしてすぐに戻ってきて、
「ほら、腹が減ったろ。」
そう言って、腰につけた袋から、黄色い実を何個も取り出してイツキに渡した。それは、ビワの実だった。
「さっきの森で、見つけたんだ。でも、美味しそうだったから採って来た。甘くて美味いぞ。」
カケルはそう言うと、むしゃむしゃと食べ始めた。イツキは、そんなカケルを見て、何だかとても腹立たしく感じていた。さっきまで道に迷ってしまって不安で不安で仕方なかったのに、カケルはちっとも不安を感じていなかった。それが妙に腹立たしかった。
しかし、安心したのもつかの間だった。さっきまで晴れていた空が、再び曇り空に変わり、山の高いところではもう雨が降り始めているようだった。目の前の川も、見る見るうちにまた水かさをましているのだった。

タグ:霊芝 ビワの実 ミズナラ
-母と子-5.滝 [アスカケ第1部 高千穂峰]
5.滝
一息つくと、二人は、来た時に渡った大岩を目指した。水かさの増してきた川を右手に見ながら、ようやく大岩の場所に辿りついたが、来た時よりも増した水に、大岩はわずかに頭が覗いている程度だった。
「だめだ、ここは渡れない。」
「どうする?」
「もう少し、上のほうへ行ってみよう。」
水かさが増えた川を渡るには、川下に行くよりも、上流に行けば流れも小さく、川幅も狭くなるのをカケルは知っていた。すでに二人とも来た事のない場所に足を踏み入れていた。
「大丈夫?」
イツキはまた不安がこみ上げてきて思わず訊ねてしまった。その様子をカケルは察した。
「大丈夫さ。前にとと様から聞いたことがある。神川の上のほうには、滝がある。その滝の後ろに人が通れる道があるって。・・昔の人が作った道らしい。だからそこまで行けばきっと向こう岸まで渡れるはずさ。」
カケルはわざとゆっくり落ちついた様子でそう言った。徐々に雨脚が強まってきた。イツキは、自分が思う以上に、体が冷え切って、体力を失い始めていた。足元が怪しくなり、カケルにすがりつかなければ歩けなくなりつつあった。
その頃、ナレの村では、村の周りを探したが二人の姿が見当たらず、やはり山へ探し手を出すべきかどうか、再度相談していた。
「ナギよ。この辺りには二人はおらんぞ。やはり、山へ入ったのだ。」
タカヒコがナギにそう言って、探し手を出すべきだと提案した。
「ああ、おそらく、山へ入って薬草を探しておるのだろう。・・・だが、この雨だ。探し手も危ない目にあうやもしれぬ。今しばらく様子を見よう。」
「だが・・カケルはいかに山に慣れておるとはいえ、まだ子どもだ。我らとて不安なのだ。二人はもっと不安を感じておるに違いないぞ。日暮れになれば、探す事もままならぬぞ。」
ナギは思案した。西の谷に降りたのなら、カケルには慣れた場所、どこかに身を休ませる場所もわかるだろう。だが、もし、御山へ登ったのなら、帰る道を見失っているかもしれない。どうすべきか悩んでいた。
そこへ、巫女セイが書物を抱えて現れた。
「二人はおそらく、西の谷にある、ぶなの森にいるのであろう。」
そう言って、書物を開いた。そこにはあの奇妙なキノコの絵が描かれていた。
「この絵のところに折り目がついておった。今まで開いた事のないところじゃ。きっと二人はこれを探すために西の谷に向かったはずじゃ。あそこにはぶなの森がある。」
「そう言えば、一度、森の入り口でそのキノコをイツキに問われた事があった。」
ナギは決断した。
「悪いが、俺と一緒に、西の谷へ行ってくれないか。」
タカヒコ他3人のミコトがナギに従った。
「日暮れまでに戻れないかも知れぬ。松明も必要になるだろう。万全の支度をして行こう。」
かなりの上流まで来たはずだが、カケルの言う大滝は見えなかった。神川にはいくつかの支流が流れ込んでいる。本流には確かに、カケルの言うような大滝があった。しかし、川が増水し、普段ならせせらぎ程度の流れも、今では渡れないほどの幅に広がっており、二人は川沿いを登る中で徐々に本流から離れているのであった。
「滝が見えたぞ!」
カケルが言うと、イツキも見上げた。しかし、それは小さな滝で、とても裏側に通り道などないものだった。むしろ、滝壺は深く、濁流に押し流された流木が突き出し、向こう岸に渡ることなど不可能であった。
「カケル・・・私、もう歩けない・・」
イツキがその場に座り込んでしまった。見ると、イツキは顔色が真っ白になっていてがたがたと震えている。これ以上は無理だとカケルにも判った。
その時だった。どこからか、鷹の鳴き声が響いた。カケルはじっと空を見上げると、旋回するように一羽の鷹が舞っている。
「ハヤテがいる。そうだ、ハヤテを使おう。」
カケルが指笛を鳴らすと、上空からハヤテは一気に下降し、滝壺の脇に生えている木の枝先に止まった。もう一度、短く指笛を鳴らすと、カケルの腕に止まった。タケルが仕込んだわけではないが、いつしか、ハヤテはタケルの指笛に応えるようになっていた。
「ハヤテ、村に知らせてくれ。」
そういうと、カケルは着衣の一部をちぎって、ハヤテの足に結び付けた。
「さあ、行け!父様にここを教えてくれ!」
ハヤテは、力強く羽ばたき、タケルの腕から上空へ舞い上がった。二度ほど旋回した後、村のほうへ向かって行った。
「頼んだぞ、ハヤテ!」

一息つくと、二人は、来た時に渡った大岩を目指した。水かさの増してきた川を右手に見ながら、ようやく大岩の場所に辿りついたが、来た時よりも増した水に、大岩はわずかに頭が覗いている程度だった。
「だめだ、ここは渡れない。」
「どうする?」
「もう少し、上のほうへ行ってみよう。」
水かさが増えた川を渡るには、川下に行くよりも、上流に行けば流れも小さく、川幅も狭くなるのをカケルは知っていた。すでに二人とも来た事のない場所に足を踏み入れていた。
「大丈夫?」
イツキはまた不安がこみ上げてきて思わず訊ねてしまった。その様子をカケルは察した。
「大丈夫さ。前にとと様から聞いたことがある。神川の上のほうには、滝がある。その滝の後ろに人が通れる道があるって。・・昔の人が作った道らしい。だからそこまで行けばきっと向こう岸まで渡れるはずさ。」
カケルはわざとゆっくり落ちついた様子でそう言った。徐々に雨脚が強まってきた。イツキは、自分が思う以上に、体が冷え切って、体力を失い始めていた。足元が怪しくなり、カケルにすがりつかなければ歩けなくなりつつあった。
その頃、ナレの村では、村の周りを探したが二人の姿が見当たらず、やはり山へ探し手を出すべきかどうか、再度相談していた。
「ナギよ。この辺りには二人はおらんぞ。やはり、山へ入ったのだ。」
タカヒコがナギにそう言って、探し手を出すべきだと提案した。
「ああ、おそらく、山へ入って薬草を探しておるのだろう。・・・だが、この雨だ。探し手も危ない目にあうやもしれぬ。今しばらく様子を見よう。」
「だが・・カケルはいかに山に慣れておるとはいえ、まだ子どもだ。我らとて不安なのだ。二人はもっと不安を感じておるに違いないぞ。日暮れになれば、探す事もままならぬぞ。」
ナギは思案した。西の谷に降りたのなら、カケルには慣れた場所、どこかに身を休ませる場所もわかるだろう。だが、もし、御山へ登ったのなら、帰る道を見失っているかもしれない。どうすべきか悩んでいた。
そこへ、巫女セイが書物を抱えて現れた。
「二人はおそらく、西の谷にある、ぶなの森にいるのであろう。」
そう言って、書物を開いた。そこにはあの奇妙なキノコの絵が描かれていた。
「この絵のところに折り目がついておった。今まで開いた事のないところじゃ。きっと二人はこれを探すために西の谷に向かったはずじゃ。あそこにはぶなの森がある。」
「そう言えば、一度、森の入り口でそのキノコをイツキに問われた事があった。」
ナギは決断した。
「悪いが、俺と一緒に、西の谷へ行ってくれないか。」
タカヒコ他3人のミコトがナギに従った。
「日暮れまでに戻れないかも知れぬ。松明も必要になるだろう。万全の支度をして行こう。」
かなりの上流まで来たはずだが、カケルの言う大滝は見えなかった。神川にはいくつかの支流が流れ込んでいる。本流には確かに、カケルの言うような大滝があった。しかし、川が増水し、普段ならせせらぎ程度の流れも、今では渡れないほどの幅に広がっており、二人は川沿いを登る中で徐々に本流から離れているのであった。
「滝が見えたぞ!」
カケルが言うと、イツキも見上げた。しかし、それは小さな滝で、とても裏側に通り道などないものだった。むしろ、滝壺は深く、濁流に押し流された流木が突き出し、向こう岸に渡ることなど不可能であった。
「カケル・・・私、もう歩けない・・」
イツキがその場に座り込んでしまった。見ると、イツキは顔色が真っ白になっていてがたがたと震えている。これ以上は無理だとカケルにも判った。
その時だった。どこからか、鷹の鳴き声が響いた。カケルはじっと空を見上げると、旋回するように一羽の鷹が舞っている。
「ハヤテがいる。そうだ、ハヤテを使おう。」
カケルが指笛を鳴らすと、上空からハヤテは一気に下降し、滝壺の脇に生えている木の枝先に止まった。もう一度、短く指笛を鳴らすと、カケルの腕に止まった。タケルが仕込んだわけではないが、いつしか、ハヤテはタケルの指笛に応えるようになっていた。
「ハヤテ、村に知らせてくれ。」
そういうと、カケルは着衣の一部をちぎって、ハヤテの足に結び付けた。
「さあ、行け!父様にここを教えてくれ!」
ハヤテは、力強く羽ばたき、タケルの腕から上空へ舞い上がった。二度ほど旋回した後、村のほうへ向かって行った。
「頼んだぞ、ハヤテ!」

-母と子-6.火起こし [アスカケ第1部 高千穂峰]
6.火起こし
ハヤテが飛び去ってから、カケルは、イツキを抱き起こし、滝の脇にあるくぼみまで連れて行った。ちょうど、張り出した岩のおかげで、雨に濡れずに済む場所だった。
「イツキ、ここで少し休もう。今、ハヤテを村にやった。きっと父様たちに知らせてくれる。ここで助けを待とう。」
イツキは、ぼんやりとした表情で頷いた。初夏とはいえ、日差しもなく、濡れた体のままでは更に冷え、体力を奪われる。カケルは、イツキをそこに残し、森の中に入っていった。
しばらくすると、カケルは、落ち木や葉をかき集めて戻った。雨に濡れた森の中でも、深い草の下には乾いた木や落ち葉はある。一抱えのそれらは、少しも濡れていなかった。
「イツキ、もう少し待ってろ。すぐに火を起こすからな。」
カケルはそういうと、乾いた木を、二本ほど、手にした。
腰につけた手刀を取り出し、太い木に切れ目をつけると、両足でしっかりと押さえ込んだ。そして、細い棒状の木を両手に挟むと力いっぱいに摺り合わせ始めた。父ナギから、火起こしの方法を叩き込まれていたカケルには、火を起こすことはそう難しい事ではなかった。
しばらくすると、うっすらと煙が上がり始めた。さらに擦り合わせるとはっきりとした糸のような煙の筋になった。そこに、よく揉んで粉状にした枯葉でそっと覆い、息を吹きかける。更に煙は大きく上がり、そのうちに、赤い火が見え始めた。息を吹きかけ、消えないように注意しながら、集めてきた落ち葉に移した。徐々に炎は大きくなった。
「ほら、焚き火の近くに来い。体を温めたほうがいい。」
そう言って、カケルはイツキを火の傍に来させた。冷え切っていた手足に炎の熱が命を与えてくれるようだった。
「もう少し、木を集めてくる。ここでじっとしてるんだぞ。」
カケルはそういうと、また森へ入っていった。焚き火の熱は、イツキの居るくぼみ全体を温かくしてくれる。イツキは疲れた体がじんわりと温まり、眠くなってしまった。
カケルが、再び、焚き火のあるくぼみに戻ると、イツキはすっかり眠ってしまっていた。
「ごめんな、イツキ。俺が、もっとしっかりしてれば・・・」
カケルは、そう言いながら、焚き火に木を入れると、自分の体を温めた。
ハヤテは一目散に村に向かっていた。村では、ナギたちが西の谷に向かう準備を整え、今にも出かけるところだった。ハヤテは急降下し、村の高楼の手すりに止まった。
「おお!ハヤテじゃ。・・おい、ナギ、ハヤテが来たぞ。」
村の長老が、高楼から声を掛ける。長老は、ハヤテに近づくと、足に結んである布を見つけた。
「・・お・・これは、カケルの服じゃな・・・お前、カケルとともに居たのか?」
ハヤテはピーっと鳴いて応え、羽ばたくしぐさをした。その様子を見て長老が、
「ナギ、きっとハヤテがカケル達の居場所を知っておる。案内してくれるじゃろう。」
ナギたちは、村の大門の前を今出ようとしていたが、そう聞いて、
「よし、ハヤテ!カケルのところへ案内してくれ。頼んだぞ!」
ハヤテは力強く羽ばたき舞い上がった。ナギたちは、行方を追うように西の谷へ向かった。
雨はいつの間にか上がったようだった。カケルも実際疲れていたのだろう、焚き火の傍でうつらうつらとしていた。雲の切れ間から、西に傾き始めた太陽の光が二人の居る窪みにも射し込んできた。少し眠った事で疲れも癒え、イツキも起き上がった。
「大丈夫か?」
「うん・・もう大丈夫。・・・晴れたね。」
そう言って見上げた空に、ハヤテの影が見えた。甲高い声で鳴き、カケルたちの居る窪みの上空を旋回している。
「きっと村に行ったはずだ。」
そう言って、カケルは立ち上がり、焚き火に落ち葉をたくさんかけた。少し湿った落ち葉からは、白い煙が大量に立ち上った。
「近くに、父様たちが来ているはずだ。こうやって狼煙をあげればきっと気づく。」
ナギたちは、一旦、西の谷の山桃の木のある淵へ向かった。だが、増水した川を見て、カケルたちは川上に迂回して対岸に渡ったはずだと判断し、川沿いを登っていった。西日に照らされ始めた頃、タカヒコが山影に上る狼煙の煙を見つけた。
「ナギよ!あれはきっとカケルの仕業だろう。」
そう言われ、ナギが空を見上げると、狼煙の煙の周りを、ハヤテが旋回しているのがわかった。
「あそこまで行ったのか。・・そうか、川を渡れずにいるのだな。よし、急ごう。日暮れまでには二人のところに行かねば。」
一行は、狼煙を頼りに上流を目指した。

ハヤテが飛び去ってから、カケルは、イツキを抱き起こし、滝の脇にあるくぼみまで連れて行った。ちょうど、張り出した岩のおかげで、雨に濡れずに済む場所だった。
「イツキ、ここで少し休もう。今、ハヤテを村にやった。きっと父様たちに知らせてくれる。ここで助けを待とう。」
イツキは、ぼんやりとした表情で頷いた。初夏とはいえ、日差しもなく、濡れた体のままでは更に冷え、体力を奪われる。カケルは、イツキをそこに残し、森の中に入っていった。
しばらくすると、カケルは、落ち木や葉をかき集めて戻った。雨に濡れた森の中でも、深い草の下には乾いた木や落ち葉はある。一抱えのそれらは、少しも濡れていなかった。
「イツキ、もう少し待ってろ。すぐに火を起こすからな。」
カケルはそういうと、乾いた木を、二本ほど、手にした。
腰につけた手刀を取り出し、太い木に切れ目をつけると、両足でしっかりと押さえ込んだ。そして、細い棒状の木を両手に挟むと力いっぱいに摺り合わせ始めた。父ナギから、火起こしの方法を叩き込まれていたカケルには、火を起こすことはそう難しい事ではなかった。
しばらくすると、うっすらと煙が上がり始めた。さらに擦り合わせるとはっきりとした糸のような煙の筋になった。そこに、よく揉んで粉状にした枯葉でそっと覆い、息を吹きかける。更に煙は大きく上がり、そのうちに、赤い火が見え始めた。息を吹きかけ、消えないように注意しながら、集めてきた落ち葉に移した。徐々に炎は大きくなった。
「ほら、焚き火の近くに来い。体を温めたほうがいい。」
そう言って、カケルはイツキを火の傍に来させた。冷え切っていた手足に炎の熱が命を与えてくれるようだった。
「もう少し、木を集めてくる。ここでじっとしてるんだぞ。」
カケルはそういうと、また森へ入っていった。焚き火の熱は、イツキの居るくぼみ全体を温かくしてくれる。イツキは疲れた体がじんわりと温まり、眠くなってしまった。
カケルが、再び、焚き火のあるくぼみに戻ると、イツキはすっかり眠ってしまっていた。
「ごめんな、イツキ。俺が、もっとしっかりしてれば・・・」
カケルは、そう言いながら、焚き火に木を入れると、自分の体を温めた。
ハヤテは一目散に村に向かっていた。村では、ナギたちが西の谷に向かう準備を整え、今にも出かけるところだった。ハヤテは急降下し、村の高楼の手すりに止まった。
「おお!ハヤテじゃ。・・おい、ナギ、ハヤテが来たぞ。」
村の長老が、高楼から声を掛ける。長老は、ハヤテに近づくと、足に結んである布を見つけた。
「・・お・・これは、カケルの服じゃな・・・お前、カケルとともに居たのか?」
ハヤテはピーっと鳴いて応え、羽ばたくしぐさをした。その様子を見て長老が、
「ナギ、きっとハヤテがカケル達の居場所を知っておる。案内してくれるじゃろう。」
ナギたちは、村の大門の前を今出ようとしていたが、そう聞いて、
「よし、ハヤテ!カケルのところへ案内してくれ。頼んだぞ!」
ハヤテは力強く羽ばたき舞い上がった。ナギたちは、行方を追うように西の谷へ向かった。
雨はいつの間にか上がったようだった。カケルも実際疲れていたのだろう、焚き火の傍でうつらうつらとしていた。雲の切れ間から、西に傾き始めた太陽の光が二人の居る窪みにも射し込んできた。少し眠った事で疲れも癒え、イツキも起き上がった。
「大丈夫か?」
「うん・・もう大丈夫。・・・晴れたね。」
そう言って見上げた空に、ハヤテの影が見えた。甲高い声で鳴き、カケルたちの居る窪みの上空を旋回している。
「きっと村に行ったはずだ。」
そう言って、カケルは立ち上がり、焚き火に落ち葉をたくさんかけた。少し湿った落ち葉からは、白い煙が大量に立ち上った。
「近くに、父様たちが来ているはずだ。こうやって狼煙をあげればきっと気づく。」
ナギたちは、一旦、西の谷の山桃の木のある淵へ向かった。だが、増水した川を見て、カケルたちは川上に迂回して対岸に渡ったはずだと判断し、川沿いを登っていった。西日に照らされ始めた頃、タカヒコが山影に上る狼煙の煙を見つけた。
「ナギよ!あれはきっとカケルの仕業だろう。」
そう言われ、ナギが空を見上げると、狼煙の煙の周りを、ハヤテが旋回しているのがわかった。
「あそこまで行ったのか。・・そうか、川を渡れずにいるのだな。よし、急ごう。日暮れまでには二人のところに行かねば。」
一行は、狼煙を頼りに上流を目指した。

-母と子‐7.無事の知らせ [アスカケ第1部 高千穂峰]
7.無事の知らせ
ナギたち一行が、二人のいる場所が見えるところまで到達する頃には、もう夕方近くになっていた。
普段なら通れる川岸の土手も、支流の流れが行く手を遮って、思うようには進めなかった。次第に、夕闇が辺りを包み始めていた。
カケルとイツキは、窪みの中で焚き火の火を見つめ、すでに、朝までここで過ごす覚悟を決めていた。
焚き火の横には寒さをしのぐためと火を絶やさないようにするために、カケルが森の中から集めた薪や落ち葉が積まれていた。
「イツキ、寒くないか?」
「うん・・大丈夫・・寒くない。」
初夏といっても、この山中では日が沈むと一気に気温が下がる。先ほどまでは狼煙を上げていたが、日が沈めば役に立たない。今は、漆黒の闇の中で、焚き火の灯りだけが二人の存在を知らせるものだった。
ふと顔をあげたイツキが、遠くの対岸に明かりのようなものを目にした。
「あれ?・・灯り?」
その声にカケルも、暗闇を凝視した。木々の間を確かに灯りが動いている。そして徐々に近づいてきているのが判った。カケルは、焚き火にさらに木を投げ込んで、炎を大きくした。そして、火のついた木を取り出して、「おーい!おおーい!」と叫びながら振った。近づく灯りもそれに応えるように動いた。じっと耳を済ませていると、周りの虫の音にかき消されながらも、かすかに人の声が聞こえた。
「父様たちだ!」
カケルは飛び跳ねるようにして、火のついた木を振り回して声を出した。徐々に、人影が暗闇に浮かんでくる。カケルたちの焚き火の灯りに照らされて、三人の男たちがこちらに向かって歩いてくるのだった。
「カケル!イツキ!無事か?」
声は、父ナギに間違いなかった。対岸まで到達したのだ。どう返事をすればよいのか、カケルは迷ったあげく、
「ごめんなさい!ごめんなさい!」
そう言って謝った。
「二人とも無事なんだな。」
その問いにはイツキが答えた。
「大丈夫。疲れちゃっただけ。でもカケルが守ってくれた。」
二人の声を聞いて、ナギたちはとりあえず安堵した。しかし、二人をどうやって、こちら側に渡らせるか困った。目の前の川は、相変わらずの濁流であり、何よりも滝つぼは真っ暗で深ささえわからなかった。松明の灯り程度では、もし水に落ち流されれば、探しようも無くなる。
「この宵闇ではむやみに動かない方が良い。」
ともに村を出たタカヒコが言った。もう一人の共、タツヒコも、
「朝まで待った方が良い。雨は上がっている。これ以上は水も増えないだろう。俺たちもむやみに動かない方がいいだろう。ここで朝を迎えよう。」
「そうか・・・そうだな。よし。」
そういうと、ナギはカケルに向かって叫んだ。
「朝まで待とう。俺たちもここに火を焚いて朝を待つ。」
「判った!・・なら、村へ無事を知らせよう。ハヤテに使いを頼む。」
カケルはそういうと、指笛を吹いた。どこにいたのか、ハヤテは羽音を響かせて闇夜から舞い降りた。カケルは、焚き火の炭を引き抜いて、持っていた麻袋に、大きく○を繋げて描いた。
「よし、これを村に届けてくれ。これで無事だと伝わるはずだ。行け!」
ハヤテは、軽く羽ばたき闇夜を飛んでいった。
滝をはさんで焚き火が二つ燃えている。皆、朝を待つために眠りについた。
夜を迎えたナレの村では、残った男たちや女たちが、高楼の下に集まっていた。
「もう見つけただろうか。」
「きっと無事だよな。」
そう呟く声が小さく響く。高楼の上には、長老と巫女が、灯りがみえはしないかと遠く西の谷の方を見つめていた。そこに、どこからとも無く、羽音が響いた。闇夜では鳥の姿など確認できない。それでも皆、羽音の先を見つめた。すると、ばさばさという音とともに、ハヤテが高楼の手すりにとまった。足には、麻袋をつけていた。長老がゆっくり麻袋を取り上げる。そして、そこに繋がった二つの○の絵を見つけた。長老は、それを見てすぐに言った。
「皆無事じゃ。探し手もカケルたちに会えたようじゃ。」
心配して高楼の下にいた村人は皆、安堵し喜んだ。
カケルが描いた絵は、猟の時に男たちが残す記号だった。獲物を会った時、その場所の木にしるしを残す。1頭のいのししなら△ひとつ。鹿なら□、人は○で記すのが、ナレの村の男たちの約束事になっていた。二つの○、二人の人が出会ったという意味だった。

ナギたち一行が、二人のいる場所が見えるところまで到達する頃には、もう夕方近くになっていた。
普段なら通れる川岸の土手も、支流の流れが行く手を遮って、思うようには進めなかった。次第に、夕闇が辺りを包み始めていた。
カケルとイツキは、窪みの中で焚き火の火を見つめ、すでに、朝までここで過ごす覚悟を決めていた。
焚き火の横には寒さをしのぐためと火を絶やさないようにするために、カケルが森の中から集めた薪や落ち葉が積まれていた。
「イツキ、寒くないか?」
「うん・・大丈夫・・寒くない。」
初夏といっても、この山中では日が沈むと一気に気温が下がる。先ほどまでは狼煙を上げていたが、日が沈めば役に立たない。今は、漆黒の闇の中で、焚き火の灯りだけが二人の存在を知らせるものだった。
ふと顔をあげたイツキが、遠くの対岸に明かりのようなものを目にした。
「あれ?・・灯り?」
その声にカケルも、暗闇を凝視した。木々の間を確かに灯りが動いている。そして徐々に近づいてきているのが判った。カケルは、焚き火にさらに木を投げ込んで、炎を大きくした。そして、火のついた木を取り出して、「おーい!おおーい!」と叫びながら振った。近づく灯りもそれに応えるように動いた。じっと耳を済ませていると、周りの虫の音にかき消されながらも、かすかに人の声が聞こえた。
「父様たちだ!」
カケルは飛び跳ねるようにして、火のついた木を振り回して声を出した。徐々に、人影が暗闇に浮かんでくる。カケルたちの焚き火の灯りに照らされて、三人の男たちがこちらに向かって歩いてくるのだった。
「カケル!イツキ!無事か?」
声は、父ナギに間違いなかった。対岸まで到達したのだ。どう返事をすればよいのか、カケルは迷ったあげく、
「ごめんなさい!ごめんなさい!」
そう言って謝った。
「二人とも無事なんだな。」
その問いにはイツキが答えた。
「大丈夫。疲れちゃっただけ。でもカケルが守ってくれた。」
二人の声を聞いて、ナギたちはとりあえず安堵した。しかし、二人をどうやって、こちら側に渡らせるか困った。目の前の川は、相変わらずの濁流であり、何よりも滝つぼは真っ暗で深ささえわからなかった。松明の灯り程度では、もし水に落ち流されれば、探しようも無くなる。
「この宵闇ではむやみに動かない方が良い。」
ともに村を出たタカヒコが言った。もう一人の共、タツヒコも、
「朝まで待った方が良い。雨は上がっている。これ以上は水も増えないだろう。俺たちもむやみに動かない方がいいだろう。ここで朝を迎えよう。」
「そうか・・・そうだな。よし。」
そういうと、ナギはカケルに向かって叫んだ。
「朝まで待とう。俺たちもここに火を焚いて朝を待つ。」
「判った!・・なら、村へ無事を知らせよう。ハヤテに使いを頼む。」
カケルはそういうと、指笛を吹いた。どこにいたのか、ハヤテは羽音を響かせて闇夜から舞い降りた。カケルは、焚き火の炭を引き抜いて、持っていた麻袋に、大きく○を繋げて描いた。
「よし、これを村に届けてくれ。これで無事だと伝わるはずだ。行け!」
ハヤテは、軽く羽ばたき闇夜を飛んでいった。
滝をはさんで焚き火が二つ燃えている。皆、朝を待つために眠りについた。
夜を迎えたナレの村では、残った男たちや女たちが、高楼の下に集まっていた。
「もう見つけただろうか。」
「きっと無事だよな。」
そう呟く声が小さく響く。高楼の上には、長老と巫女が、灯りがみえはしないかと遠く西の谷の方を見つめていた。そこに、どこからとも無く、羽音が響いた。闇夜では鳥の姿など確認できない。それでも皆、羽音の先を見つめた。すると、ばさばさという音とともに、ハヤテが高楼の手すりにとまった。足には、麻袋をつけていた。長老がゆっくり麻袋を取り上げる。そして、そこに繋がった二つの○の絵を見つけた。長老は、それを見てすぐに言った。
「皆無事じゃ。探し手もカケルたちに会えたようじゃ。」
心配して高楼の下にいた村人は皆、安堵し喜んだ。
カケルが描いた絵は、猟の時に男たちが残す記号だった。獲物を会った時、その場所の木にしるしを残す。1頭のいのししなら△ひとつ。鹿なら□、人は○で記すのが、ナレの村の男たちの約束事になっていた。二つの○、二人の人が出会ったという意味だった。

タグ:知らせ ハヤテ 安堵
-母と子-8.命綱 [アスカケ第1部 高千穂峰]
8.命綱
ナギたちの居る岸辺に朝日が射してきた。ナギが、カケルとイツキの居る窪みを見ると、二人はまだ眠っているようだった。周囲を見ると、まだ川の流れは強く、滝つぼもかなり広かった。とてもここを渡るのは不可能だと思われた。
タカヒコやタツヒコも起き出して、同じように周囲を見渡していた。タカヒコが、滝の上はどうかと、岩壁をよじ登る。しかし、滝の上までは到達できず、諦めて戻ってきた。
「ナギよ、もっと川下で渡れるところを探したほうが良いのではないか?」
「ああ、ここは無理だ。・・」
そうしているうちに、カケルとイツキも起きたようだった。
「二人とも大丈夫か!」
ナギの声に、カケルとイツキが手を振って応える。
「大丈夫。」
「カケル!ここを渡るのは無理だ。少し川下に戻るぞ。」
「ハイ!・・・少し、下に大岩が並んでいるところがある。そこなら渡れる。」
カケルとイツキ、ナギたちは川下に向かって移動した。カケルたちが昨日川を渡った大岩の場所に辿りついた。まだ、水の流れが強く、岩の上は見えているが、落ちれば命はない。
「父様!・・長縄はありますか?」
「ああ、ある。」
「それを渡して支えにして、この流れを渡る。」
「しかし・・縄をどうやって掛けるのだ?」
カケルは指笛を鳴らした。昨夜からカケルの傍にいたらしいハヤテが空から降りてきた。
「ハヤテに縄を持たせて、両岸にかける!」
「よし、判った。」
ハヤテは、カケルの言うとおり、ナギのいるところに飛び、足に縄を掴んでカケルのところに戻ってきた。縄の両端を、川岸の木にきつく結んだ。
「緩まぬよう、二重捲き結びにするのだぞ!」
カケルは、縄を編む練習とともに、縄の結び方を習っていた。太い縄は緩みやすい。二重巻き結びは、カケルが一番最初に覚えた結び方で、縄が多少揺れても解ける事はなかった。
「ナギよ。この縄を伝って渡るにはかなり力が要るぞ。まして、イツキを抱えては来れぬぞ。」
様子を見ながらタカヒコが問う。そして、タツヒコが、
「わしが行こう。力はある。イツキを背負って渡れぬ事もあるまい。」
どうしたものかと相談しているうちに、対岸ではカケルが縄を太いクヌギの木に縛り終えていた。
「イツキ、この縄を伝って向こう岸へ行くんだ。」
「でも・・怖いよ・・」
「大丈夫。ほら、こうやって・・」
カケルはそういうと、村を出るときに持ってきた縄を取り出し、端を輪にしてイツキの体に結んだ。そして、その縄を渡した長縄にかけ、もう一方の端を自分の体に同じように結んだ。
「こうすれば、縄が抜ける事もない。イツキが流されても俺が引っ張る。二人で、縄をしっかり握ってゆっくり行けば大丈夫さ。」
イツキはカケルの目をじっと見つめ、安心したように頷いた。
「父様!これから渡る。長縄が緩まぬよう見ておいて。」
「カケル!岩の後ろは深みがある。流れはきついが岩の前を来るのだぞ!ゆっくりで良い。」
二人はゆっくりと川の中に入った。思った以上に川は深かった。二人の肩ほどの深さがある。ゆっくりゆっくり進んだ。
大岩を二つほど進むと川の中ほどに達した。流れは一層強くなっていた。慎重に進んだが、急な深みにイツキが足を取られた。必死に縄にしがみつくが、もう体は流れに持っていかれている。腰の縄が締め付ける。カケルは足を踏ん張って流されまいと必死だった。ギリギリと縄が音を立てる。イツキが顔を水面に出し、必死にカケルに手を伸ばす。カケルも手を伸ばし、何とか掴んだ。右手一本で張り縄を掴み、左手でイツキの体を引き寄せ、岩に抱きつかせた。
対岸では、ナギたちが固唾を飲んで見つめていた。
「大丈夫か!もう少しだ。カケル!」
その声に、カケルは手を挙げて応えた。そして、
「イツキ、大丈夫か?」
イツキはこくりと頷く。
「一緒に行くぞ。さあ。」両手を広げ、次の岩を掴んで進んだ。3つ目の岩を過ぎると、もう楽に進めるようになった。何とか、対岸に辿りつくことができた。
ナギは二人を強く抱きとめ、涙を流した。
「二人とも、よく頑張った。偉かったなあ。」
タカヒコもタツヒコも涙していた。
「よし、戻るか。・・帰りはわしがおぶってやろう。」
タツヒコがイツキを、タカヒコがカケルを背負い、山道を戻って行った。
青空には、ハヤテがカケルの様子を見ているかのように、ゆっくりと旋回していた。

ナギたちの居る岸辺に朝日が射してきた。ナギが、カケルとイツキの居る窪みを見ると、二人はまだ眠っているようだった。周囲を見ると、まだ川の流れは強く、滝つぼもかなり広かった。とてもここを渡るのは不可能だと思われた。
タカヒコやタツヒコも起き出して、同じように周囲を見渡していた。タカヒコが、滝の上はどうかと、岩壁をよじ登る。しかし、滝の上までは到達できず、諦めて戻ってきた。
「ナギよ、もっと川下で渡れるところを探したほうが良いのではないか?」
「ああ、ここは無理だ。・・」
そうしているうちに、カケルとイツキも起きたようだった。
「二人とも大丈夫か!」
ナギの声に、カケルとイツキが手を振って応える。
「大丈夫。」
「カケル!ここを渡るのは無理だ。少し川下に戻るぞ。」
「ハイ!・・・少し、下に大岩が並んでいるところがある。そこなら渡れる。」
カケルとイツキ、ナギたちは川下に向かって移動した。カケルたちが昨日川を渡った大岩の場所に辿りついた。まだ、水の流れが強く、岩の上は見えているが、落ちれば命はない。
「父様!・・長縄はありますか?」
「ああ、ある。」
「それを渡して支えにして、この流れを渡る。」
「しかし・・縄をどうやって掛けるのだ?」
カケルは指笛を鳴らした。昨夜からカケルの傍にいたらしいハヤテが空から降りてきた。
「ハヤテに縄を持たせて、両岸にかける!」
「よし、判った。」
ハヤテは、カケルの言うとおり、ナギのいるところに飛び、足に縄を掴んでカケルのところに戻ってきた。縄の両端を、川岸の木にきつく結んだ。
「緩まぬよう、二重捲き結びにするのだぞ!」
カケルは、縄を編む練習とともに、縄の結び方を習っていた。太い縄は緩みやすい。二重巻き結びは、カケルが一番最初に覚えた結び方で、縄が多少揺れても解ける事はなかった。
「ナギよ。この縄を伝って渡るにはかなり力が要るぞ。まして、イツキを抱えては来れぬぞ。」
様子を見ながらタカヒコが問う。そして、タツヒコが、
「わしが行こう。力はある。イツキを背負って渡れぬ事もあるまい。」
どうしたものかと相談しているうちに、対岸ではカケルが縄を太いクヌギの木に縛り終えていた。
「イツキ、この縄を伝って向こう岸へ行くんだ。」
「でも・・怖いよ・・」
「大丈夫。ほら、こうやって・・」
カケルはそういうと、村を出るときに持ってきた縄を取り出し、端を輪にしてイツキの体に結んだ。そして、その縄を渡した長縄にかけ、もう一方の端を自分の体に同じように結んだ。
「こうすれば、縄が抜ける事もない。イツキが流されても俺が引っ張る。二人で、縄をしっかり握ってゆっくり行けば大丈夫さ。」
イツキはカケルの目をじっと見つめ、安心したように頷いた。
「父様!これから渡る。長縄が緩まぬよう見ておいて。」
「カケル!岩の後ろは深みがある。流れはきついが岩の前を来るのだぞ!ゆっくりで良い。」
二人はゆっくりと川の中に入った。思った以上に川は深かった。二人の肩ほどの深さがある。ゆっくりゆっくり進んだ。
大岩を二つほど進むと川の中ほどに達した。流れは一層強くなっていた。慎重に進んだが、急な深みにイツキが足を取られた。必死に縄にしがみつくが、もう体は流れに持っていかれている。腰の縄が締め付ける。カケルは足を踏ん張って流されまいと必死だった。ギリギリと縄が音を立てる。イツキが顔を水面に出し、必死にカケルに手を伸ばす。カケルも手を伸ばし、何とか掴んだ。右手一本で張り縄を掴み、左手でイツキの体を引き寄せ、岩に抱きつかせた。
対岸では、ナギたちが固唾を飲んで見つめていた。
「大丈夫か!もう少しだ。カケル!」
その声に、カケルは手を挙げて応えた。そして、
「イツキ、大丈夫か?」
イツキはこくりと頷く。
「一緒に行くぞ。さあ。」両手を広げ、次の岩を掴んで進んだ。3つ目の岩を過ぎると、もう楽に進めるようになった。何とか、対岸に辿りつくことができた。
ナギは二人を強く抱きとめ、涙を流した。
「二人とも、よく頑張った。偉かったなあ。」
タカヒコもタツヒコも涙していた。
「よし、戻るか。・・帰りはわしがおぶってやろう。」
タツヒコがイツキを、タカヒコがカケルを背負い、山道を戻って行った。
青空には、ハヤテがカケルの様子を見ているかのように、ゆっくりと旋回していた。

タグ:命綱 沢 岩場 川渡り
-母と子-9.母の薬 [アスカケ第1部 高千穂峰]
9.母の薬
カケルたちを連れて、男たちが村に戻った。村の皆は昨夜のハヤテの便りに一応安堵していたものの、やはり顔を見るまでは不安で、大門の前でじっと待っていた。高楼から様子を伺っていた長老が、男たちの帰りを知らせると、歓喜した。
カケルたちが、大門にたどり着くと、長老と巫女がカケルとイツキの前に立った。
「カケル、イツキ、勝手に村の外に出るとは・・掟破りじゃ。皆、どれだけ心配したか。」長老が、優しくも厳しい声で言った。
「ごめんなさい。」二人は声を揃えて謝った。
「掟破りには罰を与えねばならぬ。」
カケルはどんな罰でも受ける覚悟はできていた。
「カケルは、一月の間、魚とりに励み、皆の食い物を獲ってくるのじゃ。・・ハヤテの餌もな。・・イツキは、カケルの取る魚を使って料理し、皆に配るのじゃ。・・ナミの口にも良いよう工夫して食べさせるのじゃ。良いか。」
二人はいつもの仕事を一生懸命にやる事が罰だと言われ、少し驚いた。長老はそういうとにやりと笑って高楼に戻っていった。
「さあ、昨夜は疲れたであろう。少し休むが良い。・・休んだら、後で館に来るのじゃ。お前たちに話すべきことがある。」
巫女セイも、二人の元気そうな姿に安堵して、労わるようにそう言って館に戻っていった。
カケルとイツキは、家に戻った。二人が家に入ると、ナミは寝床から起き、何も言わず二人を抱きしめた。そこに、ナギが干草を抱えて部屋に入ってきた。
「二人とも、昨夜は岩の上にいて辛かっただろう。さあ、寝床を作るから少し休め。」
いつもより覆いふかふかの干草の寝床に二人は横になった。カケルは、村に戻るまで気を張っていたので、柔らかな干草の寝床に横になるとすぐに眠ってしまった。イツキも、カケルに寄り添うように横になり眠った。
二人が目を覚ましたのは昼を過ぎていた。ナギが用意した食事を済ませて、館に向かった。
館では、巫女セイと数人の女たちがが待っていた。
「・・来たか・・」
二人が館に入ると、巫女の前に、二人が取ってきたキノコが広げてあった。
「これは昨夜、カケルが無事を知らせた麻袋の中に入っていたものじゃ。・・すぐに、書物と照らして調べた。」
「それで・・それは母様の薬になるのですか?」
イツキが不安げに訊いた。
「うむ・・よくよく調べた。これは、霊芝というキノコじゃ。書物によると、痛みを沈め、体の毒を出し、滋養を与えるとある。きっと、ナミの体を直してくれるはずじゃ。」
「じゃあ・・母様は元気になる?」
カケルが訊いた。
「すぐには無理じゃ。しばらくこれを煎じて飲み続ける事が大事じゃ。毎日少しずつな。」
「わかりました。私が、母様の食事とともに飲んでいただくようにします。」
「ああ。それがええ。・・それと、母様だけではなく、他の体の弱っている者にも飲ませるとしよう。ワシも飲んだほうが良さそうじゃ。」
「じゃあ、これだけじゃ足りないね。」
カケルが訊く。
「ああ。書物によると、このキノコが採れる場所は限られておるようじゃ。お前たちが見つけた場所は大切にせねばならぬ。・・・今度、天気が戻り、神川が静かな時、村の者と一緒に行くのじゃ。むやみに取ってはならぬ。必要なだけ採り、薬として館に置くことにしよう。カケルよ。良いか。しばらくはお前があの森の守り主になるのじゃ。」
「はい。・・西の川は漁場。森を守ることは川を守ることと父様から教わりました。木も草も、魚もみなつながっておると・・しっかり守ります。」
カケルは神妙な顔つきで巫女の言いつけに答えた。
傍にいた、ハルとスズが、イツキに薬の作り方を教えると言い、イツキを連れて行った。
館には、カケルと巫女セイが残った。
「カケルよ。お前、この書物が読めるのか?」
カケルは、母に文字を教わり、全てではないが書かれていることの意味はわかると答えた。
「それならば・・」
巫女はそういうと、祭壇の下にある他の書物も出して見せた。そして、
「ここにある書物は、いにしえに我が一族がはるか大陸から持ち出したもの。我が村の宝じゃ。この中にはまだこの国には知られていない多くの知恵が詰まっておる。・・お前もいずれはアスカケに出るであろう。それまでにこの書物をすべて読むのじゃ。きっとお前の役に立つはずじゃ。いや・・アスカケに出ずとも、この村を守る力になる。」
「でも・・それは巫女様のお役では・・」
「ワシもそう長くはない。他にも文字を覚えたものはおるが、これからは多くのものが知る事が大事じゃ。子どものお前なら、覚えも早かろう。良いな。」

カケルたちを連れて、男たちが村に戻った。村の皆は昨夜のハヤテの便りに一応安堵していたものの、やはり顔を見るまでは不安で、大門の前でじっと待っていた。高楼から様子を伺っていた長老が、男たちの帰りを知らせると、歓喜した。
カケルたちが、大門にたどり着くと、長老と巫女がカケルとイツキの前に立った。
「カケル、イツキ、勝手に村の外に出るとは・・掟破りじゃ。皆、どれだけ心配したか。」長老が、優しくも厳しい声で言った。
「ごめんなさい。」二人は声を揃えて謝った。
「掟破りには罰を与えねばならぬ。」
カケルはどんな罰でも受ける覚悟はできていた。
「カケルは、一月の間、魚とりに励み、皆の食い物を獲ってくるのじゃ。・・ハヤテの餌もな。・・イツキは、カケルの取る魚を使って料理し、皆に配るのじゃ。・・ナミの口にも良いよう工夫して食べさせるのじゃ。良いか。」
二人はいつもの仕事を一生懸命にやる事が罰だと言われ、少し驚いた。長老はそういうとにやりと笑って高楼に戻っていった。
「さあ、昨夜は疲れたであろう。少し休むが良い。・・休んだら、後で館に来るのじゃ。お前たちに話すべきことがある。」
巫女セイも、二人の元気そうな姿に安堵して、労わるようにそう言って館に戻っていった。
カケルとイツキは、家に戻った。二人が家に入ると、ナミは寝床から起き、何も言わず二人を抱きしめた。そこに、ナギが干草を抱えて部屋に入ってきた。
「二人とも、昨夜は岩の上にいて辛かっただろう。さあ、寝床を作るから少し休め。」
いつもより覆いふかふかの干草の寝床に二人は横になった。カケルは、村に戻るまで気を張っていたので、柔らかな干草の寝床に横になるとすぐに眠ってしまった。イツキも、カケルに寄り添うように横になり眠った。
二人が目を覚ましたのは昼を過ぎていた。ナギが用意した食事を済ませて、館に向かった。
館では、巫女セイと数人の女たちがが待っていた。
「・・来たか・・」
二人が館に入ると、巫女の前に、二人が取ってきたキノコが広げてあった。
「これは昨夜、カケルが無事を知らせた麻袋の中に入っていたものじゃ。・・すぐに、書物と照らして調べた。」
「それで・・それは母様の薬になるのですか?」
イツキが不安げに訊いた。
「うむ・・よくよく調べた。これは、霊芝というキノコじゃ。書物によると、痛みを沈め、体の毒を出し、滋養を与えるとある。きっと、ナミの体を直してくれるはずじゃ。」
「じゃあ・・母様は元気になる?」
カケルが訊いた。
「すぐには無理じゃ。しばらくこれを煎じて飲み続ける事が大事じゃ。毎日少しずつな。」
「わかりました。私が、母様の食事とともに飲んでいただくようにします。」
「ああ。それがええ。・・それと、母様だけではなく、他の体の弱っている者にも飲ませるとしよう。ワシも飲んだほうが良さそうじゃ。」
「じゃあ、これだけじゃ足りないね。」
カケルが訊く。
「ああ。書物によると、このキノコが採れる場所は限られておるようじゃ。お前たちが見つけた場所は大切にせねばならぬ。・・・今度、天気が戻り、神川が静かな時、村の者と一緒に行くのじゃ。むやみに取ってはならぬ。必要なだけ採り、薬として館に置くことにしよう。カケルよ。良いか。しばらくはお前があの森の守り主になるのじゃ。」
「はい。・・西の川は漁場。森を守ることは川を守ることと父様から教わりました。木も草も、魚もみなつながっておると・・しっかり守ります。」
カケルは神妙な顔つきで巫女の言いつけに答えた。
傍にいた、ハルとスズが、イツキに薬の作り方を教えると言い、イツキを連れて行った。
館には、カケルと巫女セイが残った。
「カケルよ。お前、この書物が読めるのか?」
カケルは、母に文字を教わり、全てではないが書かれていることの意味はわかると答えた。
「それならば・・」
巫女はそういうと、祭壇の下にある他の書物も出して見せた。そして、
「ここにある書物は、いにしえに我が一族がはるか大陸から持ち出したもの。我が村の宝じゃ。この中にはまだこの国には知られていない多くの知恵が詰まっておる。・・お前もいずれはアスカケに出るであろう。それまでにこの書物をすべて読むのじゃ。きっとお前の役に立つはずじゃ。いや・・アスカケに出ずとも、この村を守る力になる。」
「でも・・それは巫女様のお役では・・」
「ワシもそう長くはない。他にも文字を覚えたものはおるが、これからは多くのものが知る事が大事じゃ。子どものお前なら、覚えも早かろう。良いな。」

-母と子-10.団欒 [アスカケ第1部 高千穂峰]
10.団欒
カケルとイツキが持ち帰った薬の効果か、ひと月ほどでナミは動けるほどに回復した。それは、村の皆が驚くほどであったが、何より一番驚いているのは、カケルとイツキだった。
ある朝、イツキが目覚めると、ナミが竃の前で朝餉の支度をしていた。
「母様、起きても良いの?」
「ああ・・今日は随分加減がいいの。今、朝餉にするからね。昨日、カケルが採って来たヤマメがあるから・・」
「私も手伝う!」
イツキは、ナミが元気になったのを見て嬉しくて、朝餉の支度の手伝いと言いながら、ほとんどナミの周りでじゃれているようであった。
ナギとカケルもようやく起き出してきて、四人で朝餉となった。
「今日は随分楽なのよ。ねえ、久しぶりに外に出たいわ。」
「そうか・・まだ、遠くは無理だが・・・・そこの畑くらいなら行けるだろう。よし、ちょうど、山芋をとる頃だ。むかごも取れるだろう。一緒に行こう。」
ナギはナミの体を心配しつつも、久しぶりに外に出たいというナミの願いを聞き入れた。
イツキは、巫女に言われたように、ナミの薬を煎じて差し出し、ナミもすっと飲み干した。毎日の日課のようになっていた。
朝餉の片づけをしている時、ナギは表に出て背負子を出していた。カケルはそれを見て、
「どうするの?」
「ああ、かか様が疲れるといけないからな。背負子で畑まで行く。」
最初、ナミは自分で歩けるといったが、疲れてまた寝込んでしまうとカケルやイツキが心配するからと説得した。
「よし、行くぞ。」
そう言って、背負子を背負い立ち上がったナギは驚いた。ナミの体が思ったよりも軽かったからだ。見た目には、元気にしているが、やはり病気で体は随分痩せ細ってしまっていたのだ。
「・・カケル・・鍬と籠を持って来い。イツキ、竹筒に水を汲んでくるのだ。行くぞ。」
そう言うと、すたすたと歩き始めた。
畑まではすぐだった。畑の回りには、毎年芽が出て、夏には山のように蔓が茂っていた畑も、秋になり少しずつ葉が落ちかけていた。葉の付け根には、大きなむかごが実をつけていた。カケルとイツキは、籠をもってむかご採りに夢中だった。むかごは、蒸かすと甘くて美味しい。
「そろそろ、芋を掘り始めよう。」
ナギが立ち上がり、むかごのなっていた芋の蔓の根元を丁寧に吟味して、一番太そうなものを選んだ。そして、根元を少し残して蔓を切った。
「さあ、カケル。まずは周りを掘るぞ。」
そう言って持ってきた鍬で周りを掘り始める。
「きっとこいつは大きいはずだ。周りをしっかり掘るんだ。カケルも土を脇へ掻き出し徐々に掘り進めた。
「カケル、穴の中へ入って掘りあげるぞ。ほら。」
カケルが穴の中に身を入れてさらに掘る。山芋の形が徐々に姿を見え始めた。
「先のほうは細くなって折れやすいから気をつけろ。」
カケルは慎重に掘った。ついに、一番先までたどり着き、ゆっくりと引き上げた。
「思ったとおり随分大きい。これなら、うちで食べても余る。そうだ、赤子を産んだばかりのトモにも半分分けてやろう。」
秋の穏やかな陽の中で、ナギもカケルも泥だらけの顔で笑った。そして、傍で二人を見つめるナミも微笑んでいた。イツキはそうした風景を見ながら、顔さえ良く覚えていない父や母の事を想い出していた。
しばらく休んだ後、ナギが、
「ナミが少し疲れたようだ。家に戻るぞ。お前たちはどうする?」
「西の谷へ行く。・・今日もみなの食べ物を取る約束だから・・」
「私も行く。薬のレイシがもう少なくなったって巫女様が言ってたから。」
「そうか・・このごろは日暮れも早くなった。遅くならぬうちに戻るのだぞ。」
そう言うと、来た時と同じようにナミを背負子に座らせ戻る事にした。
家までの戻り道、背負子に座ったナミが、呟くように言った。
「二人とも、良い子に育った・・。カケルは人一倍元気で、あなたに似て力もある。きっと、すばらしいミコトになってくれる。イツキももう一人前。食事の支度も私の介抱もしっかりできる。・・本当に良い子に育ってくれた。」
ナミの呟きを、背中で聞きながら、ナギは、「ああ」とだけ答えた。
ナギには、ナミの言葉が、ただ安堵したという意味ではなく、「いつ自分が死んでも大丈夫ね」と、まるで別れの言葉に聞こえてしまい、涙をこぼしそうになっていたからだった。
ナミの体が、どんどん軽くなって、そのうちに、ふっと消えて見えなくなるんじゃないかという不安が胸をふさぐようで辛かった。

カケルとイツキが持ち帰った薬の効果か、ひと月ほどでナミは動けるほどに回復した。それは、村の皆が驚くほどであったが、何より一番驚いているのは、カケルとイツキだった。
ある朝、イツキが目覚めると、ナミが竃の前で朝餉の支度をしていた。
「母様、起きても良いの?」
「ああ・・今日は随分加減がいいの。今、朝餉にするからね。昨日、カケルが採って来たヤマメがあるから・・」
「私も手伝う!」
イツキは、ナミが元気になったのを見て嬉しくて、朝餉の支度の手伝いと言いながら、ほとんどナミの周りでじゃれているようであった。
ナギとカケルもようやく起き出してきて、四人で朝餉となった。
「今日は随分楽なのよ。ねえ、久しぶりに外に出たいわ。」
「そうか・・まだ、遠くは無理だが・・・・そこの畑くらいなら行けるだろう。よし、ちょうど、山芋をとる頃だ。むかごも取れるだろう。一緒に行こう。」
ナギはナミの体を心配しつつも、久しぶりに外に出たいというナミの願いを聞き入れた。
イツキは、巫女に言われたように、ナミの薬を煎じて差し出し、ナミもすっと飲み干した。毎日の日課のようになっていた。
朝餉の片づけをしている時、ナギは表に出て背負子を出していた。カケルはそれを見て、
「どうするの?」
「ああ、かか様が疲れるといけないからな。背負子で畑まで行く。」
最初、ナミは自分で歩けるといったが、疲れてまた寝込んでしまうとカケルやイツキが心配するからと説得した。
「よし、行くぞ。」
そう言って、背負子を背負い立ち上がったナギは驚いた。ナミの体が思ったよりも軽かったからだ。見た目には、元気にしているが、やはり病気で体は随分痩せ細ってしまっていたのだ。
「・・カケル・・鍬と籠を持って来い。イツキ、竹筒に水を汲んでくるのだ。行くぞ。」
そう言うと、すたすたと歩き始めた。
畑まではすぐだった。畑の回りには、毎年芽が出て、夏には山のように蔓が茂っていた畑も、秋になり少しずつ葉が落ちかけていた。葉の付け根には、大きなむかごが実をつけていた。カケルとイツキは、籠をもってむかご採りに夢中だった。むかごは、蒸かすと甘くて美味しい。
「そろそろ、芋を掘り始めよう。」
ナギが立ち上がり、むかごのなっていた芋の蔓の根元を丁寧に吟味して、一番太そうなものを選んだ。そして、根元を少し残して蔓を切った。
「さあ、カケル。まずは周りを掘るぞ。」
そう言って持ってきた鍬で周りを掘り始める。
「きっとこいつは大きいはずだ。周りをしっかり掘るんだ。カケルも土を脇へ掻き出し徐々に掘り進めた。
「カケル、穴の中へ入って掘りあげるぞ。ほら。」
カケルが穴の中に身を入れてさらに掘る。山芋の形が徐々に姿を見え始めた。
「先のほうは細くなって折れやすいから気をつけろ。」
カケルは慎重に掘った。ついに、一番先までたどり着き、ゆっくりと引き上げた。
「思ったとおり随分大きい。これなら、うちで食べても余る。そうだ、赤子を産んだばかりのトモにも半分分けてやろう。」
秋の穏やかな陽の中で、ナギもカケルも泥だらけの顔で笑った。そして、傍で二人を見つめるナミも微笑んでいた。イツキはそうした風景を見ながら、顔さえ良く覚えていない父や母の事を想い出していた。
しばらく休んだ後、ナギが、
「ナミが少し疲れたようだ。家に戻るぞ。お前たちはどうする?」
「西の谷へ行く。・・今日もみなの食べ物を取る約束だから・・」
「私も行く。薬のレイシがもう少なくなったって巫女様が言ってたから。」
「そうか・・このごろは日暮れも早くなった。遅くならぬうちに戻るのだぞ。」
そう言うと、来た時と同じようにナミを背負子に座らせ戻る事にした。
家までの戻り道、背負子に座ったナミが、呟くように言った。
「二人とも、良い子に育った・・。カケルは人一倍元気で、あなたに似て力もある。きっと、すばらしいミコトになってくれる。イツキももう一人前。食事の支度も私の介抱もしっかりできる。・・本当に良い子に育ってくれた。」
ナミの呟きを、背中で聞きながら、ナギは、「ああ」とだけ答えた。
ナギには、ナミの言葉が、ただ安堵したという意味ではなく、「いつ自分が死んでも大丈夫ね」と、まるで別れの言葉に聞こえてしまい、涙をこぼしそうになっていたからだった。
ナミの体が、どんどん軽くなって、そのうちに、ふっと消えて見えなくなるんじゃないかという不安が胸をふさぐようで辛かった。
-帰還‐1.先人たちの遺産 [アスカケ第1部 高千穂峰]
1.先人たちの遺産
カケルは11歳を迎えた。
ナミが薬湯を飲み始めて1年、病は一進一退を繰り返していた。冬の寒さは、家の中で暖を取れば耐えられるが、夏の暑さは体力の落ちたナミには辛かった。食欲もなくなり、痩せた体がさらに絞られるように思えた。村の者は、ナミが少しでも食べられるものを、少しでも栄養のあるものをと、相談し、協力し、用意した。
カケルは、漁の合間の時間を使って、巫女の言いつけどおり、館にある古い書物を丁寧に読み、特に、薬草については村の誰よりも詳しくなっていた。漁に行くと、近くの森や川の岸辺で、薬草と思われるものを摘んできては書物と照らし合わせ試していた。ナミの病に良いと考えられるものは、イツキと相談し、ナミの了解を得て、服用させていた。その甲斐もあってか、夏を何とか乗り切る事ができた。涼しくなる頃には、ナミは食欲が戻り、痩せ細っていた体も徐々に戻り、また、動けるようになっていた。
ある日、カケルは館で書物を読んでいた時、棚の一番奥に、小さな巻物を見つけた。表書きも何もなく、封印がされていた。かなり古いものであると同時に、その巻物は、薄く織った布で作られた他の書物とは明らかに違う材質であった。丁寧に結ばれた紐を解くと、中には絵図が描かれていて、さらに広げると、ナレの村周辺の地図のようだった。すぐに、巫女セイの許へ向かった。セイは高楼で長老と話をしていた。
「セイ様!お教え下さい。」
息を切らし、高楼に登ってきたカケルに二人は驚いた。
「セイ様、これは何でしょう?」
答えたのは、長老だった。
「これは・・先人が残してくれた知恵じゃ。・・カケルも知っておるだろうが・・我が一族は、遥か大陸より渡来した。・・まだこの地にはない多くの知恵を持っていた。・・お前が持っている巻物も、紙というものでできておる。」
カケルは、長老の言葉に驚きを隠せなかった。
「紙?」
この時代、まだ倭国には文字もなく、紙を必要とはしていなかったため、それを作る技術も渡来していなかった。紙は大和朝廷以降、渡来人からもたらされたと考えられている。
「先人たちは、この地で生きるために、一族に伝わる大陸の知恵のいくつかを封印したのだ。さもなくば、周囲の村と争いが起きる。・・そればかりか・・大陸から大軍で我らを滅ぼしに来るやも知れぬと先人たちは考えたのだ。だが、いつの日か、我が一族が必要とする日が来る。その時まで封印したのだ。・・・お前がナミの病を治す為に用いた薬湯も、そのひとつだった。」
「長様(おささま)は、それを知っているのですか?」
「いや・・封印されて長い年月が経った。もはや、どういうものかは判らぬものばかりだ。・・ただ、そこに書かれているのは、もっともっと重い事だと伝わっておる。・・命やこの地そのものを失う事が書かれておるとな。」
長老の顔は厳しかった。
長い年月、封印された一族の存続に関わるものをカケルは開けてしまったのだ。畏れを抱き、戸惑った。その様子を察して、セイが言葉を発した。
「・・カケルよ。知恵というものは使い方しだいなのじゃ。ナミの薬湯も、量を誤れば死に至る。薬草の中には毒気の強いものもある。お前は強い子じゃ。・・いや、お前がそれを見つけたのもきっと運命(さだめ)じゃろう。・・・良いか、カケル。その中に書かれていることをしっかり読み解くのじゃ。そして、それをどう使うべきかを考えよ。」
カケルは声が出なかった。長老と巫女の瞳の奥に、憂いと惧れと望みとを感じ、自らの運命(さだめ)と言われ、すぐには受け止める事ができなかった。
カケルは巻物を懐に仕舞い、館に戻った。そして一旦、巻物を元の場所に戻し、急いで家に戻ると、干草の寝床にうつ伏せになり、眼を閉じ、じっと考え込んだ。少しだけ見た、あの絵地図を思い出していた。
所々に、印がついていた。西の谷にも、そして高千穂の峰に登る山道にも同じような印があった。・・他には何が書かれているのだろう。・・母の命を救える他の方法も書かれているのだろうか・・いろんな思いが頭を巡りながらも、カケルは徐々にまどろみの中に落ちていった。
翌朝、まだ陽が登る前に、カケルは館に行った。昨日見つけた巻物をもう一度開き、そこに書かれている地図と印を頭に叩き込んだ。そこに巫女セイが現れた。
「カケルよ、どうするのじゃ?」
「セイ様。災いになるか、救いになるか、わかりません。でも、これを見たもののさだめなら、最後までやってみます。」
セイを見たカケルの目には覚悟が感じられた。
「よかろう。・・・ミコト達にはワシが話しておく。」
カケルは、地図の印の着いた場所に向かうことにした。
ひとつは、館の裏手の斜面あたりだった。獣除けの柵と堀の間に、小さな門があったが、ずっと閉じられたままであったため、蔦が絡みつき、そこにあることもわからないようになっていた。カケルはその門をそっと開くと、村の裏手に出た。雑草と低木が茂り、その先には竹やぶも広がっている。カケルは少しずつ周囲を探りながら、深く分け入った。

カケルは11歳を迎えた。
ナミが薬湯を飲み始めて1年、病は一進一退を繰り返していた。冬の寒さは、家の中で暖を取れば耐えられるが、夏の暑さは体力の落ちたナミには辛かった。食欲もなくなり、痩せた体がさらに絞られるように思えた。村の者は、ナミが少しでも食べられるものを、少しでも栄養のあるものをと、相談し、協力し、用意した。
カケルは、漁の合間の時間を使って、巫女の言いつけどおり、館にある古い書物を丁寧に読み、特に、薬草については村の誰よりも詳しくなっていた。漁に行くと、近くの森や川の岸辺で、薬草と思われるものを摘んできては書物と照らし合わせ試していた。ナミの病に良いと考えられるものは、イツキと相談し、ナミの了解を得て、服用させていた。その甲斐もあってか、夏を何とか乗り切る事ができた。涼しくなる頃には、ナミは食欲が戻り、痩せ細っていた体も徐々に戻り、また、動けるようになっていた。
ある日、カケルは館で書物を読んでいた時、棚の一番奥に、小さな巻物を見つけた。表書きも何もなく、封印がされていた。かなり古いものであると同時に、その巻物は、薄く織った布で作られた他の書物とは明らかに違う材質であった。丁寧に結ばれた紐を解くと、中には絵図が描かれていて、さらに広げると、ナレの村周辺の地図のようだった。すぐに、巫女セイの許へ向かった。セイは高楼で長老と話をしていた。
「セイ様!お教え下さい。」
息を切らし、高楼に登ってきたカケルに二人は驚いた。
「セイ様、これは何でしょう?」
答えたのは、長老だった。
「これは・・先人が残してくれた知恵じゃ。・・カケルも知っておるだろうが・・我が一族は、遥か大陸より渡来した。・・まだこの地にはない多くの知恵を持っていた。・・お前が持っている巻物も、紙というものでできておる。」
カケルは、長老の言葉に驚きを隠せなかった。
「紙?」
この時代、まだ倭国には文字もなく、紙を必要とはしていなかったため、それを作る技術も渡来していなかった。紙は大和朝廷以降、渡来人からもたらされたと考えられている。
「先人たちは、この地で生きるために、一族に伝わる大陸の知恵のいくつかを封印したのだ。さもなくば、周囲の村と争いが起きる。・・そればかりか・・大陸から大軍で我らを滅ぼしに来るやも知れぬと先人たちは考えたのだ。だが、いつの日か、我が一族が必要とする日が来る。その時まで封印したのだ。・・・お前がナミの病を治す為に用いた薬湯も、そのひとつだった。」
「長様(おささま)は、それを知っているのですか?」
「いや・・封印されて長い年月が経った。もはや、どういうものかは判らぬものばかりだ。・・ただ、そこに書かれているのは、もっともっと重い事だと伝わっておる。・・命やこの地そのものを失う事が書かれておるとな。」
長老の顔は厳しかった。
長い年月、封印された一族の存続に関わるものをカケルは開けてしまったのだ。畏れを抱き、戸惑った。その様子を察して、セイが言葉を発した。
「・・カケルよ。知恵というものは使い方しだいなのじゃ。ナミの薬湯も、量を誤れば死に至る。薬草の中には毒気の強いものもある。お前は強い子じゃ。・・いや、お前がそれを見つけたのもきっと運命(さだめ)じゃろう。・・・良いか、カケル。その中に書かれていることをしっかり読み解くのじゃ。そして、それをどう使うべきかを考えよ。」
カケルは声が出なかった。長老と巫女の瞳の奥に、憂いと惧れと望みとを感じ、自らの運命(さだめ)と言われ、すぐには受け止める事ができなかった。
カケルは巻物を懐に仕舞い、館に戻った。そして一旦、巻物を元の場所に戻し、急いで家に戻ると、干草の寝床にうつ伏せになり、眼を閉じ、じっと考え込んだ。少しだけ見た、あの絵地図を思い出していた。
所々に、印がついていた。西の谷にも、そして高千穂の峰に登る山道にも同じような印があった。・・他には何が書かれているのだろう。・・母の命を救える他の方法も書かれているのだろうか・・いろんな思いが頭を巡りながらも、カケルは徐々にまどろみの中に落ちていった。
翌朝、まだ陽が登る前に、カケルは館に行った。昨日見つけた巻物をもう一度開き、そこに書かれている地図と印を頭に叩き込んだ。そこに巫女セイが現れた。
「カケルよ、どうするのじゃ?」
「セイ様。災いになるか、救いになるか、わかりません。でも、これを見たもののさだめなら、最後までやってみます。」
セイを見たカケルの目には覚悟が感じられた。
「よかろう。・・・ミコト達にはワシが話しておく。」
カケルは、地図の印の着いた場所に向かうことにした。
ひとつは、館の裏手の斜面あたりだった。獣除けの柵と堀の間に、小さな門があったが、ずっと閉じられたままであったため、蔦が絡みつき、そこにあることもわからないようになっていた。カケルはその門をそっと開くと、村の裏手に出た。雑草と低木が茂り、その先には竹やぶも広がっている。カケルは少しずつ周囲を探りながら、深く分け入った。

タグ:霧島 遺産 倭国 文字
-帰還-2.目印 [アスカケ第1部 高千穂峰]
2.目印
深い深い竹やぶが続いていた。途中には、深い溝がいくつか掘られ、入る者を拒んでいるかのようであった。いくつかは飛び越え、いくつかは転げ落ち、這い上がり、なんとか越えた。そのうちに、茨の森を抜けると、大きな岩壁が見え、前が開けた。
地図に打たれた印の場所にたどり着いたようだった。特に怪しい雰囲気は感じなかったが、明らかに、人手で開かれた場所には間違いなかった。岩壁のやや斜面になった辺りに、こんもりとした盛り土のようなものがあった。カケルは近づいて、盛り土を見たが、何かを特定することはできない。少し、地面を削ってみると、古い黒炭が出てきた。明らかにここで何かを燃やしたのだった。カケルは、盛り土の周りを探った。足元に赤茶けた塊が落ちている。拾い上げるとずっしりと重くて硬い。石のようだが違う。何かが溶けて固まったようなものだった。
カケルは、巻物を広げてみた。地図に続き、何だか読めない難しい文字があり、こんもりとした盛り土や炭、そして作業の様子が書かれていた。
「これで何かを燃やして、この茶色のものを作るのかな?」
更に広げてみると、叩いたり削ったりする絵があり、さらに、刀や棒のようなものが描かれていた。形から、猟をする時に、木や骨や石で作っている道具とよく似ていた。
「何か道具の元になるものが作れるというのかな?」
カケルは、その茶色の塊を懐にしまって、もう一度、地図をみた。
「確かに、この印が打ってある場所には何かある。次のところにも行ってみよう。」
次に目指す印は、その場所から、東へ出て、高千穂の峰の登り口あたりのようだった。
また深い竹薮を戻った。その先は、更に深い森だった。普段なら、立ち入る事は禁じられている森だ。
慎重に歩いている途中、妙な事に気づいた。来る時は気づかなかったが、ただ竹薮が広がっているのではなく、足元には石が敷き詰めてあるようだった。ところどころは、崩れてしまったり、草に埋もれていたりするが、確かに、平たい石が敷き詰めてあり、歩きやすくなっている。深い森のはずなのに、ちゃんと通れるような道がついているのだ。周りの木々にも、何かがぶつかり擦れたような跡もあった。次の目的地までは随分距離がある。
もう昼を回っていた。
途中、カケルは、サルナシの実を摘んだ。サルナシは、熟すと甘くなる。渇いた喉を潤し、空腹を満たすには好都合だった。カケルは、サルナシを持ったまま、辺りで一番高いくすの木によじ登った。梢から顔を出すと、森を上から見下ろした。深い森が、高千穂の峰の中腹辺りまで広がっていた。カケルは、梢の枝を支えにして、体を横たえ、サルナシをかじりながら、青空を見上げた。空には、ハヤテが旋回していた。
「ハヤテのやつにはすぐ見つかるなあ・・。」
カケルは、ハヤテの姿を目で追いながら、少しうとうととした。
ビューっと一陣の風が吹いてきて、枝が揺れた。その拍子に、カケルも目を覚ました。少し伸びをしたあと、カケルは次に目指す場所の方向を見定める。
目指している次の場所あたりは、少し森が薄く、陥没したような形に見えた。カケルは、巻物の地図と照らして、目指す方向を確認した。

するすると楠木から降りると、再び森の中を進んだ。先ほどのような石畳が残る道だった。更に進むと、森の脇に、小さな洞窟のようなものがある。入り口は、蔦や苔で覆われ、中は真っ暗で様子がわからなかったが、自然の洞窟ではなく、明らかに人の手で開けられたものだった。よく見ると、他にも数箇所の穴があり、赤茶けた斜面も削られている。
「ここで、何かを掘っていたのかな?石かな?・・何を掘ってたんだろ。」
カケルには、この二つの関連は理解できなかった。再び、巻物を開く。どう見ても、この二つは何かを作るための仕掛けのようだった。
「あと三つあるな。・・・でも、印の形が違う。・・・どいうことは、また別のものか?」
そう呟くと、来た道を戻った。次の目印は、ナレの村よりも下・・つまり、南側の谷だった。何度か、ナギとともに行った事のある辺りだった。
「あの辺りには、何もないよな。・・背丈ほどの低い木が生えているだけのはず。」
山道を下りながら、全ての目印を探すのだけでも、大変なことだと思い始めていた。
ナレの村に戻れたのは、もう陽が傾き始めていた。3つ目の印には、明日行く事にして、一旦館に戻った。
深い深い竹やぶが続いていた。途中には、深い溝がいくつか掘られ、入る者を拒んでいるかのようであった。いくつかは飛び越え、いくつかは転げ落ち、這い上がり、なんとか越えた。そのうちに、茨の森を抜けると、大きな岩壁が見え、前が開けた。
地図に打たれた印の場所にたどり着いたようだった。特に怪しい雰囲気は感じなかったが、明らかに、人手で開かれた場所には間違いなかった。岩壁のやや斜面になった辺りに、こんもりとした盛り土のようなものがあった。カケルは近づいて、盛り土を見たが、何かを特定することはできない。少し、地面を削ってみると、古い黒炭が出てきた。明らかにここで何かを燃やしたのだった。カケルは、盛り土の周りを探った。足元に赤茶けた塊が落ちている。拾い上げるとずっしりと重くて硬い。石のようだが違う。何かが溶けて固まったようなものだった。
カケルは、巻物を広げてみた。地図に続き、何だか読めない難しい文字があり、こんもりとした盛り土や炭、そして作業の様子が書かれていた。
「これで何かを燃やして、この茶色のものを作るのかな?」
更に広げてみると、叩いたり削ったりする絵があり、さらに、刀や棒のようなものが描かれていた。形から、猟をする時に、木や骨や石で作っている道具とよく似ていた。
「何か道具の元になるものが作れるというのかな?」
カケルは、その茶色の塊を懐にしまって、もう一度、地図をみた。
「確かに、この印が打ってある場所には何かある。次のところにも行ってみよう。」
次に目指す印は、その場所から、東へ出て、高千穂の峰の登り口あたりのようだった。
また深い竹薮を戻った。その先は、更に深い森だった。普段なら、立ち入る事は禁じられている森だ。
慎重に歩いている途中、妙な事に気づいた。来る時は気づかなかったが、ただ竹薮が広がっているのではなく、足元には石が敷き詰めてあるようだった。ところどころは、崩れてしまったり、草に埋もれていたりするが、確かに、平たい石が敷き詰めてあり、歩きやすくなっている。深い森のはずなのに、ちゃんと通れるような道がついているのだ。周りの木々にも、何かがぶつかり擦れたような跡もあった。次の目的地までは随分距離がある。
もう昼を回っていた。
途中、カケルは、サルナシの実を摘んだ。サルナシは、熟すと甘くなる。渇いた喉を潤し、空腹を満たすには好都合だった。カケルは、サルナシを持ったまま、辺りで一番高いくすの木によじ登った。梢から顔を出すと、森を上から見下ろした。深い森が、高千穂の峰の中腹辺りまで広がっていた。カケルは、梢の枝を支えにして、体を横たえ、サルナシをかじりながら、青空を見上げた。空には、ハヤテが旋回していた。
「ハヤテのやつにはすぐ見つかるなあ・・。」
カケルは、ハヤテの姿を目で追いながら、少しうとうととした。
ビューっと一陣の風が吹いてきて、枝が揺れた。その拍子に、カケルも目を覚ました。少し伸びをしたあと、カケルは次に目指す場所の方向を見定める。
目指している次の場所あたりは、少し森が薄く、陥没したような形に見えた。カケルは、巻物の地図と照らして、目指す方向を確認した。

するすると楠木から降りると、再び森の中を進んだ。先ほどのような石畳が残る道だった。更に進むと、森の脇に、小さな洞窟のようなものがある。入り口は、蔦や苔で覆われ、中は真っ暗で様子がわからなかったが、自然の洞窟ではなく、明らかに人の手で開けられたものだった。よく見ると、他にも数箇所の穴があり、赤茶けた斜面も削られている。
「ここで、何かを掘っていたのかな?石かな?・・何を掘ってたんだろ。」
カケルには、この二つの関連は理解できなかった。再び、巻物を開く。どう見ても、この二つは何かを作るための仕掛けのようだった。
「あと三つあるな。・・・でも、印の形が違う。・・・どいうことは、また別のものか?」
そう呟くと、来た道を戻った。次の目印は、ナレの村よりも下・・つまり、南側の谷だった。何度か、ナギとともに行った事のある辺りだった。
「あの辺りには、何もないよな。・・背丈ほどの低い木が生えているだけのはず。」
山道を下りながら、全ての目印を探すのだけでも、大変なことだと思い始めていた。
ナレの村に戻れたのは、もう陽が傾き始めていた。3つ目の印には、明日行く事にして、一旦館に戻った。
-帰還-3.神器 [アスカケ第1部 高千穂峰]
3.神器
館で、カケルはもって返ってきた茶色の塊と巻物を取り出した。
「一体、これはなんだろう。ただの石ころとは違うみたいだけど・・・。」
目の前にある塊を持っていた小刀で叩いてみた。キンキンという高い音が響く。ふと思いついた。
「そういえば、・・この刀・・石じゃないし、骨でもない・・・これって何で作ったんだろう。」
そうしているところに、巫女が戻ってきた。
カケルが頭を掻きながら、何か考え事をしているのはすぐにわかったが、それよりもカケルの目の前に置かれた塊をみて驚いた。
「カケルよ!それをどうした?」
「ああ、セイ様。・・・巻物の印の場所を探していて、拾ったんです。・・これは何ですか?」
セイは塊を手にしてじっと見入った。そして、塊をそこにおくと、じっと考え込んだ。ふっと立ち上がり、祭壇に向かってうやうやしくお辞儀をすると、やにわに手を入れた。祭壇に奉納されている神器を取り出そうとしている。慎重に取り出すと、カケルの前にゆっくりと置いた。村の者には、神器を見ることは許されていなかった。カケルは、慌てて頭を床につけ眼を閉じていた。
「カケル。顔を上げてよく見るのじゃ。」
カケルはおそるおそる顔を上げ、神器を見た。それは、鈍い銀色の光を怪しく放っていた。カケルが両手を広げたほどの長さがあり、鋭く尖っていた。
「これは、剣(つるぎ)じゃ。・・・・お前が拾ってきたものは、この神器、剣(つるぎ)を作る元になるもので、古人(いにしえびと)はハガネと呼んでおったようじゃ。・・・おお、そうじゃ、お前が持っている小刀も同じじゃ。ミコト達や、限られたものが代々受け継いできた。・・お前が見つけたのは、このハガネを作るタタラという場所じゃ。・・どうの昔に隠され、だれも見つける事はできなかった。・・いや、見つける事は禁じられてきたのじゃ。」
「どうして?」
「この剣は、神の道具。大いなる力の元なのじゃ。それは、災いを払う。神器として祀るのも、その大いなる力で一族を災いより守りいただくためじゃ。じゃが、大いなる力は時として、大きな災いや争いを生む。命を危め、一族を滅ぼすこととになる。古人はそれを恐れ、その元を作る場所・・タタラ場を見つける事は、一族に災いが及ぶと謂われてきたのじゃ。」
「もうひとつの場所は、洞穴でした。・・何かを掘っていたような・・」
「おそらく、ハガネの元になるものを掘っておったのじゃろう。・・ハガネは砂より生まれる。砂を焼き続け、砂の命を取り出し、冷やし固めるとハガネができると言う。砂はこの大地そのものじゃ。よって、大地の命を削り、焼き、冷やし固めて生まれるハガネには、この大地の命が封じ込められておる。いや、大地の怒りの固まりやも知れぬ。だからこそ、人を危める剣となるのじゃ。古人は、この剣を作ったのち、タタラ場を壊し、隠した。のちの一族に災いが及ばぬようにしたのじゃ。」
この時代、この国にはまだ鉄を作る技術は広まっていなかったとされている。大陸の戦乱の中、難を逃れ、倭国へ渡った渡来人にとっては、鉄器はなくてはならないものであった。砂鉄を探し、炭を作り、タタラ場を作る事は重要な事であった。一方で、渡来人である証であり、倭人との諍いも起きたであろう。剣等の武器を作り、倭人を力でねじ伏せることもできたはずである。この倭国で、倭人と共に生きていくために、この一族の先人たちは、大陸からの高い技術を敢えて封印したのである。
「カケルよ。この塊は隠しておくのじゃ。まだ、時は来ておらぬ。今しばらく、タタラ場の事は皆には秘密じゃ。良いな。」
「はい。・・・だけど・・」
「お前の言いたい事は判る。まだ待つのじゃ。いずれ役に立てる時が来る。・・それより、巻物には他にも何か隠されているのではないか。」
「はい。まだ・・。」
「タタラ以外の事は、きっと今の我らの暮らしに生きるはずじゃ。まず、それを探し当てるのじゃ。・・お前の母を救った薬草のように・・良いな。」
巫女セイはそう言うと、奥の部屋に入ってしまった。
カケルも、一日中、山を駆け回ったせいか、随分疲れてしまい、家に戻る事にした。
その夜遅く、巫女セイは長老と話していた。
「カケルが、タタラ場を見つけたようじゃ。」
「・・なんですと・・我らが何年も探して見つけられなかったものを・・・やはり、カケルには底知れぬ力があるようだな・・・。」
「いずれ、またハガネを作る日が来よう。・・村にも・・恵みと災いが来るのであろうな。・・」
「今しばらく、時を待とう。・・・アスカケから戻るミコトもある。その者からも様子を聞き、タタラ場を興すかどうか決める事にしよう。」

館で、カケルはもって返ってきた茶色の塊と巻物を取り出した。
「一体、これはなんだろう。ただの石ころとは違うみたいだけど・・・。」
目の前にある塊を持っていた小刀で叩いてみた。キンキンという高い音が響く。ふと思いついた。
「そういえば、・・この刀・・石じゃないし、骨でもない・・・これって何で作ったんだろう。」
そうしているところに、巫女が戻ってきた。
カケルが頭を掻きながら、何か考え事をしているのはすぐにわかったが、それよりもカケルの目の前に置かれた塊をみて驚いた。
「カケルよ!それをどうした?」
「ああ、セイ様。・・・巻物の印の場所を探していて、拾ったんです。・・これは何ですか?」
セイは塊を手にしてじっと見入った。そして、塊をそこにおくと、じっと考え込んだ。ふっと立ち上がり、祭壇に向かってうやうやしくお辞儀をすると、やにわに手を入れた。祭壇に奉納されている神器を取り出そうとしている。慎重に取り出すと、カケルの前にゆっくりと置いた。村の者には、神器を見ることは許されていなかった。カケルは、慌てて頭を床につけ眼を閉じていた。
「カケル。顔を上げてよく見るのじゃ。」
カケルはおそるおそる顔を上げ、神器を見た。それは、鈍い銀色の光を怪しく放っていた。カケルが両手を広げたほどの長さがあり、鋭く尖っていた。
「これは、剣(つるぎ)じゃ。・・・・お前が拾ってきたものは、この神器、剣(つるぎ)を作る元になるもので、古人(いにしえびと)はハガネと呼んでおったようじゃ。・・・おお、そうじゃ、お前が持っている小刀も同じじゃ。ミコト達や、限られたものが代々受け継いできた。・・お前が見つけたのは、このハガネを作るタタラという場所じゃ。・・どうの昔に隠され、だれも見つける事はできなかった。・・いや、見つける事は禁じられてきたのじゃ。」
「どうして?」
「この剣は、神の道具。大いなる力の元なのじゃ。それは、災いを払う。神器として祀るのも、その大いなる力で一族を災いより守りいただくためじゃ。じゃが、大いなる力は時として、大きな災いや争いを生む。命を危め、一族を滅ぼすこととになる。古人はそれを恐れ、その元を作る場所・・タタラ場を見つける事は、一族に災いが及ぶと謂われてきたのじゃ。」
「もうひとつの場所は、洞穴でした。・・何かを掘っていたような・・」
「おそらく、ハガネの元になるものを掘っておったのじゃろう。・・ハガネは砂より生まれる。砂を焼き続け、砂の命を取り出し、冷やし固めるとハガネができると言う。砂はこの大地そのものじゃ。よって、大地の命を削り、焼き、冷やし固めて生まれるハガネには、この大地の命が封じ込められておる。いや、大地の怒りの固まりやも知れぬ。だからこそ、人を危める剣となるのじゃ。古人は、この剣を作ったのち、タタラ場を壊し、隠した。のちの一族に災いが及ばぬようにしたのじゃ。」
この時代、この国にはまだ鉄を作る技術は広まっていなかったとされている。大陸の戦乱の中、難を逃れ、倭国へ渡った渡来人にとっては、鉄器はなくてはならないものであった。砂鉄を探し、炭を作り、タタラ場を作る事は重要な事であった。一方で、渡来人である証であり、倭人との諍いも起きたであろう。剣等の武器を作り、倭人を力でねじ伏せることもできたはずである。この倭国で、倭人と共に生きていくために、この一族の先人たちは、大陸からの高い技術を敢えて封印したのである。
「カケルよ。この塊は隠しておくのじゃ。まだ、時は来ておらぬ。今しばらく、タタラ場の事は皆には秘密じゃ。良いな。」
「はい。・・・だけど・・」
「お前の言いたい事は判る。まだ待つのじゃ。いずれ役に立てる時が来る。・・それより、巻物には他にも何か隠されているのではないか。」
「はい。まだ・・。」
「タタラ以外の事は、きっと今の我らの暮らしに生きるはずじゃ。まず、それを探し当てるのじゃ。・・お前の母を救った薬草のように・・良いな。」
巫女セイはそう言うと、奥の部屋に入ってしまった。
カケルも、一日中、山を駆け回ったせいか、随分疲れてしまい、家に戻る事にした。
その夜遅く、巫女セイは長老と話していた。
「カケルが、タタラ場を見つけたようじゃ。」
「・・なんですと・・我らが何年も探して見つけられなかったものを・・・やはり、カケルには底知れぬ力があるようだな・・・。」
「いずれ、またハガネを作る日が来よう。・・村にも・・恵みと災いが来るのであろうな。・・」
「今しばらく、時を待とう。・・・アスカケから戻るミコトもある。その者からも様子を聞き、タタラ場を興すかどうか決める事にしよう。」

-帰還-4,三つ目の印 [アスカケ第1部 高千穂峰]
4.三つ目の印
次の日から数日は、雨続きになり、カケルも隠された印の場所を探すのは諦め、漁に使う銛や籠の手入れをしたり、母の薬の下ごしらえ等の仕事で過ごしていた。父ナギも、猟のための仕掛けを手入れして過ごしていた。
「とと様、この小刀は・・」
と言いかけてカケルは止めた。タタラ場で見つけたハガネの事を知られると思ったのだった。
「何だ?カケル。その小刀は、お前の爺様のものだ。お前が生まれた時、爺様がくだされた。よく研げば、何でも切れる。」
「とと様も持ってる?」
「ああ、俺のは、俺の爺様から貰ったものだ。お前のものよりも少し重くて大きい。使いづらいが、猪を捕らえる時には役に立つ。しっかり身を裂けるからな。」
「ミコト様は皆持ってるの?」
「ああ、この村にはそれぞれの家に伝わった小刀があると聞く。確か、村には小刀は9本あると聞いたが・・誰がもっておるのかは知らぬ。」
「何か、特別なものなの?」
「ああ・・古より伝わるものだ。一族を災いから守るため、神様が下されたものだと・・・粗末に扱うのではないぞ。・・それと・・できるだけ身につけ、盗られたり、見られたりせぬよう気をつけるのだ。」
カケルは物心ついた時には、腰につけていた。小さい頃から、父ナギに同じ話を聞かされていたが、これほど大事な事だとは思っていなかった。巻物の秘密を知った事で、小刀も違ってみえる。
数日が過ぎ、ようやく天気が回復した。カケルは3つ目の印の場所へ行く事にした。
3つ目は、村の南側、大門を出て、村のある丘を少し下ったところだった。アスカケに出たケスキが下った道を少し進み、途中でまた、山手に上がる場所になっていた。カケルはゆっくりその場所への入り口を探って、昨日の山の中で見たのと同じような石敷きがあるのを見つけた。草が生い茂り、入り口には盛り土がされ、そこへ立ち入るのを遮っているようだった。古人が塞いだのだとカケルは感じ、ここに次の秘密があると確信した。
盛り土をよじ登ると、カケルが予想したとおり、低木が一面に広がっていた。この近くには、ナギにつれられ、ウサギの猟をしたことがあった。
「ここに何があるのだろう」
昨日のタタラ場のような造り物はなさそうだった。背丈ほどの低い木の中を何度も何度も歩いてみたが、何も見つからなかった。中ほどに少し木の生えていない場所があり、カケルは歩きつかれたので、そこに体を横たえ、大空を見上げた。初秋に入って、日陰は心地よい風が吹き、昼寝にはちょうど良い気候で、カケルは少しうとうとしていた。そのうち、何か地響きのような、低い音が聞こえた。空は晴れている。どこからするのか耳を澄ました。・・・どうやら、地面から聞こえてくるようだった。カケルは起き上がると、辺りの草を刈り、地面をむき出しにしてみた。少し地面を掘ると、硬い石に当たった。さらに石の周りを掘った。それは、自分の身の丈ほどの大きさで、まるで地面に蓋をしているような石があるのが判った。
「この石の下に何かあるんだ。・・低い音が聞こえる・・・何があるんだろう・・」
石をじっと触ってみた。普通、石ならひんやりとするはずなのだが、この石は何故か温かい。カケルは、石の上にかかっている土を全て払い、周りを掘り始めた。どこか、中が見えるような箇所はないか、とにかく掘り続けた。その石は、まるで亀のような格好をしていた。頭に当たる部分には明らかに掘り込まれた跡がある。その下にわずかに見える部分にも石組みがされていた。どうやら井戸のような形になっているのがわかった。しかし、カケルの力ではこれ以上は無理だった。疲れ果て、石を椅子にして座った時だった。先ほどの地響きのような音が、足元からどんどん近づいてくる。そして、どーんと当たったような衝撃を感じた。岩の隙間から、熱い蒸気が噴出してきた。辺りには湯気が立ち込めた。
最初、カケルは何が起きたのか判らず呆然としていた。しばらくして、我に返った時、ここが熱い湯が噴出すところだと判った。
この時代、人々はまだ湯に浸かる習慣は持っておらず、体を洗うのは川の水を使う程度であった。火が貴重な時代である。大量の湯を沸かす事は、並大抵の事ではなかったのだ。
カケルは、館で読んだ書物を思い出していた。確か、病を治す方法の中に、体を熱い湯に浸ける事が書かれていたのだ。母の病を治す方法として覚えたが、体を浸けるほど大量の湯を沸かす事は容易ではない。その湯がここには大量にあるのだ。カケルは何としてもこの湯を使いたいと考えた。すぐに村に戻り、相談する事にした。
カケルの話を聞いた長老は、すぐにミコト達を集め、カケルが見つけた場所に向かった。
「おお、確かに、湯気が出ている。・・・よくやったぞ、カケル。」
ミコト達は力を合わせて、蓋になっている石を棒を使って動かし始めた。ギリギリと音がしてゆっくりと石はずらされた。カケルが予想したとおり、蓋石をどけると、井戸のように石が汲まれていた。中を覗いたが、湯はなかった。小石を投げ入れると、しばらくして音がした。遥か底の方に水面があるようだった。
「これじゃあ、湯を汲めないな。・・・」
そう言った時だった。先ほどのように、いきなり音がして下から蒸気が上がってくる。そして、勢い良く湯気が立ち上り、湯が噴出した。周りに居たミコト達は、全身、ずぶ濡れになった。始めてみる光景に、カケルもミコト達も驚き、歓喜した。何度か同じように噴出したが徐々に落ち着き、岩の囲いを超えて流れるようになった。ミコト達は周辺の低木を次々に切り払った。

次の日から数日は、雨続きになり、カケルも隠された印の場所を探すのは諦め、漁に使う銛や籠の手入れをしたり、母の薬の下ごしらえ等の仕事で過ごしていた。父ナギも、猟のための仕掛けを手入れして過ごしていた。
「とと様、この小刀は・・」
と言いかけてカケルは止めた。タタラ場で見つけたハガネの事を知られると思ったのだった。
「何だ?カケル。その小刀は、お前の爺様のものだ。お前が生まれた時、爺様がくだされた。よく研げば、何でも切れる。」
「とと様も持ってる?」
「ああ、俺のは、俺の爺様から貰ったものだ。お前のものよりも少し重くて大きい。使いづらいが、猪を捕らえる時には役に立つ。しっかり身を裂けるからな。」
「ミコト様は皆持ってるの?」
「ああ、この村にはそれぞれの家に伝わった小刀があると聞く。確か、村には小刀は9本あると聞いたが・・誰がもっておるのかは知らぬ。」
「何か、特別なものなの?」
「ああ・・古より伝わるものだ。一族を災いから守るため、神様が下されたものだと・・・粗末に扱うのではないぞ。・・それと・・できるだけ身につけ、盗られたり、見られたりせぬよう気をつけるのだ。」
カケルは物心ついた時には、腰につけていた。小さい頃から、父ナギに同じ話を聞かされていたが、これほど大事な事だとは思っていなかった。巻物の秘密を知った事で、小刀も違ってみえる。
数日が過ぎ、ようやく天気が回復した。カケルは3つ目の印の場所へ行く事にした。
3つ目は、村の南側、大門を出て、村のある丘を少し下ったところだった。アスカケに出たケスキが下った道を少し進み、途中でまた、山手に上がる場所になっていた。カケルはゆっくりその場所への入り口を探って、昨日の山の中で見たのと同じような石敷きがあるのを見つけた。草が生い茂り、入り口には盛り土がされ、そこへ立ち入るのを遮っているようだった。古人が塞いだのだとカケルは感じ、ここに次の秘密があると確信した。
盛り土をよじ登ると、カケルが予想したとおり、低木が一面に広がっていた。この近くには、ナギにつれられ、ウサギの猟をしたことがあった。
「ここに何があるのだろう」
昨日のタタラ場のような造り物はなさそうだった。背丈ほどの低い木の中を何度も何度も歩いてみたが、何も見つからなかった。中ほどに少し木の生えていない場所があり、カケルは歩きつかれたので、そこに体を横たえ、大空を見上げた。初秋に入って、日陰は心地よい風が吹き、昼寝にはちょうど良い気候で、カケルは少しうとうとしていた。そのうち、何か地響きのような、低い音が聞こえた。空は晴れている。どこからするのか耳を澄ました。・・・どうやら、地面から聞こえてくるようだった。カケルは起き上がると、辺りの草を刈り、地面をむき出しにしてみた。少し地面を掘ると、硬い石に当たった。さらに石の周りを掘った。それは、自分の身の丈ほどの大きさで、まるで地面に蓋をしているような石があるのが判った。
「この石の下に何かあるんだ。・・低い音が聞こえる・・・何があるんだろう・・」
石をじっと触ってみた。普通、石ならひんやりとするはずなのだが、この石は何故か温かい。カケルは、石の上にかかっている土を全て払い、周りを掘り始めた。どこか、中が見えるような箇所はないか、とにかく掘り続けた。その石は、まるで亀のような格好をしていた。頭に当たる部分には明らかに掘り込まれた跡がある。その下にわずかに見える部分にも石組みがされていた。どうやら井戸のような形になっているのがわかった。しかし、カケルの力ではこれ以上は無理だった。疲れ果て、石を椅子にして座った時だった。先ほどの地響きのような音が、足元からどんどん近づいてくる。そして、どーんと当たったような衝撃を感じた。岩の隙間から、熱い蒸気が噴出してきた。辺りには湯気が立ち込めた。
最初、カケルは何が起きたのか判らず呆然としていた。しばらくして、我に返った時、ここが熱い湯が噴出すところだと判った。
この時代、人々はまだ湯に浸かる習慣は持っておらず、体を洗うのは川の水を使う程度であった。火が貴重な時代である。大量の湯を沸かす事は、並大抵の事ではなかったのだ。
カケルは、館で読んだ書物を思い出していた。確か、病を治す方法の中に、体を熱い湯に浸ける事が書かれていたのだ。母の病を治す方法として覚えたが、体を浸けるほど大量の湯を沸かす事は容易ではない。その湯がここには大量にあるのだ。カケルは何としてもこの湯を使いたいと考えた。すぐに村に戻り、相談する事にした。
カケルの話を聞いた長老は、すぐにミコト達を集め、カケルが見つけた場所に向かった。
「おお、確かに、湯気が出ている。・・・よくやったぞ、カケル。」
ミコト達は力を合わせて、蓋になっている石を棒を使って動かし始めた。ギリギリと音がしてゆっくりと石はずらされた。カケルが予想したとおり、蓋石をどけると、井戸のように石が汲まれていた。中を覗いたが、湯はなかった。小石を投げ入れると、しばらくして音がした。遥か底の方に水面があるようだった。
「これじゃあ、湯を汲めないな。・・・」
そう言った時だった。先ほどのように、いきなり音がして下から蒸気が上がってくる。そして、勢い良く湯気が立ち上り、湯が噴出した。周りに居たミコト達は、全身、ずぶ濡れになった。始めてみる光景に、カケルもミコト達も驚き、歓喜した。何度か同じように噴出したが徐々に落ち着き、岩の囲いを超えて流れるようになった。ミコト達は周辺の低木を次々に切り払った。

タグ:霧島 源泉 印
‐帰還‐5.湯治 [アスカケ第1部 高千穂峰]
5.湯治
温泉の噴出した周辺を切り払うと、湧き出した湯の流れる先が一段低くなっているのが見えた。ミコト達は、湯の流れた辺りを掘り返してみた。そこには、石を敷き詰め固められた水路のようなものがあり、さらに一段下がったところには岩を並べて、湯を溜めるような設えがあるのがわかった。皆、湯と泥に塗れながら、辺り一帯を掘り返していった。日暮れ近くになると、おおよその様子が見えてきた。昔、ここには湯殿があったようだった。掘り返した土の下からはいくつかの柱のようなものも現れた。
巫女と長老がその場に現れた。そしてミコト達に向かって言った。
「これは古人の設えた湯場だな。・・よく見つけた。」
「おさ様・・なぜ、古人はここを隠したのでしょう。」
一人のミコトが尋ねた。
「・・判らぬ・・何か災いがあったのやも知れぬが・・・。」
カケルは、館で読んだ書物を思い出していた。湯場について書かれたものが確かにあったはずだ。だが、なかなか思い出せなかった。
そうしていると、別のミコトが大きな声で皆を呼んだ。
「おい、ここにも何かあるようだぞ。」
湯の噴き出している場所の更に上に、カケルが見つけたものと同じような石組みで蓋のある場所があった。近づいてみると、全体に黄色く変色し、異様な臭いもしていた。ミコト達は、すぐに蓋を開けようとした。カケルが急に思い出したように叫んだ。
「だめ!そこを開けてはいけない!」
その声にミコト達は止まった。
「そこを開けると毒気が上がってくる。・・毒気を吸うと、皆もだえ苦しむとあった。止めて!」
皆、カケルの話を聞いて、その場を飛び退いた。巫女セイが言う。
「そうか・・昔、そういう災いがあったのじゃな・・それでここを埋めたのじゃな。」
「その場には触れるでない。・・・そこは今一度埋め戻すのだ。・・そうだ、辺りの岩を集め、さらに蓋を頑丈にして、二度と毒気の出ないようにしておく。」
ミコト達は、辺りに散らばっている岩を集め、乗せ、土をかぶせて埋め戻した。
一通り、作業を終えた頃には日暮れとなり、皆、家に戻った。
翌朝、村人は皆、温泉に集まっていた。ミコト達が家に戻り、温泉の話をしており、みな興味深く、湯の湧き出す様子を見ていた。そこを分け入るように巫女と長老、カケルが入ってくる。
「皆、聞くのだ。」
長老の一言で、静まった。
「さあ、カケル、話すがよい。お前の知っている事を皆に伝えるのじゃ。」
巫女が促し、カケルは皆に聞こえるよう、岩の上に上がってこう話した。
「これは、温泉といって・・・大地の命が湧き出ているんだ。古人の伝えでは、この湯で、体を清めれば穢れが取れる。それから、湯に体を浸け温めると病の元である毒を抜いてくれる。」
カケルがそう言うと村人は皆どよめいた。
「じゃあ・・傷も治してくれるのかい?」
誰かが聞いた。みな、同じように頷いて、カケルの返答を待った。
「はい、ゆっくり浸かって傷を癒せば良いと・・。」
村人は顔を見合わせ、喜んだ。森で見つけた薬草に続いて、温泉を見つけ、村人の病を治療する術をカケルは見つけたのだ。
「おお、それなら・・ナミを・・お前の母様を一番に入れてやれ!」
誰かが言った。みな、賛同した。だが、カケルは、俯いたまま返答しない。父ナギが皆に言った。
「すまない。・・夕べ、ナミにカケルが話したんだ。だが・・ナミは嫌だと言うんだ。」
「せっかく、病を治せる湯をカケルが見つけたのに・・。」
「よし、俺たちがナミを説得してやる。行くぞ・・おい。」
「いや、よしなさいよ。判るよ、私は。ナミの気持ちがさ。」
「何が判るんだよ!」
口々に皆言い争いを始めた。ナギは皆を制するように言った。
「みんな、すまない。・・・・俺も如何してなんだと訊いた。・・そうなんだ・・ナミは、随分痩せてしまった。・・だから・・皆に見せたくないんだと。・・」
それを聞いて皆押し黙った。気づくとカケルは涙を零している。
「大丈夫よ!・・ねえ、皆でこの湯の周りに囲いを作りましょう。目隠しを作れば、かか様も気にすることなく入れる。」
言い出したのは、イツキだった。すぐに、近くの竹を切りだした。竹は四つに割られ板にした。ナギが家から細縄を持ってきて、竹の目隠しを作った。出来上がった頃、ナギは、ナミを迎えに行った。背負子に乗ったナミを、村の皆で迎えた。
「さあ、これでいいだろう。・・俺が抱えてやる。大丈夫だ。カケルが見つけた湯だ。綺麗に体を清め、毒を出してやればきっと良くなる。さあ。」
ナギは、ナミを抱え、目隠しの中へ入っていった。しばらくすると、湯船に浸かる音がした。
「ああ・・・良い気持ちだ・・なあ、ナミ、どうだ?」
「ええ・・とっても・・・体が芯から温まる・・・気持ちいいわ。痛いのを忘れられる・・ほんとに、ありがとう、カケル。皆さん・・本当にありがとう・・・」
ナミは、ナギに抱えられたまま湯船に浸かり、涙を流していた。
「おい、カケル。イツキ。お前たちも来い。カカ様の体を綺麗にしてやろう。」

温泉の噴出した周辺を切り払うと、湧き出した湯の流れる先が一段低くなっているのが見えた。ミコト達は、湯の流れた辺りを掘り返してみた。そこには、石を敷き詰め固められた水路のようなものがあり、さらに一段下がったところには岩を並べて、湯を溜めるような設えがあるのがわかった。皆、湯と泥に塗れながら、辺り一帯を掘り返していった。日暮れ近くになると、おおよその様子が見えてきた。昔、ここには湯殿があったようだった。掘り返した土の下からはいくつかの柱のようなものも現れた。
巫女と長老がその場に現れた。そしてミコト達に向かって言った。
「これは古人の設えた湯場だな。・・よく見つけた。」
「おさ様・・なぜ、古人はここを隠したのでしょう。」
一人のミコトが尋ねた。
「・・判らぬ・・何か災いがあったのやも知れぬが・・・。」
カケルは、館で読んだ書物を思い出していた。湯場について書かれたものが確かにあったはずだ。だが、なかなか思い出せなかった。
そうしていると、別のミコトが大きな声で皆を呼んだ。
「おい、ここにも何かあるようだぞ。」
湯の噴き出している場所の更に上に、カケルが見つけたものと同じような石組みで蓋のある場所があった。近づいてみると、全体に黄色く変色し、異様な臭いもしていた。ミコト達は、すぐに蓋を開けようとした。カケルが急に思い出したように叫んだ。
「だめ!そこを開けてはいけない!」
その声にミコト達は止まった。
「そこを開けると毒気が上がってくる。・・毒気を吸うと、皆もだえ苦しむとあった。止めて!」
皆、カケルの話を聞いて、その場を飛び退いた。巫女セイが言う。
「そうか・・昔、そういう災いがあったのじゃな・・それでここを埋めたのじゃな。」
「その場には触れるでない。・・・そこは今一度埋め戻すのだ。・・そうだ、辺りの岩を集め、さらに蓋を頑丈にして、二度と毒気の出ないようにしておく。」
ミコト達は、辺りに散らばっている岩を集め、乗せ、土をかぶせて埋め戻した。
一通り、作業を終えた頃には日暮れとなり、皆、家に戻った。
翌朝、村人は皆、温泉に集まっていた。ミコト達が家に戻り、温泉の話をしており、みな興味深く、湯の湧き出す様子を見ていた。そこを分け入るように巫女と長老、カケルが入ってくる。
「皆、聞くのだ。」
長老の一言で、静まった。
「さあ、カケル、話すがよい。お前の知っている事を皆に伝えるのじゃ。」
巫女が促し、カケルは皆に聞こえるよう、岩の上に上がってこう話した。
「これは、温泉といって・・・大地の命が湧き出ているんだ。古人の伝えでは、この湯で、体を清めれば穢れが取れる。それから、湯に体を浸け温めると病の元である毒を抜いてくれる。」
カケルがそう言うと村人は皆どよめいた。
「じゃあ・・傷も治してくれるのかい?」
誰かが聞いた。みな、同じように頷いて、カケルの返答を待った。
「はい、ゆっくり浸かって傷を癒せば良いと・・。」
村人は顔を見合わせ、喜んだ。森で見つけた薬草に続いて、温泉を見つけ、村人の病を治療する術をカケルは見つけたのだ。
「おお、それなら・・ナミを・・お前の母様を一番に入れてやれ!」
誰かが言った。みな、賛同した。だが、カケルは、俯いたまま返答しない。父ナギが皆に言った。
「すまない。・・夕べ、ナミにカケルが話したんだ。だが・・ナミは嫌だと言うんだ。」
「せっかく、病を治せる湯をカケルが見つけたのに・・。」
「よし、俺たちがナミを説得してやる。行くぞ・・おい。」
「いや、よしなさいよ。判るよ、私は。ナミの気持ちがさ。」
「何が判るんだよ!」
口々に皆言い争いを始めた。ナギは皆を制するように言った。
「みんな、すまない。・・・・俺も如何してなんだと訊いた。・・そうなんだ・・ナミは、随分痩せてしまった。・・だから・・皆に見せたくないんだと。・・」
それを聞いて皆押し黙った。気づくとカケルは涙を零している。
「大丈夫よ!・・ねえ、皆でこの湯の周りに囲いを作りましょう。目隠しを作れば、かか様も気にすることなく入れる。」
言い出したのは、イツキだった。すぐに、近くの竹を切りだした。竹は四つに割られ板にした。ナギが家から細縄を持ってきて、竹の目隠しを作った。出来上がった頃、ナギは、ナミを迎えに行った。背負子に乗ったナミを、村の皆で迎えた。
「さあ、これでいいだろう。・・俺が抱えてやる。大丈夫だ。カケルが見つけた湯だ。綺麗に体を清め、毒を出してやればきっと良くなる。さあ。」
ナギは、ナミを抱え、目隠しの中へ入っていった。しばらくすると、湯船に浸かる音がした。
「ああ・・・良い気持ちだ・・なあ、ナミ、どうだ?」
「ええ・・とっても・・・体が芯から温まる・・・気持ちいいわ。痛いのを忘れられる・・ほんとに、ありがとう、カケル。皆さん・・本当にありがとう・・・」
ナミは、ナギに抱えられたまま湯船に浸かり、涙を流していた。
「おい、カケル。イツキ。お前たちも来い。カカ様の体を綺麗にしてやろう。」

タグ:湯治 温泉 霧島
-帰還-6.毛むくじゃら [アスカケ第1部 高千穂峰]
6.毛むくじゃら
冬の寒さを感じる季節になると、村の人々は、夜明けとともに、温泉に入るようになっていた。
「朝入ると、一日ぽかぽかして、畑仕事も苦じゃなくなったよ。」
「うちの婆様なんか、一日何度も入ってるんだ。何だか近頃、元気になったよ。」
皆、温泉に入るようになって、前以上に働くようになり、村の中は元気になっていた。
ある日の事、ケスキの母モヨが血相を変えて村に戻ってきた。
「大変だよ!・・温泉に、熊が・・熊が入ってるんだ!」
その声は、総長の静かな村に響き渡り、数人が家から飛び出してきた。モヨの夫シシトも驚いて家から出てきた。
「お前、ちゃんと見たのか?・・本当に熊だったのか?」
「ああ。間違いない。真っ黒で毛むくじゃらで、のそのそ動いて湯に浸かっていた。時々、ウォーって叫んでたし・・」
その話を聞いて、シシトは首をかしげた。
「おかしいなあ,熊はもうねぐらに入ってる頃だぞ。・・・」
そこに、タカヒコやナギもやってきた。
「猟の支度をしていこう。熊なら仕留めて、冬の食いものにしよう。」
そう言って、タカヒコ、ナギ、シシトは温泉に向かった。少し遅れて、カケルとイツキも行った。
入り口で一旦皆立ち止まった。そして、ナギが言った。
「温泉の下は崖になってる。人の気配を察して、下に逃げるかもしれぬ。俺とシシトは下に回ろう。タカヒコは、サチ(弓矢)で後ろから狙ってくれ。」
そう言って、ナギとシシトは、入り口の横から、土手伝いに下へ回り込んだ。タカヒコは弓を構えて、そっと温泉の入り口を上がった。その頃、ようやく、カケルとイツキが追いついた。伏せた姿でじりじりと入り口を上がっていくタカヒコ。竹の囲いの隙間から、確かに、毛むくじゃらの黒い生き物が湯に浸かっているのを確認した。
「ここからじゃ、まだ遠いな・・・囲いも邪魔だ。もう少し・・・」
伏せた姿のまま、徐々に近づいていく。囲いを避けるために、湯が噴き出している井戸を通りすぎた。そして、ゆっくりと弓を引いて狙いを定めた時だった。
「おや、誰かいるのか?」
黒い毛むくじゃらの生き物は言葉を発したのだ。タカヒコは驚いて、弓を置いた。カケルも声を聞き、人間だとわかってから、湯船に飛び込んだ。そして、
「お前は誰だ!ここで何してる!」
と問い詰めた。
「何だ?お前は。・・ナレの村の者か?・・名は何という。父様は誰だ?」
「うるさい。ここは、村の人の大切な湯だ。皆、朝湯に浸かるのを楽しみにしてるんだ。」
「おお、そうか。ナレの村にこんな温泉があったなんてなあ・・」
そうしていると、タカヒコとイツキも顔を見せた。それを見た男が、
「・・おお、タカヒコ様じゃないか。俺だよ、アラヒコ・・アラヒコだよ!」
毛むくじゃらは、数年前にアスカケに旅立ったアラヒコだった。父は長老のテイシ、母は巫女セイであった。したがって、アラヒコはいずれこの村を束ねる長となる人物であった。タカヒコより10歳ほど年下で、タカヒコがアスカケに出た時にはまだ5歳の子どもだったのだ。
「アラヒコ?・・あの泣き虫のアラヒコか?」
「泣き虫は余分だな。・・戻ってきたよ。」
そうと判って、タカヒコは、シシトとナギを呼び寄せた。
「シシト様、ナギ様、今、戻りました。」
アラヒコは湯に浸かったまま挨拶をした。
毛むくじゃらだったのは、長い旅のなかで伸び放題だった髪を洗い流すために、解いたためだった。そして、全身も黒い毛で覆われていたのだった。
「それにしても、お前、本当にアラヒコか?」
「ああ、アスカケで随分体を使った。自分でもおかしいくらい、大きくなった。」
そう言って、湯船から立ち上がると、シシトもナギもタカヒコも、アラヒコを見上げる事になったのだ。本人が言うように、人とは思えないほど大きくがっしりとした体だった。モヨが熊と間違えても仕方ないほどの巨漢だったのだ。
「それにしても・・いい湯だ。・・こんな湯があったとは知らなかった。・・・村に辿り付いた時、白い湯気が立ち上っていたんで、まさかと思って覗いたら、この湯だ。村に戻る前に、綺麗にしたほうが良いかと思ったんだが・・・。」
「お前、熊と間違えられてたんだぞ。」
「熊?・・ああ、あちこちの村でも同じ事を言われたよ。わっはっは・・」
そう言って、久しぶりの対面に、皆、喜びあって笑った。
そうしているうちに、他の村人も、湯に入れるのか心配顔でやってきていて、ミコト達の笑い声に安心して、温泉に入ってきた。
「アラヒコか?」
「何だか、大男になったねえ。これからは、力仕事はアラヒコに頼むとしよう。」
そんな会話があちこちで聞かれた。ナギが言った。
「さあ、もう湯は良かろう。長老や巫女様もきっとお前の帰りを待っておられる。村に戻るぞ。」
「僕、おさ様に伝えてくるよ。」
カケルが一足先に村に戻っていった。

冬の寒さを感じる季節になると、村の人々は、夜明けとともに、温泉に入るようになっていた。
「朝入ると、一日ぽかぽかして、畑仕事も苦じゃなくなったよ。」
「うちの婆様なんか、一日何度も入ってるんだ。何だか近頃、元気になったよ。」
皆、温泉に入るようになって、前以上に働くようになり、村の中は元気になっていた。
ある日の事、ケスキの母モヨが血相を変えて村に戻ってきた。
「大変だよ!・・温泉に、熊が・・熊が入ってるんだ!」
その声は、総長の静かな村に響き渡り、数人が家から飛び出してきた。モヨの夫シシトも驚いて家から出てきた。
「お前、ちゃんと見たのか?・・本当に熊だったのか?」
「ああ。間違いない。真っ黒で毛むくじゃらで、のそのそ動いて湯に浸かっていた。時々、ウォーって叫んでたし・・」
その話を聞いて、シシトは首をかしげた。
「おかしいなあ,熊はもうねぐらに入ってる頃だぞ。・・・」
そこに、タカヒコやナギもやってきた。
「猟の支度をしていこう。熊なら仕留めて、冬の食いものにしよう。」
そう言って、タカヒコ、ナギ、シシトは温泉に向かった。少し遅れて、カケルとイツキも行った。
入り口で一旦皆立ち止まった。そして、ナギが言った。
「温泉の下は崖になってる。人の気配を察して、下に逃げるかもしれぬ。俺とシシトは下に回ろう。タカヒコは、サチ(弓矢)で後ろから狙ってくれ。」
そう言って、ナギとシシトは、入り口の横から、土手伝いに下へ回り込んだ。タカヒコは弓を構えて、そっと温泉の入り口を上がった。その頃、ようやく、カケルとイツキが追いついた。伏せた姿でじりじりと入り口を上がっていくタカヒコ。竹の囲いの隙間から、確かに、毛むくじゃらの黒い生き物が湯に浸かっているのを確認した。
「ここからじゃ、まだ遠いな・・・囲いも邪魔だ。もう少し・・・」
伏せた姿のまま、徐々に近づいていく。囲いを避けるために、湯が噴き出している井戸を通りすぎた。そして、ゆっくりと弓を引いて狙いを定めた時だった。
「おや、誰かいるのか?」
黒い毛むくじゃらの生き物は言葉を発したのだ。タカヒコは驚いて、弓を置いた。カケルも声を聞き、人間だとわかってから、湯船に飛び込んだ。そして、
「お前は誰だ!ここで何してる!」
と問い詰めた。
「何だ?お前は。・・ナレの村の者か?・・名は何という。父様は誰だ?」
「うるさい。ここは、村の人の大切な湯だ。皆、朝湯に浸かるのを楽しみにしてるんだ。」
「おお、そうか。ナレの村にこんな温泉があったなんてなあ・・」
そうしていると、タカヒコとイツキも顔を見せた。それを見た男が、
「・・おお、タカヒコ様じゃないか。俺だよ、アラヒコ・・アラヒコだよ!」
毛むくじゃらは、数年前にアスカケに旅立ったアラヒコだった。父は長老のテイシ、母は巫女セイであった。したがって、アラヒコはいずれこの村を束ねる長となる人物であった。タカヒコより10歳ほど年下で、タカヒコがアスカケに出た時にはまだ5歳の子どもだったのだ。
「アラヒコ?・・あの泣き虫のアラヒコか?」
「泣き虫は余分だな。・・戻ってきたよ。」
そうと判って、タカヒコは、シシトとナギを呼び寄せた。
「シシト様、ナギ様、今、戻りました。」
アラヒコは湯に浸かったまま挨拶をした。
毛むくじゃらだったのは、長い旅のなかで伸び放題だった髪を洗い流すために、解いたためだった。そして、全身も黒い毛で覆われていたのだった。
「それにしても、お前、本当にアラヒコか?」
「ああ、アスカケで随分体を使った。自分でもおかしいくらい、大きくなった。」
そう言って、湯船から立ち上がると、シシトもナギもタカヒコも、アラヒコを見上げる事になったのだ。本人が言うように、人とは思えないほど大きくがっしりとした体だった。モヨが熊と間違えても仕方ないほどの巨漢だったのだ。
「それにしても・・いい湯だ。・・こんな湯があったとは知らなかった。・・・村に辿り付いた時、白い湯気が立ち上っていたんで、まさかと思って覗いたら、この湯だ。村に戻る前に、綺麗にしたほうが良いかと思ったんだが・・・。」
「お前、熊と間違えられてたんだぞ。」
「熊?・・ああ、あちこちの村でも同じ事を言われたよ。わっはっは・・」
そう言って、久しぶりの対面に、皆、喜びあって笑った。
そうしているうちに、他の村人も、湯に入れるのか心配顔でやってきていて、ミコト達の笑い声に安心して、温泉に入ってきた。
「アラヒコか?」
「何だか、大男になったねえ。これからは、力仕事はアラヒコに頼むとしよう。」
そんな会話があちこちで聞かれた。ナギが言った。
「さあ、もう湯は良かろう。長老や巫女様もきっとお前の帰りを待っておられる。村に戻るぞ。」
「僕、おさ様に伝えてくるよ。」
カケルが一足先に村に戻っていった。

タグ:帰還 アラヒコ
-帰還-7.土産話 [アスカケ第1部 高千穂峰]
7.土産話
その夜、アラヒコの帰還を祝う宴が開かれた。アスカケから戻る若者は、二人に一人。村に戻るということは、自らの生きる意味を見つけたという事であり、村に大きな富や幸せをもたらす事を意味していた。無事に戻ったというだけでなく、村にはこの上ない喜びの日なのであった。
篝火が村中に立てられ、村の真ん中にある広場には大きな焚き火が設えられた。アスカケに旅立ったケスキの時と同様に、皆、ご馳走を持ち寄り、アラヒコを取り巻いて宴に興じている。
アラヒコに最も興味をもったのは、カケルであった。ケスキの旅立ちの時はまだ八つで、アスカケなど遠い未来の事だと思っていた。11歳になり、あと数年でアスカケに旅立つと思うと、帰還したアラヒコが、どんな旅をしてきたのか、外の世界はどうなのか、全て聞いてみたいと思っていた。宴の最中も、アラヒコの隣にいて、アラヒコの話す事を聞き漏らさぬようにしていた。
濁酒を注がれながら、アラヒコはアスカケの旅の話を始めた。
「俺のアスカケは、これだ!」
アラヒコが、ずっしりと重みのある麻袋を持ち、立ち上がった。そして、袋の中に手を入れ、ごそごそと動かして、何かを掴んだ。そして、皆の前に広げた手のひらには、小さな塊があった。
「何だ、それは?」
そばに居たタカヒコが尋ねると、アラヒコは得意げな顔で言った。
「これは、桃の種だ。・・桃というのは不老不死の薬と言われておる。これをこの村に植えるのだ。皆、この村のものは長生きになる。どうだ!」
隣に居たカケルは目を輝かせて聞いた。そして、館の書物にも、不老不死の力を持つ果実として描かれていた事を思い出していた。
「他にもあるぞ。・・これが杏、これは梅、これは・・なんだったかな?・・まあいいんだ。とにかくこいつを村のあちこちに植えて、実を採るんだ。」
そして座り込むと、また濁酒を飲んだ。ナギがそんなアラヒコに言った。
「まあ、いいさ。・・だが、少し、お前のアスカケの旅の様子を教えろ。」
「そうか?・・じゃあ、そうするか。」
また濁酒を飲んで話し始めた。

「俺は、村を出て東に歩いた。一日ほど歩いたところに、大きな池があって、確か〈御池(みいけ〉と呼んでいたな。池のそばには、ここみたいな村があった。ユイの村と言っておった。ほとんどここと変わらぬ暮らしだった。そうだ、その村で、ナギ様の事を訊かれたよ。」
ナギは自分の名が出たことに驚いたが、思い出したように言った。
「・・ユイか。・・そうだ、アスカケから戻る途中に行った村だ。」
「え、とと様もその村に?」
「ああ、アスカケから戻る途中、ナミが疲れからか少し体を痛めてしまって、その村でしばらく養生させてもらったんだ。皆、元気だったか?」
「ああ、皆、元気そうだ。ナギ様には随分感謝していると言っていた。暮らしが随分楽になったと言ってたな。」
「とと様、その村で何をしたの?」
「いや、ナミの体が戻るまで、村でいろいろとな・・ユイの村は、男が少なかったんだ。何でも、はやり病で力仕事のできる男が何人か死んでしまって、女と子どもばかりだった。・・だから、村のあちこちが傷んだままだったんで、俺は村に居る間に、お礼のために修理した。堀も深くして獣除けも大きくした。水を引くための水路も作った。・・・そうだ、村から池に出るための橋も掛けた。・・あの橋は今も使ってるだろうか。」
「ああ、しっかり使えていた。少しも痛んでいなかった。・・それと、男の子も大きくなって、村の仕事をしっかりやっていた。あの村はもう元気だ。また、いつか来て欲しいと言っていた。」
「ああ、そうか・・そんなに遠いところではないからな。またいつか訪れてみるとするか・・」
ナギは、その話を聞き、満足そうな顔をしていた。
「それから、俺は北に向かった。ユイの村で、北に行くと大きな村があると聞いたんだ。小さな丘をいくつか越えた先に、大きな村があった。いや、あれは国だ。ヒムカの国と呼んでおった。こことは比べ物にならないほど大きな村があった。だが、そこには女が一人もいないんだ。」
「女が居ないって?子どもも居ないのか。」
タカヒコガ少し酔った様子で訊く。
「ああ、そうだ。・・なぜなら、そこはただの村じゃない。戦をするための村だった。男たちは、剣や弓を持ち、戦いの支度をしてたんだ。食い物とかは、周りの村から運んでくる。ヒムカの王が、海の向こうからやってくる敵に備えるために作ったんだ。・・俺はしばらくそこで暮らした。来る日も来る日も、剣や弓の練習をした。大きな石を転がしたり、そうだ、石投げの練習もした。夜になると腹いっぱい食べて寝た。そのうちに、俺の体はこんなに大きくなった。その村の誰よりも大きくなった。」
「戦をしたの?」
カケルが少し遠慮がちに訊いた。アラヒコはにやりと笑ってこう答えた。
「いや・・・戦などない。・・・後で聞いたが、ヒムカの国の王は、随分と気弱で、昔、海から異人が来たのに遭遇して、怖くて怖くてたまらなかったらしい。」
「じゃあ、戦というのは?」
「あるわけも無い。・・なのに、そのために村々から食い物を集め、男たちを養う。村々はみな貧しい暮らしをしているのに、戦に供える男たちと王様だけは優雅な暮らしだ。・・俺は、しばらく居たが、そういう暮らしが嫌になった。俺のアスカケはこんなところには無いと決めて、その村を離れて、海辺の小さな村に行ったんだ。」
その夜、アラヒコの帰還を祝う宴が開かれた。アスカケから戻る若者は、二人に一人。村に戻るということは、自らの生きる意味を見つけたという事であり、村に大きな富や幸せをもたらす事を意味していた。無事に戻ったというだけでなく、村にはこの上ない喜びの日なのであった。
篝火が村中に立てられ、村の真ん中にある広場には大きな焚き火が設えられた。アスカケに旅立ったケスキの時と同様に、皆、ご馳走を持ち寄り、アラヒコを取り巻いて宴に興じている。
アラヒコに最も興味をもったのは、カケルであった。ケスキの旅立ちの時はまだ八つで、アスカケなど遠い未来の事だと思っていた。11歳になり、あと数年でアスカケに旅立つと思うと、帰還したアラヒコが、どんな旅をしてきたのか、外の世界はどうなのか、全て聞いてみたいと思っていた。宴の最中も、アラヒコの隣にいて、アラヒコの話す事を聞き漏らさぬようにしていた。
濁酒を注がれながら、アラヒコはアスカケの旅の話を始めた。
「俺のアスカケは、これだ!」
アラヒコが、ずっしりと重みのある麻袋を持ち、立ち上がった。そして、袋の中に手を入れ、ごそごそと動かして、何かを掴んだ。そして、皆の前に広げた手のひらには、小さな塊があった。
「何だ、それは?」
そばに居たタカヒコが尋ねると、アラヒコは得意げな顔で言った。
「これは、桃の種だ。・・桃というのは不老不死の薬と言われておる。これをこの村に植えるのだ。皆、この村のものは長生きになる。どうだ!」
隣に居たカケルは目を輝かせて聞いた。そして、館の書物にも、不老不死の力を持つ果実として描かれていた事を思い出していた。
「他にもあるぞ。・・これが杏、これは梅、これは・・なんだったかな?・・まあいいんだ。とにかくこいつを村のあちこちに植えて、実を採るんだ。」
そして座り込むと、また濁酒を飲んだ。ナギがそんなアラヒコに言った。
「まあ、いいさ。・・だが、少し、お前のアスカケの旅の様子を教えろ。」
「そうか?・・じゃあ、そうするか。」
また濁酒を飲んで話し始めた。

「俺は、村を出て東に歩いた。一日ほど歩いたところに、大きな池があって、確か〈御池(みいけ〉と呼んでいたな。池のそばには、ここみたいな村があった。ユイの村と言っておった。ほとんどここと変わらぬ暮らしだった。そうだ、その村で、ナギ様の事を訊かれたよ。」
ナギは自分の名が出たことに驚いたが、思い出したように言った。
「・・ユイか。・・そうだ、アスカケから戻る途中に行った村だ。」
「え、とと様もその村に?」
「ああ、アスカケから戻る途中、ナミが疲れからか少し体を痛めてしまって、その村でしばらく養生させてもらったんだ。皆、元気だったか?」
「ああ、皆、元気そうだ。ナギ様には随分感謝していると言っていた。暮らしが随分楽になったと言ってたな。」
「とと様、その村で何をしたの?」
「いや、ナミの体が戻るまで、村でいろいろとな・・ユイの村は、男が少なかったんだ。何でも、はやり病で力仕事のできる男が何人か死んでしまって、女と子どもばかりだった。・・だから、村のあちこちが傷んだままだったんで、俺は村に居る間に、お礼のために修理した。堀も深くして獣除けも大きくした。水を引くための水路も作った。・・・そうだ、村から池に出るための橋も掛けた。・・あの橋は今も使ってるだろうか。」
「ああ、しっかり使えていた。少しも痛んでいなかった。・・それと、男の子も大きくなって、村の仕事をしっかりやっていた。あの村はもう元気だ。また、いつか来て欲しいと言っていた。」
「ああ、そうか・・そんなに遠いところではないからな。またいつか訪れてみるとするか・・」
ナギは、その話を聞き、満足そうな顔をしていた。
「それから、俺は北に向かった。ユイの村で、北に行くと大きな村があると聞いたんだ。小さな丘をいくつか越えた先に、大きな村があった。いや、あれは国だ。ヒムカの国と呼んでおった。こことは比べ物にならないほど大きな村があった。だが、そこには女が一人もいないんだ。」
「女が居ないって?子どもも居ないのか。」
タカヒコガ少し酔った様子で訊く。
「ああ、そうだ。・・なぜなら、そこはただの村じゃない。戦をするための村だった。男たちは、剣や弓を持ち、戦いの支度をしてたんだ。食い物とかは、周りの村から運んでくる。ヒムカの王が、海の向こうからやってくる敵に備えるために作ったんだ。・・俺はしばらくそこで暮らした。来る日も来る日も、剣や弓の練習をした。大きな石を転がしたり、そうだ、石投げの練習もした。夜になると腹いっぱい食べて寝た。そのうちに、俺の体はこんなに大きくなった。その村の誰よりも大きくなった。」
「戦をしたの?」
カケルが少し遠慮がちに訊いた。アラヒコはにやりと笑ってこう答えた。
「いや・・・戦などない。・・・後で聞いたが、ヒムカの国の王は、随分と気弱で、昔、海から異人が来たのに遭遇して、怖くて怖くてたまらなかったらしい。」
「じゃあ、戦というのは?」
「あるわけも無い。・・なのに、そのために村々から食い物を集め、男たちを養う。村々はみな貧しい暮らしをしているのに、戦に供える男たちと王様だけは優雅な暮らしだ。・・俺は、しばらく居たが、そういう暮らしが嫌になった。俺のアスカケはこんなところには無いと決めて、その村を離れて、海辺の小さな村に行ったんだ。」
-帰還-8.海辺の村 [アスカケ第1部 高千穂峰]
8.海辺の村
「海って・・あの波に飲まれたら死んじゃうっていう怖いところ?」
カケルは海を見たことが無い。ケスキの旅立ちの日に、ケスキの父から聞いた話でしか知らなかった。
「ん?・・・海って、お前は知らないのか。」
カケルはこくりと頷いた。
「海は広くて青い。どこまでも続いている。優しい時も厳しい時もある。確かに、海に出て死ぬ事もある。だが、海には、もっと良いことがたくさんある。魚は、ここの川魚とは比べ物にならないくらい大きい。・・そうだ、お前の背丈以上の大きな魚だっている。旨い貝や海草も取れる。食い物には困らないんだよ。」
「銛を使って獲るの?」
「ああ、だが、皆は網を使う。舟で海へ出て網を広げ、泳いでいる魚を捕らえるんだ。それはにぎやかで楽しい。そしてたくさん獲れる。」
「アラヒコは、そこでアスカケを探したの?」
「ああ・・そのために、先ず、舟を作る技を教えてもらって、海へ出ることにしたんだ。」
「船を作るって・・どれくらいの舟を作ったんだ?」
タカヒコも興味深そうに訊いた。
「いや・・そんな大きなものじゃない。自分が乗るくらいの舟さ。海辺には、そんなに大きな木もないからな。だが、それでもなかなか手間が掛かる。削って縛って、波にもひっくり返らないように何度も何度も作り直す。ちゃんと乗れる舟ができるのには1年くらい掛かるんだ。」
「それで・・海に出たの?」
今度は、イツキが訊ねた。アラヒコは、イツキのほうを向いて、にやりと笑ってからこう言った。
「ああ、天気の良い日に、村のみんなと一緒に沖へ出た。しばらく行くと、陸が見えなくなる。自分がどっちへ向かっているか判らなくなるんだ。そりゃあ怖かったよ。・・だけど、近くに仲間がいる。声を掛け合って沖へ沖へと向かったんだ。それから、みんなで網を広げた。びっくりするくらい魚が獲れたよ。もう夢中で魚を捕まえた。」
カケルも川では鮎やヤマメを捕まえている。だが、アラヒコの話に出てくる魚はもっともっと大きい。カケルも、そんな大きな魚を捕まえたくて、アラヒコの話を聞きながらドキドキしてきた。
「ぼくもいつか海へ行きたい!そして大きな魚を捕まえたい!」
「おおっ、そうか。カケルも捕まえたいか。なら、アスカケに出るんだな。お前なら、きっと鯨も捕まえられるだろう。」
耳慣れない言葉が出てきて、カケルは戸惑った。
「くじら?」
「ああ、くじらはなあ・・大きいんだ。俺なんかよりずっと大きい。口も大きくて、飲み込まれたらひとたまりもない。舟だって木っ端微塵だ。黒くておっかない。」
「そんな恐ろしいものが海にいるの?」
イツキがそっと訊いた。アラヒコはイツキを見て、ちょっと言い過ぎたと反省して、
「いや・・滅多に会うもんじゃない。それに、普段は何も怖くない。人間が捕まえようとして銛を打ったり、追い込んだりするから暴れるのさ。・・生き物はみなそうさ。森にいる熊だって鹿だって、猿だって、みな、おとなしく生きてる。こっちから何かしない限り、滅多に襲ったりはしないんだ。」
タカヒコもナギも、頷いて、イツキやカケルを見た。そして、ナギが、
「そうだぞ。・・人間ってのが一番厄介なんだ。それぞれ、生き物には自分の縄張りがあって、静かに暮らしてる。でも、人間は、どこにでも入っていく。山深くまで踏み入れて、生き物を取る。木を切る。実を摘む。・・みな、生きてるんだからな。やたらに傷つけてはならんのだ。」
カケルとイツキは神妙な面持ちで、ナギの話を聞いた。周りに居た村人たちも、押し黙った。
「なんだい、俺の話の続きはまだあるぞ。」
静かになった様子を破るように、アラヒコが話を続ける。
「実はな、何度か海に出るうちに、俺も要領を得た。海には、小さな島というのがある。・・そうだな・・川から岩が突き出るみたいに、海にも岩が突き出ているところや、大きな山があるんだ。それを島というんだが・・ある日、俺は、その島が並んでいるところまで舟を進めたんだ。村の長からも、あそこにはいい魚が獲れるところがあると聞いたんでなあ。」
アラヒコは、濁酒をぐいっと飲むと話を続ける。
「そこで俺は人に会った。・・・いや、その島に人が居たんだ。・・そう、海の向こうにある国からの使者だった。荒波で舟が壊れ、流されてたどり着いたらしい。三人居たが、二人はもう死んでいた。たった一人残っていた男も、随分、弱っていた。すぐに俺の船に乗せて、村に戻ったんだ。しばらく養生してから、話を聞くと、海の向うにあるイヨの国王の使者だと言うんだ。ヒムカの国へ王の手紙を届けるところだったらしい。だが、荒波で全てを無くしたと言った。」
「それで、どうしたの?」
「俺は、その男を連れて、イヨの国へ行く事にした。このまま、ヒムカの国へ行っても、無駄だと教え、俺の舟で海を渡る事にしたんだ。」

「海って・・あの波に飲まれたら死んじゃうっていう怖いところ?」
カケルは海を見たことが無い。ケスキの旅立ちの日に、ケスキの父から聞いた話でしか知らなかった。
「ん?・・・海って、お前は知らないのか。」
カケルはこくりと頷いた。
「海は広くて青い。どこまでも続いている。優しい時も厳しい時もある。確かに、海に出て死ぬ事もある。だが、海には、もっと良いことがたくさんある。魚は、ここの川魚とは比べ物にならないくらい大きい。・・そうだ、お前の背丈以上の大きな魚だっている。旨い貝や海草も取れる。食い物には困らないんだよ。」
「銛を使って獲るの?」
「ああ、だが、皆は網を使う。舟で海へ出て網を広げ、泳いでいる魚を捕らえるんだ。それはにぎやかで楽しい。そしてたくさん獲れる。」
「アラヒコは、そこでアスカケを探したの?」
「ああ・・そのために、先ず、舟を作る技を教えてもらって、海へ出ることにしたんだ。」
「船を作るって・・どれくらいの舟を作ったんだ?」
タカヒコも興味深そうに訊いた。
「いや・・そんな大きなものじゃない。自分が乗るくらいの舟さ。海辺には、そんなに大きな木もないからな。だが、それでもなかなか手間が掛かる。削って縛って、波にもひっくり返らないように何度も何度も作り直す。ちゃんと乗れる舟ができるのには1年くらい掛かるんだ。」
「それで・・海に出たの?」
今度は、イツキが訊ねた。アラヒコは、イツキのほうを向いて、にやりと笑ってからこう言った。
「ああ、天気の良い日に、村のみんなと一緒に沖へ出た。しばらく行くと、陸が見えなくなる。自分がどっちへ向かっているか判らなくなるんだ。そりゃあ怖かったよ。・・だけど、近くに仲間がいる。声を掛け合って沖へ沖へと向かったんだ。それから、みんなで網を広げた。びっくりするくらい魚が獲れたよ。もう夢中で魚を捕まえた。」
カケルも川では鮎やヤマメを捕まえている。だが、アラヒコの話に出てくる魚はもっともっと大きい。カケルも、そんな大きな魚を捕まえたくて、アラヒコの話を聞きながらドキドキしてきた。
「ぼくもいつか海へ行きたい!そして大きな魚を捕まえたい!」
「おおっ、そうか。カケルも捕まえたいか。なら、アスカケに出るんだな。お前なら、きっと鯨も捕まえられるだろう。」
耳慣れない言葉が出てきて、カケルは戸惑った。
「くじら?」
「ああ、くじらはなあ・・大きいんだ。俺なんかよりずっと大きい。口も大きくて、飲み込まれたらひとたまりもない。舟だって木っ端微塵だ。黒くておっかない。」
「そんな恐ろしいものが海にいるの?」
イツキがそっと訊いた。アラヒコはイツキを見て、ちょっと言い過ぎたと反省して、
「いや・・滅多に会うもんじゃない。それに、普段は何も怖くない。人間が捕まえようとして銛を打ったり、追い込んだりするから暴れるのさ。・・生き物はみなそうさ。森にいる熊だって鹿だって、猿だって、みな、おとなしく生きてる。こっちから何かしない限り、滅多に襲ったりはしないんだ。」
タカヒコもナギも、頷いて、イツキやカケルを見た。そして、ナギが、
「そうだぞ。・・人間ってのが一番厄介なんだ。それぞれ、生き物には自分の縄張りがあって、静かに暮らしてる。でも、人間は、どこにでも入っていく。山深くまで踏み入れて、生き物を取る。木を切る。実を摘む。・・みな、生きてるんだからな。やたらに傷つけてはならんのだ。」
カケルとイツキは神妙な面持ちで、ナギの話を聞いた。周りに居た村人たちも、押し黙った。
「なんだい、俺の話の続きはまだあるぞ。」
静かになった様子を破るように、アラヒコが話を続ける。
「実はな、何度か海に出るうちに、俺も要領を得た。海には、小さな島というのがある。・・そうだな・・川から岩が突き出るみたいに、海にも岩が突き出ているところや、大きな山があるんだ。それを島というんだが・・ある日、俺は、その島が並んでいるところまで舟を進めたんだ。村の長からも、あそこにはいい魚が獲れるところがあると聞いたんでなあ。」
アラヒコは、濁酒をぐいっと飲むと話を続ける。
「そこで俺は人に会った。・・・いや、その島に人が居たんだ。・・そう、海の向こうにある国からの使者だった。荒波で舟が壊れ、流されてたどり着いたらしい。三人居たが、二人はもう死んでいた。たった一人残っていた男も、随分、弱っていた。すぐに俺の船に乗せて、村に戻ったんだ。しばらく養生してから、話を聞くと、海の向うにあるイヨの国王の使者だと言うんだ。ヒムカの国へ王の手紙を届けるところだったらしい。だが、荒波で全てを無くしたと言った。」
「それで、どうしたの?」
「俺は、その男を連れて、イヨの国へ行く事にした。このまま、ヒムカの国へ行っても、無駄だと教え、俺の舟で海を渡る事にしたんだ。」

-帰還-9.イヨの国 [アスカケ第1部 高千穂峰]
9.イヨの国
アラヒコは、ついにイヨの国に渡った話に入った。
「イヨまで船で行くには、数日かかった。水や食料を積み、少しずつ船を進めた。西風は強くなってくる季節、海は少し荒れたが、風に乗り思った以上に早く着けたんだ。」
「イヨ国はどんなところだった?」
タカヒコガ訊く。
「・・・良いところだ。なだらかな丘、広い田畑、そして海、のんびりとした良いところだ。」
「温かく迎えてくれたのか?」
「ああ、国王の使者とともに戻ったのだ。すぐに、国王の館へ案内された。国王はもう高齢で、ほとんど館からは出ることはなく、代わりに国王の娘が出迎えてくれた。名を乙姫〈オツキ〉と言ったな。」
タカヒコガ身を乗り出して、アラヒコに尋ねた。
「おい、そのオツキ様は綺麗か?」
アラヒコは少し戸惑い、辺りを見回し、囁くような声で、
「・・ああ・・見たことも無いほど綺麗だ。肌が白く、長い黒髪で・・・。」
「おお・・それは・・一度お目にかかりたいものだ。」
タカヒコガニヤニヤしながら答えた。横から、ハルがタカヒコの腕を抓った。
「いたたたた・・何するんだよ・・・」痛がるタカヒコを見て皆笑った。
「ねえ、アラヒコはそこで何をしたの?」
皆が笑っている様子がよくわからず、それよりもアラヒコの土産話にわくわくしながらもっと聞きたくてしょうがなかった。
「・・ああ、その日は、乙姫様が宴を催してくれた。館には広い部屋があって・・そうだな・・この村の皆が入れるほど・・いやそれ以上に大きな部屋があって、目の前には、海の幸・山の幸・・とにかくありとあらゆるものが並べられた。俺はそれをつまみながら、目の前では、若い娘たちの舞や笛の音で、一晩中、楽しく過ごしたよ。」
「いいなあ・・」と漏らしたタカヒコが、ハルにまた抓られた。
「だが、宴はその日だけではなかったんだ。次の日から三日と開けず、村々の長たちが入れ替わりに、王の館にやってきて、海の向こうの異国の話を聞かせてくれとせがむんだ。・・・そんな日が、ふた月・・いや三月も続いたのだ。・・・いかに楽しい宴でもそう続けば、おかしくなる。・・俺は乙姫様に言ったのだ。アスカケの途中であり、自らの生きる道を見つけなければならない。そろそろ旅立ちたいと。」
「どうなった?」
「乙姫様は、それならば、しばらく、この国に住み、見つければよいと言い、家を用意してくれた。それから俺は、畑仕事や山の仕事、海の仕事、とにかくできることは何でもやってみた。力仕事もたくさん引き受けた。そのたびに、皆、俺に美味いものをくれたのだ。中でも、この桃がとても美味かった。だから、この桃を手に入れたいと思ったのだ。」
「山に取りに行くのか?」
「いや、これは山に実るのではない。木を植え、手入れをし、花を咲かせ、大きな実を取るのだ。乙姫様の館の近くにも、畑があり、桃を育てていた。・・他にも、杏や梨も作れるのだ。」
それを聞いて、長老が興味を示した。
「畑でそんなものが作れるのか・・・」
「イヨの国には、そうした畑があちこちにある。みな、自分で好きなものを植えている。春には綺麗な花も咲き、見事だった。」
長老の脇で話を聞いていた、スズが聞いた。スズは村一番の食いしん坊で、旨いものには目がなかったのだ。
「その・・・ももというのはどれくらい美味いのだ?」
「白い実をかじると、中から甘い汁が吹きだしてくる。それをすすりながら食べると、もう口の中はとろとろになる。・・思い出すだけで、よだれが出てくる・・・。」
「食ってみたいなあ・・。」
それを聞いて、スズは思わず口にした。あちこちで喉をごくりと言わせる音がした。
「そうだろう。俺は、桃を初めて食った時、真っ先に、これをナレの村の皆に食わせたいと思ったのだ。ここには、豊かな森の恵みはある。食べ物に困るような事はなかったが、外に出るともっともっと旨い物がたくさんあった。この村を、もっともっと豊かにしたい。そう思ったんだ。」
「それで・・・さっき見せた種がお前のアスカケなんだな。」
長老は納得したようにアラヒコを見て喜んだ。
「桃の作り方はちゃんと教わった。乙姫様は、国の中でも最も桃作りが上手かったから、館の庭で毎日教えてもらったのだ。3年近く掛かってようやく満足に作れるようになった。」
皆、アラヒコの話をじっと聞くようになっていた。
「そのころだ、こいつが俺にナレの村にもどる時だと教えてくれた。」
アラヒコはそう言うと、大きな麻袋の中から、包みを取りだした。包みは、真っ黒になっていた。

アラヒコは、ついにイヨの国に渡った話に入った。
「イヨまで船で行くには、数日かかった。水や食料を積み、少しずつ船を進めた。西風は強くなってくる季節、海は少し荒れたが、風に乗り思った以上に早く着けたんだ。」
「イヨ国はどんなところだった?」
タカヒコガ訊く。
「・・・良いところだ。なだらかな丘、広い田畑、そして海、のんびりとした良いところだ。」
「温かく迎えてくれたのか?」
「ああ、国王の使者とともに戻ったのだ。すぐに、国王の館へ案内された。国王はもう高齢で、ほとんど館からは出ることはなく、代わりに国王の娘が出迎えてくれた。名を乙姫〈オツキ〉と言ったな。」
タカヒコガ身を乗り出して、アラヒコに尋ねた。
「おい、そのオツキ様は綺麗か?」
アラヒコは少し戸惑い、辺りを見回し、囁くような声で、
「・・ああ・・見たことも無いほど綺麗だ。肌が白く、長い黒髪で・・・。」
「おお・・それは・・一度お目にかかりたいものだ。」
タカヒコガニヤニヤしながら答えた。横から、ハルがタカヒコの腕を抓った。
「いたたたた・・何するんだよ・・・」痛がるタカヒコを見て皆笑った。
「ねえ、アラヒコはそこで何をしたの?」
皆が笑っている様子がよくわからず、それよりもアラヒコの土産話にわくわくしながらもっと聞きたくてしょうがなかった。
「・・ああ、その日は、乙姫様が宴を催してくれた。館には広い部屋があって・・そうだな・・この村の皆が入れるほど・・いやそれ以上に大きな部屋があって、目の前には、海の幸・山の幸・・とにかくありとあらゆるものが並べられた。俺はそれをつまみながら、目の前では、若い娘たちの舞や笛の音で、一晩中、楽しく過ごしたよ。」
「いいなあ・・」と漏らしたタカヒコが、ハルにまた抓られた。
「だが、宴はその日だけではなかったんだ。次の日から三日と開けず、村々の長たちが入れ替わりに、王の館にやってきて、海の向こうの異国の話を聞かせてくれとせがむんだ。・・・そんな日が、ふた月・・いや三月も続いたのだ。・・・いかに楽しい宴でもそう続けば、おかしくなる。・・俺は乙姫様に言ったのだ。アスカケの途中であり、自らの生きる道を見つけなければならない。そろそろ旅立ちたいと。」
「どうなった?」
「乙姫様は、それならば、しばらく、この国に住み、見つければよいと言い、家を用意してくれた。それから俺は、畑仕事や山の仕事、海の仕事、とにかくできることは何でもやってみた。力仕事もたくさん引き受けた。そのたびに、皆、俺に美味いものをくれたのだ。中でも、この桃がとても美味かった。だから、この桃を手に入れたいと思ったのだ。」
「山に取りに行くのか?」
「いや、これは山に実るのではない。木を植え、手入れをし、花を咲かせ、大きな実を取るのだ。乙姫様の館の近くにも、畑があり、桃を育てていた。・・他にも、杏や梨も作れるのだ。」
それを聞いて、長老が興味を示した。
「畑でそんなものが作れるのか・・・」
「イヨの国には、そうした畑があちこちにある。みな、自分で好きなものを植えている。春には綺麗な花も咲き、見事だった。」
長老の脇で話を聞いていた、スズが聞いた。スズは村一番の食いしん坊で、旨いものには目がなかったのだ。
「その・・・ももというのはどれくらい美味いのだ?」
「白い実をかじると、中から甘い汁が吹きだしてくる。それをすすりながら食べると、もう口の中はとろとろになる。・・思い出すだけで、よだれが出てくる・・・。」
「食ってみたいなあ・・。」
それを聞いて、スズは思わず口にした。あちこちで喉をごくりと言わせる音がした。
「そうだろう。俺は、桃を初めて食った時、真っ先に、これをナレの村の皆に食わせたいと思ったのだ。ここには、豊かな森の恵みはある。食べ物に困るような事はなかったが、外に出るともっともっと旨い物がたくさんあった。この村を、もっともっと豊かにしたい。そう思ったんだ。」
「それで・・・さっき見せた種がお前のアスカケなんだな。」
長老は納得したようにアラヒコを見て喜んだ。
「桃の作り方はちゃんと教わった。乙姫様は、国の中でも最も桃作りが上手かったから、館の庭で毎日教えてもらったのだ。3年近く掛かってようやく満足に作れるようになった。」
皆、アラヒコの話をじっと聞くようになっていた。
「そのころだ、こいつが俺にナレの村にもどる時だと教えてくれた。」
アラヒコはそう言うと、大きな麻袋の中から、包みを取りだした。包みは、真っ黒になっていた。

-帰還-10.約束 [アスカケ第1部 高千穂峰]
10.約束
「これは、俺はアスカケに出る日、ミユが俺にくれた。」
ミユの名が出て、皆、驚いた。そして、ミユを探した。
ミユは、タゾヒコとタンの娘で、年はアラヒコより一つ下だった。ミユはタゾヒコの影に隠れるように座っていたが、アラヒコの口から自分の名が出て、驚き、真っ赤になったまま俯いていた。
その様子に村人たちは凡そ理解した。
アスカケに出る青年に恋心を抱く娘。村に戻る青年にその事を伝えてはならないのが、村の女たちの掟になっていたはずだった。だが、その掟に背いてまで、ミユはアラヒコに強い想いを抱いていたという事になる。
「ミユが、アスカケの旅の供にとくれたのだ。毎晩、寝る前に握ってナレの村を思い出していた。そしていつか必ず戻ると誓っていたんだ。」
「そいつが戻る時を教えてくれたとは?」
「ああ、桃の作り方を覚えた頃の夜のことだ。いつものように、こいつを取り出した。」
そういって包みを開くと、中には小さな石があった。
「最初は、真っ黒な、ただの石ころだと思っていた。ナレの村でミユが拾った石を村を忘れぬようにというだけで持たせてくれたのだと思っていた。・・最初は、軽い気持ちで眺めては、時々磨いたりしているうちに、何だか心が落ち着くようになった。それで、俺は、毎晩、握り締めて眠るようになったんだ。」
みな、じっとアラヒコの話を聞いている。
「だが、その日は様子がおかしかった。寝る前にいつものように取り出すと、どこかおかしい。軽く握るとぱくっと割れたんだ。中を見ると・・光っていた。不思議な色の光が広がって、目の前に、ミユの顔が浮かんだ。俺は、会いたくて堪らなくなった。だからすぐに戻る事にしたのだ。」
そう聞いて、村人は皆、アラヒコとミユの心を理解した。
アラヒコは立ち上がり、ミユの傍に行った。
「ミユ、俺はちゃんとアスカケを見つけ戻ってきたぞ。お前のくれた石が俺を守ってくれたおかげだ。ありがとう。約束どおり、俺の妻になってくれるな?」
呆気に取られた村人はしばらく静かになっていた。
タンがミユの背を押した。ミユも立ち上がり、
「ずっとずっと待っていました。よく戻ってきてくださいました。」
そこまでいうと涙をぽろぽろと零し始め、アラヒコはそっと抱きしめたのだ。
村人はみな拍手喝采し喜んだ。
アラヒコの石は、巫女セイに手渡された。
「おお、これは紫水晶という宝じゃな。・・・悪いものを吸い取り良いものを吐き出す・・争いをおさめ、調和を作り出す不思議な石なのじゃ。・・これをミユがアラヒコに・・・いや、これはきっとミユの分身じゃろう。アラヒコにはミユが守り神なのじゃ。」
巫女セイの言葉は、さらに二人の未来を祝福するものとなった。
アラヒコは、ミユとともに、タゾヒコとタンの前に跪いた。そして、
「タゾヒコ様、タン様、我らが夫婦になる事をお許しください。」
そう言って手を着き頭を下げた。
タゾヒコとタンは顔を見合わせ、大きく頷いた。そして、タゾヒコが低く柔らかな声で、
「アラヒコよ。この村を支えるミコトとして、力を尽くしてくれ。そして、この村を豊かな里にしてくれ。ミユはもう何年もお前の事を待っておった。朝な夕なに、大門からお前の姿を探し、帰りを待ちわびておったのだ。幸せにしてやってくれ。」
そう言いながら、アラヒコの手を取り、ミユの手と重ねた。
タンが、加えた。
「もう、二人の暮らす家はあるのよ。・・昔、アラヒコが住んでいた家・・お前がアスカケに出てからも、ミユは毎日のように掃除をしていたから、すぐにも住めるはず。大丈夫、お前たち二人ならしっかりやっていけるはず。」
そう言って、目頭を押さえていた。
アラヒコのアスカケからに帰還を祝う宴は、そのまま、二人の結婚の宴となった。
「ねえ、笛を吹いてよ!」
村の娘たちは、ミコト達に言って、薄絹の衣に着替えて、祝いのための舞を踊った。
カケルもイツキも、エンもケンも、子どもたちも皆、その舞の輪に混ざって踊り楽しんだ。
ナレの村に幸せの輪が広がっていた。

「これは、俺はアスカケに出る日、ミユが俺にくれた。」
ミユの名が出て、皆、驚いた。そして、ミユを探した。
ミユは、タゾヒコとタンの娘で、年はアラヒコより一つ下だった。ミユはタゾヒコの影に隠れるように座っていたが、アラヒコの口から自分の名が出て、驚き、真っ赤になったまま俯いていた。
その様子に村人たちは凡そ理解した。
アスカケに出る青年に恋心を抱く娘。村に戻る青年にその事を伝えてはならないのが、村の女たちの掟になっていたはずだった。だが、その掟に背いてまで、ミユはアラヒコに強い想いを抱いていたという事になる。
「ミユが、アスカケの旅の供にとくれたのだ。毎晩、寝る前に握ってナレの村を思い出していた。そしていつか必ず戻ると誓っていたんだ。」
「そいつが戻る時を教えてくれたとは?」
「ああ、桃の作り方を覚えた頃の夜のことだ。いつものように、こいつを取り出した。」
そういって包みを開くと、中には小さな石があった。
「最初は、真っ黒な、ただの石ころだと思っていた。ナレの村でミユが拾った石を村を忘れぬようにというだけで持たせてくれたのだと思っていた。・・最初は、軽い気持ちで眺めては、時々磨いたりしているうちに、何だか心が落ち着くようになった。それで、俺は、毎晩、握り締めて眠るようになったんだ。」
みな、じっとアラヒコの話を聞いている。
「だが、その日は様子がおかしかった。寝る前にいつものように取り出すと、どこかおかしい。軽く握るとぱくっと割れたんだ。中を見ると・・光っていた。不思議な色の光が広がって、目の前に、ミユの顔が浮かんだ。俺は、会いたくて堪らなくなった。だからすぐに戻る事にしたのだ。」
そう聞いて、村人は皆、アラヒコとミユの心を理解した。
アラヒコは立ち上がり、ミユの傍に行った。
「ミユ、俺はちゃんとアスカケを見つけ戻ってきたぞ。お前のくれた石が俺を守ってくれたおかげだ。ありがとう。約束どおり、俺の妻になってくれるな?」
呆気に取られた村人はしばらく静かになっていた。
タンがミユの背を押した。ミユも立ち上がり、
「ずっとずっと待っていました。よく戻ってきてくださいました。」
そこまでいうと涙をぽろぽろと零し始め、アラヒコはそっと抱きしめたのだ。
村人はみな拍手喝采し喜んだ。
アラヒコの石は、巫女セイに手渡された。
「おお、これは紫水晶という宝じゃな。・・・悪いものを吸い取り良いものを吐き出す・・争いをおさめ、調和を作り出す不思議な石なのじゃ。・・これをミユがアラヒコに・・・いや、これはきっとミユの分身じゃろう。アラヒコにはミユが守り神なのじゃ。」
巫女セイの言葉は、さらに二人の未来を祝福するものとなった。
アラヒコは、ミユとともに、タゾヒコとタンの前に跪いた。そして、
「タゾヒコ様、タン様、我らが夫婦になる事をお許しください。」
そう言って手を着き頭を下げた。
タゾヒコとタンは顔を見合わせ、大きく頷いた。そして、タゾヒコが低く柔らかな声で、
「アラヒコよ。この村を支えるミコトとして、力を尽くしてくれ。そして、この村を豊かな里にしてくれ。ミユはもう何年もお前の事を待っておった。朝な夕なに、大門からお前の姿を探し、帰りを待ちわびておったのだ。幸せにしてやってくれ。」
そう言いながら、アラヒコの手を取り、ミユの手と重ねた。
タンが、加えた。
「もう、二人の暮らす家はあるのよ。・・昔、アラヒコが住んでいた家・・お前がアスカケに出てからも、ミユは毎日のように掃除をしていたから、すぐにも住めるはず。大丈夫、お前たち二人ならしっかりやっていけるはず。」
そう言って、目頭を押さえていた。
アラヒコのアスカケからに帰還を祝う宴は、そのまま、二人の結婚の宴となった。
「ねえ、笛を吹いてよ!」
村の娘たちは、ミコト達に言って、薄絹の衣に着替えて、祝いのための舞を踊った。
カケルもイツキも、エンもケンも、子どもたちも皆、その舞の輪に混ざって踊り楽しんだ。
ナレの村に幸せの輪が広がっていた。

タグ:紫水晶 約束 守り神



